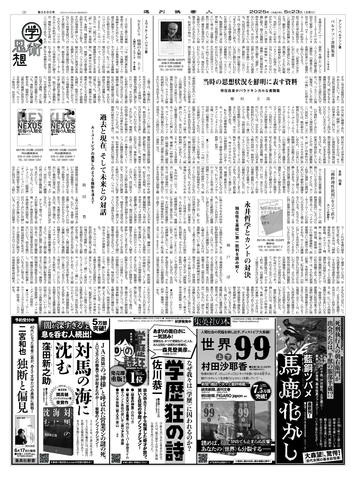- ジャンル:哲学・思想・宗教
- 著者/編者: ユヴァル・ノア・ハラリ
- 評者: 飯田豊
NEXUS 情報の人類史 上・下
ユヴァル・ノア・ハラリ著
飯田 豊
AIは史上最大の情報革命であり、その特異性を理解するためにこそ、過去の情報テクノロジーとの比較が不可欠だ、とハラリはいう。「ネクサス(nexus)」とは「つながり」や「結びつき」、「絆」や「中枢」を意味する。本書は、情報を社会的なネクサスと捉え、それが現実を映しているか否かにかかわらず、つねに人や物事を結びつけてきた歴史に注目する。
そのうえで、ハラリがあらかじめ批判するのが、情報に対する誤った二つの見方である。その一つは「情報の素朴な見方」で、大規模ネットワークが真実を導き、知恵や力を得るとする楽観論のこと。もう一つは「情報のポピュリズム的な見方」で、エリートによる情報操作があることを前提に、真実から目を背け、制度への不信を煽るものだ。ハラリはこの両極のあいだに希望の余地を模索している。本書全体の主張は極めて明快だが、歴史を主軸とする上巻と、コンピューターやAIの考察を中心に据えた下巻とでは、読後の印象にやや差異がある。
上巻では、人類が長い年月をかけて多様な情報テクノロジーを発明し、接続性が飛躍的に強化された一方で、それが必ずしも世界のより正確な把握にはつながらなかった経緯が論じられる。人間社会の大規模な協力は共同主観的現実、すなわち神話などの虚構にもとづいた物語によって初めて可能になった。虚構は単純で快く、複雑で不快な真実よりも人々を団結させやすい。そして官僚制も同様に、秩序のために真実を犠牲にしがちで、人々の理解を歪める。今日の偏ったアルゴリズムや非人間的な手順の多くは、紙の文書と官僚制に起源を持つという。また、不可謬性が保障されたはずの書物、とくに聖典は秩序の基盤とされつつも、実際には多様な解釈を生み、結果的に人々は教会の権威に依存せざるを得なかった。カトリック教会は、社会をエコーチェンバーに閉じ込め、教会が支持する書物だけが広まることを許した、というわけである。
それに対して、情報の自由市場こそが解決策だとするのは素朴な見方だ。ハラリによれば、印刷術の歴史が示す通り、情報の自由な流通は陰謀論も拡散させ、魔女狩りを引き起こした。真実を広めるには、事実に重きを置く「自己修正メカニズム」を備えたキュレーションの機関が必要となる。科学革命を支えたのは、不可謬性の幻想ではなく、自らの誤りを認め、訂正する制度、すなわち学会や学術雑誌といった仕組みだった。
とはいえ、自己修正メカニズムは時に秩序を脅かす。社会はつねに真実と秩序のバランスに悩まされてきた。ハラリは、独裁体制は自己修正を欠いた中央集権型ネットワーク、民主社会はそれを持つ分散型ネットワークと整理する。民主社会において真実の追求は、政府ではなく、学術、メディア、司法といった機関の持つ自己修正機能に頼るべきだという。
以上のように、「エコーチェンバー」「陰謀論」「キュレーション」といった現代用語を人類史のなかに投げ込み、大胆に遡及適用しているのが本書の醍醐味だ。大学で科学史やメディア技術史の基礎を講じている評者からみても、現代の問題意識を過去に照射することで、歴史をより身近で切実なものとして提示しようという意図も含めて、上巻の大筋は首肯できる。ただし、本書を「歴史書」と呼んでよいかは意見が分かれるところであろう。本書が試みているのは、過去と現在、そして未来との対話にほかならない。
そして下巻では、データの収集と処理を担う官僚、そして物語を生み出す神話作者の役割を、現代のAIがいかに代替しつつあるかが論じられている。AIは法の起草や違反の監視、議論への介入などにおいても高度な能力を発揮し、ネットワークが独自のロジックで機能することで、人間を排除してしまう恐れすらある。とくにAIが生成する物語や文化は人間の想像を超えるもので、こうした異質な知能とどう向き合うかが重要になる。
そこでハラリは、その政治的な潜在能力を人間の視点から理解し、責任ある規制をおこなう必要があると説く。AIは可謬でありながら社会に深く関与し、人間の価値観と乖離したときに壊滅的危機をもたらす。ソーシャルメディアのアルゴリズムが憤慨や憎悪を煽るように、AIは人間の感情を巧妙に操作し得る存在であり、自己修正機能の欠如は暴走を招きかねないという。民主主義の根幹は透明性にあるが、AIが意思決定に関与することでそのプロセスが不可視化され、政治的責任が曖昧になってしまう。人々が現実を把握できなくなれば、陰謀論やポピュリズムに傾倒する危険もさらに高まる。
ハラリは最後に、AIが国家間の力のバランスを変化させ、特定の国や企業がデータを独占することで、新しいかたちの帝国主義やデータ植民地主義が生まれる危険性に言及している。かつて「ウェブ(網)」と呼ばれたインターネットはいまや「コクーン(繭)」と化しており、AIは人類のつながりを分断する方向へと進みつつあるという見立てだ。たしかに日本でも昨年来、ソーシャルメディアが有権者の投票行動に強い影響を与えるようになった。真偽不明の情報が蔓延するなかで、極論が中道を切り崩し、社会の分断が加速しているように見える。その背景にあるグローバルな地殻変動を読み解き、これからのメディアやジャーナリズムのあり方を探るうえでも、本書は示唆に富んでいる。
このように下巻は、上巻で提示された歴史認識を土台としつつ、数々の思考実験と未来への警鐘を積み重ねた構成となっている。技術決定論を回避しようとする姿勢は一貫しているが、それでもハラリが描く未来像には、起業家たちが語るユートピアの裏写しのような陰影が差しており、その点には一定の批判も向けられよう。したがって、本書の問題提起に対する応答こそが、AI時代における人文学的思考を加速させる重要な契機となるに違いない。(柴田裕之訳)(いいだ・ゆたか=立命館大学産業社会学部教授・メディア論・メディア技術史)
★ユヴァル・ノア・ハラリ=イスラエルの歴史学者・哲学者。一九七六年生。
書籍
| 書籍名 | NEXUS情報の人類史上・下 |