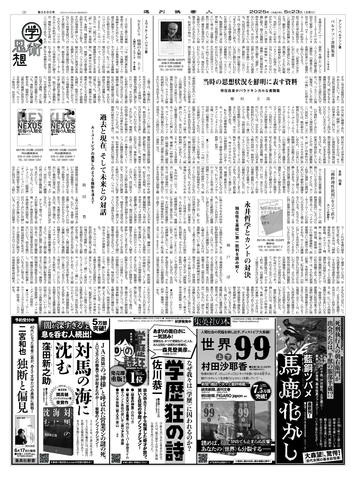『純粋理性批判』を立て直す
永井 均著
城戸 淳
カント哲学の意義や価値について伝えることは難しい。そこには、カント哲学に習熟した専門家のあいだで解釈の論議をするのとはまた異なった難しさがある。カントは独自の流儀で問題を立てて、それを独自の概念や論証によって解決するから、カント哲学に習熟するにはその概念のサーキットを走りこむ以外にはない。だが、走りこんで習熟すると、カント哲学の意義や価値について語るはずの言葉が、カントの模倣のようになり、伝える力を失ってしまうのである。今日まで読み継がれるカント書がしばしば、博識で篤実なカント研究者が書いたものではなく、むしろハイデガーの『カントと形而上学の問題』やストローソンの『意味の限界』など、独自の哲学的視角をもってカントに切りこんだものであるのも、そのような事情によるところがある。
永井均氏(以下、永井)の新著は、とくに近年では『哲学探究』の三部作において鍛えあげてきた永井哲学の洞察と概念装置を、カントの『純粋理性批判』にぶつけた成果であって、ハイデガーやストローソンの伝統につらなるカント書であるといえる。もちろんこれは逆から見れば、ときに同じ旋律の執拗な反復に陥りがちな永井哲学を、カントとの対決という新たな断面図へと展開して読むことにもなるだろう。
なぜかこの〈私〉からだけ世界が開けているという「独在性」の事実をカントは見落としており、その結果カントの「超越論哲学には、基礎に手抜き工事がある」から、その独在性の基礎から「『純粋理性批判』を立て直す」ことを試みよう──これが本書の基本的な方針である。この方針のもと永井は、『純粋理性批判』をひもとき、感性論、カテゴリー論、第一版と第二版の演繹論、図式論、原則論(とりわけ観念論論駁)、誤謬推理という順序で読みすすめる。カントの議論に対して永井が思いついたことをコメントするというかたちで論じられている箇所からも、多くの哲学的洞察を学ぶことができる。とはいえ、カントと永井の議論がいちばん嚙みあっているのは、演繹論について論じた第3~4章であろうと思われる。
永井はみずからの独在性の洞察を、デカルトの「私は思う(cogito)」に託す。カントは第二版の演繹論において、デカルトのコギトを「私は考える(Ich denke)」として継承しているが、それは諸表象を総合的に統一する作用を意味するものである。カントの超越論哲学の洞察によれば、世界の開闢の原点としての私の覚醒である「私は思う」は、その私の思想(記憶)を総合的に統一する「私は考える」の作用がなければ成り立たないのであり、さらにその総合作用は同時に客観的な世界構築でもある。しかしここでは逆向きの制約も成り立つのであって、そのようなカントの超越論的総合は、デカルト的な〈私〉の覚醒によって賦活されなければまるで無意味なものになってしまうのである。このような独在性と超越論哲学との相補性は、永井の前著である『独在性の矛は超越論的構成の盾を貫きうるか──哲学探究3』でも論じられたが、本書ではそれが『純粋理性批判』のテクストにそくして究明されている。
しかしながら、永井自身も認めるとおり、そもそもカントの超越論哲学は独在性の事実から出発するものではない。じっさい、さまざまな場面で永井はカント哲学における〈私〉についての問題意識の不在を言いつのるし、最終章ではむしろ誤謬推理の批判対象である合理的心理学のなかに独在性の残響を聞きとどけるまでになる。このような場面ではカントは、むしろ哲学的な対蹠者として、永井哲学の輪郭を際立たせる役割をになっているように思われる。
最後に蛇足のように指摘したいのは、本書の哲学書としての特徴である。本書(だけでなく近年の著書)での永井は、事柄をみつめてはじめて言葉を紡ぎたすというより、さまざまな自家薬籠中の概念装置や論証の手順を再構成して事柄について語っているように見える。読んでいて受ける感触は乾いた論理的な構築性であって、カントの著作でいえば『純粋理性批判』よりも『判断力批判』にちかい。読むことそのものが一つの哲学的な体験になるような文体であるように思われる。(きど・あつし=東北大学文学部教授・哲学)
★ながい・ひとし=日本大学文理学部特任教授・哲学・倫理学。一九五一年生。
書籍
| 書籍名 | 『純粋理性批判』を立て直す |