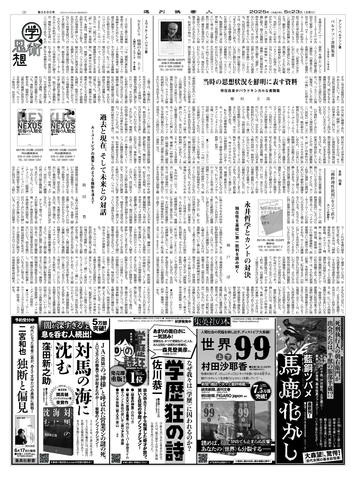ベルクソン書簡集Ⅲ
アンリ・ベルクソン著
檜垣 立哉
本書はすでに『Ⅰ 1865―1913』が合田正人監修・ボアグリオ治子訳で、『Ⅱ 1914―1924』が松井久訳で法政大学出版局から刊行されているベルクソンの書簡集の完結編にあたる。翻訳としても『Ⅰ』の刊行が二〇一二年であり、完訳に一三年の年月がかかっている。全体の通し頁数は一五〇〇頁を優に超え、個々の書簡は例外を除けばそう長くはないとはいえ、やはり大変な偉業であるといえる。今回刊行された『Ⅲ』では、四大著作のうち三つをすでに刊行し終え、ノーベル文学賞を獲得した名声の最中にありつつも、戦間期から第二次世界大戦へと世相が変化していく途上で『道徳と宗教の二源泉』という「社会的」著作を急ぎ刊行する晩年のベルクソンの実像がみてとれるものである。訳者の平賀は、『二源泉』を論じた『アンリ・ベルクソンの神秘主義』(論創社)の著者であり、本書の訳者として最適の人物といえよう。
さて、「訳者あとがき」において平賀自身が、この書を読むことの「居心地の悪さ」とともに詳細な経緯を記しているが、ベルクソン自身が、自ら公刊したものではない「原稿類」や、まさに「書簡」の類の閲覧や死後の公開を「遺言」で一切禁じており、その遺言自身が本書の(Ⅰからの通し頁数の)一五三〇─一五三一頁に記載されている点に触れないわけにはいかない。つまり、この書簡集は、ベルクソンの意志としては出版が認められないものであり、その存在自身がパラドックス的でもあるといえる。これは、現在のわれわれにとってのメールやLINEの文章の死後公開の是非の問題とも関連する(完全な秘匿はもはやありえない)。また一七世紀の思想家たちを想定すれば、逆にそもそも書簡が貴重な思想表現の媒体として公認のものであった。ベルクソンの強い態度は、こうした時代の「中間」に位置する「典型的な近代人」であるベルクソンの位置を考えさせることでもある。
この問題に決着をつけることは不可能だろう。現実に関係者がほぼ鬼籍にはいり、テクストが歴史的資料となったとき、それにどう対応するべきかは大変に複雑であり、それ自身「時間」と「生」の哲学者らしい問いがベルクソンによって投げかけられているかのようでもある。
ただ資料としてみたとき、フランス現代思想の二〇世紀の「華々しさ」については、戦中期から戦後におけるサルトルやメルロ=ポンティらと、ドゥルーズ・フーコー・デリダによる六八年以降の時代がおおきくクローズアップされる傾向があり、一九世紀のベル・エポックの雰囲気を強くひきうけたベルクソンの時代については、なかなか検討材料に乏しいという事情もある。この一連のテクストは、当時の思想状況を鮮明にさせてくれるという意味で、やはり貴重なのである。
私もこの書簡集を読み、ジェイムズとの交流やアインシュタインとの交錯、『ベルクソンとの対話』の著者であるシュヴァリエとのやりとりなどは想像がつくものの、記憶にかんする社会学者として近年注目を浴びるアルバックスや『暴力論』のソレル、あるいは人格主義者ととらえられるムーニエとの親しさや、ヴァレリーやジッドなど文学畑の著名人との交流など、この時代の人脈のありようが浮き彫りになることからは、そうした関係性自身が現代思想の底流を形成することも含め、さまざまな刺激をうけた。また、これも訳者の平賀が記していることだが、晩年の書簡集を一読して印象的なのは、リウマチや不眠に苦しめられ、一日のあいだ数時間しか活動できないと嘆き、さまざまな会合への出席を断念し謝罪をするベルクソンの老いの姿である。ベルクソンは何よりも生命と進化の哲学者であるが、生命を襲う反生命的な契機、病や死にベルクソンは向きあう際の肉声は、肺病ゆえに自らいのちをたった、ベルクソンの最良の後継者でもあるドゥルーズの晩年とつながる点もあり、考えさせられた。(平賀裕貴訳)(ひがき・たつや=専修大学文学部教授・哲学)
★アンリ・ベルクソン(一八五九―一九四一)=フランスの哲学者。生の哲学の論者の一人であり、真の実在を生命の連続した流れとしての「純粋持続」に求めた。1927年ノーベル文学賞受賞。著書に『時間と自由』『物質と記憶』『創造的進化』『道徳と宗教の二源泉』など。
書籍
| 書籍名 | ベルクソン書簡集Ⅲ |
| ISBN13 | 9784588009808 |
| ISBN10 | 458800980X |