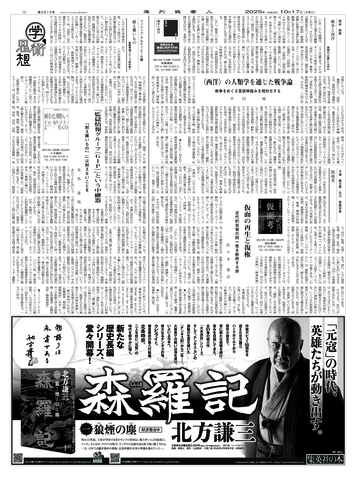戦争と西洋
西谷 修著
平田 周
〈いま〉という時間は、ただ刻々と過ぎ去る瞬間でしかなく、それだけでは確実性をもつことはできない。即時的・直接的体験に依拠する素朴な経験論に対するこのような批判から出発してヘーゲルが示すひとつの道筋は、沈殿していく過去を媒介として〈現在の厚み〉を捉えることである。光がプリズムを通してその波長ごとに分解された成分の配列を示すように、現在は、過去というプリズムを通すことでさまざまな側面を有した厚みを見せる。このことは、ウクライナ戦争やガザ攻撃に見られる現代の戦争においても当てはまる。
しかし、戦後八〇年が節目となるように、現代の戦争は、日本が経験した第二次世界大戦というプリズムを通して見られる傾向にある。もちろんそれは重要な視点であり続けるのだが、本書のプリズムは異なる。それはタイトルで戦争と並ぶ「西洋」である。著者である西谷修は、最初の著書『不死のワンダーランド』(一九九〇年)刊行以来、フランス現代思想の領域に、「共同体」「戦争」「世界史」「西洋の制度空間」といった、従来の研究では異質とされるテーマを導入することで、新たな思想史の領域を開拓してきた。その思想の集大成とする本書で力点を置くのは、先に挙げたこれまでの著書と同様に、日本というナショナルな単位というよりもむしろ世界というスケールである。日本が問われるとすれば、閉じた島国の特殊論としてではなく、世界的同時代性においてである。そしてこの世界史的同時代性に位置づけられた日本という視点こそが、類書にはない、西洋に対する独自の人類学的まなざしと呼びうるものを向けることを可能にしている。
著者にとって、〈西洋〉とは、括弧付きで強調されるように、特殊な名前である。煎じ詰めれば、それは単なる地理的区分を指すのではなく、西洋の「世界化」を実現した制度的編成体なのである。それは、一六四八年のウェストファリア体制によって確立された西洋の主権国家間の秩序をひとつの画期とする。戦争が国家間においてのみ認められるという規範を取り決め、戦争がそれまでのように宗教ではなく国益を重視する「国家理性」によって遂行されることになるからである。こうした世俗化の契機は、産業社会やそのエンジンとなる科学技術の進展と絡み合って、兵士と市民、前線と銃後の区別なく実施される総力戦と呼ばれる世界大戦の背景をかたちづくっていく。他方で西洋においてこのような主権国家間秩序が確立されていく時代は、それまで西洋の外部であった「新世界」アメリカ大陸が「無主の地」として発見され植民地にされていく時代と同時代である。西洋が地中海から大西洋へと活動の舞台を移していくまさにこの時代に先住民を虐殺・排除しその土地を占有することでアメリカ合州国が生まれる。それからおよそ一世紀をかけて、植民地化の脅威を背景とした西洋化の波は、日本を含むアジアやアフリカに及び、西欧列強の帝国主義的植民地獲得競争は、膨張したバブルのように世界に炸裂することになる。
本書で仔細に考察される二つの世界大戦、核抑止による米ソの冷戦と、ベトナム戦争を主とするその代理戦争、ポスト冷戦後の湾岸戦争、ユーゴスラビア内戦、二〇〇一年の九・一一以降、およそ二〇年にわたって続いた「テロとの戦争」、そしてウクライナとガザの戦争、これらはすべて〈西洋〉のプリズムを通して語られる。特にアメリカとイスラエルの建国の類似性や、ジェロニモから「テロリスト」へ至るいわば制度的怪物の系譜学として書かれた部分は本書の白眉であろう。メディア情報環境の変化によって日々スクリーン上を目まぐるしい速度で駆けめぐる膨大な情報に触れるようになった私たちは、忘却の速度も増し、断片化され、重要な認識を共有することが困難になっている。しかし、著者も強調するように、そのような変化をも踏まえて、どのような構造的要因で戦争が起きてきたのかを知り、否応なく浴びせかけられている戦争をめぐる言説のフレームワークを相対化する必要がある。少なくとも、「考える」ことの一歩は、著者の言葉を用いるならば、これまでの世界との関係から「離脱」していく主体の運動なのだから。(ひらた・しゅう=南山大学准教授・社会思想史)
★にしたに・おさむ=東京外国語大学名誉教授・フランス現代思想。著書に『戦争論』『夜の鼓動にふれる』など。一九五〇年生。
書籍
| 書籍名 | 戦争と西洋 |
| ISBN13 | 9784480018236 |
| ISBN10 | 4480018239 |