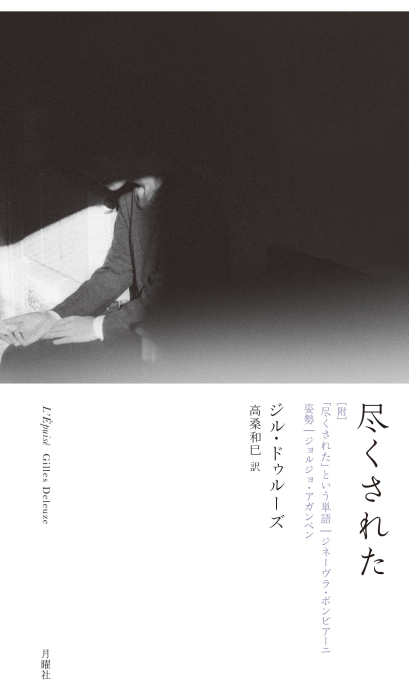- ジャンル:哲学・思想・宗教
- 著者/編者: ジル・ドゥルーズ、ジョルジョ・アガンベン、ジネーヴラ・ボンピアーニ
- 評者: 檜垣立哉
尽くされた 附:「尽くされた」という単語/姿勢
ジル・ドゥルーズ/ジネーヴラ・ボンピアーニ/ジョルジョ・アガンベン著
檜垣 立哉
本書は、サミュエル・ベケットの四つのテレビ作品の台本(「クワッド」「ゴースト・トリオ」「……ただ雲のみ……」「夜と夢」)の仏訳にドゥルーズが付したテクストを中心として、そのイタリア語版刊行に際し収録された、イタリア語訳者のジネーヴラ・ボンピアーニの前書きとジョルジョ・アガンベンの「姿勢」と題された後書きを高桑が訳出したものである。ドゥルーズのテクストは、すでに『消尽したもの』として、宇野邦一訳が白水社から一九九四年に出版されている。白水社版の方は、高橋康也訳によるベケットの台本の翻訳が付されている。今回再訳に至った詳しい経緯はわからないが、現代思想のなかですでに一定の地歩をえているアガンベンが、このドゥルーズの短いテクストにコメントを寄せていることがおおきいだろう(訳者の高桑はアガンベンの膨大な翻訳をなし、概説書も書いている)。
ドゥルーズのテクストは一九九二年に書かれたものであり最後期のものといえる。白水社版の宇野による後書きに詳しいが、この時期のドゥルーズはすでに重篤な肺病にかかっており、執筆も一日に数時間しかできなかったとのことである。その意味で最後の論考「内在──ひとつの生──」などとあわせて、最後期のドゥルーズの言葉を伝える貴重なテクストでもある。内容的にも『アンチ・オイディプス』で引用されたベケットの小説(『モロイ』『マロウンは死ぬ』)などにも言及され、ドゥルーズがベケットからうけた示唆を、「内在」にかんする最後期の思考においても維持し、思考しつづけていることがわかる。
「尽くされ」とは「疲労」ではない。「疲労」が「実現」される「可能性」を残すものであるのに対し、「尽くされ」はあらゆる「可能性」を欠いた世界、その意味であらゆる可能性のない「スピノザ主義」を描くものであるとされる(スピノザにおいてすべては必然性である)。それはすべての「組み合わせ」を「尽くした」上で現れる、ドゥルーズが「言語Ⅲ」と名指すイマージュでもある。こうしたイマージュは、言葉によって「暗くされ」た「視覚的」「音響的」のイマージュであり、「穴」や「裂け目」という「内在的限界」においてとらえられるという。ここで「尽くされた人」は寝そべるものでなく、ただ机に座るだけであり、起き上がることも寝ることもできない。こうしたイマージュの提示は、フランシス・ベーコン論である『感覚の論理』や『シネマ』の議論とも接近する。
アガンベンの後書きでは、こうした「尽くされ」は、レヴィナスが「疲労」や「不眠」として描く「現象学」を乗り超えたものとして位置づけられる。さらに、「座る」ことに対し、ハイデガーがもちいる「横たわる」(「現存在の本質はその実存のなかに横たわっている」)を対比させ、その意義を強調する。そして座るという言葉の語源を考察し、「存在を可能性のすまいから退去させる」姿勢であると規定する。ドゥルーズを現代哲学の布置のなかにおくアガンベンの読解は、総体としては魅力的ではある。レヴィナスの感覚の議論とドゥルーズとの意外な近さや、ハイデガーの「可能性」の議論との突きあわせも重要ではある。ただし、後期のドゥルーズに即するならば、このテクストは、八〇年代以前の議論とは少しく異なった方向性を、つまり「可能性」を「潜在性」とは別の方向で積極的にとりあげ、内在や感覚、身体と脳について論じだす時期のものであり、アガンベンの(とりわけ現象学やデリダを対比させる)哲学史上の配置はいささか強引にみえなくもない。とはいえアガンベンは自らの「現勢力」という言葉をもちい、「現勢力に穴を穿ち、現勢力を超えたその先」に継続させる方向をここにみていく。それはまさにアガンベン流に、中世哲学的な概念と連関するイマージュの系譜の提示であり、潜勢力/現勢力、可能/現実を中和するものとのべられる。これは、最後期のドゥルーズを読み解くひとつの方向たりうるだろう。(高桑和巳訳)(ひがき・たつや=専修大学教授・哲学)
★ジル・ドゥルーズ(一九二五―一九九五)=フランスの哲学者。著書に『差異と反復』『アンチ・オイディプス』(F・ガタリとの共著)など。
★ジネーヴラ・ボンピアーニ=イタリアの編集者・作家・翻訳者。一九三九年生。
★ジョルジョ・アガンベン=イタリアの哲学者。一九四二年生。
書籍
| 書籍名 | 尽くされた |
| ISBN13 | 9784865032093 |