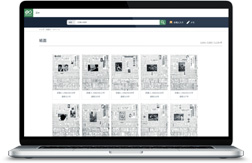お知らせ
【WEB限定・完全版】読書人7/18号 ファブリス・アラーニョ インタビュー【本紙続き】
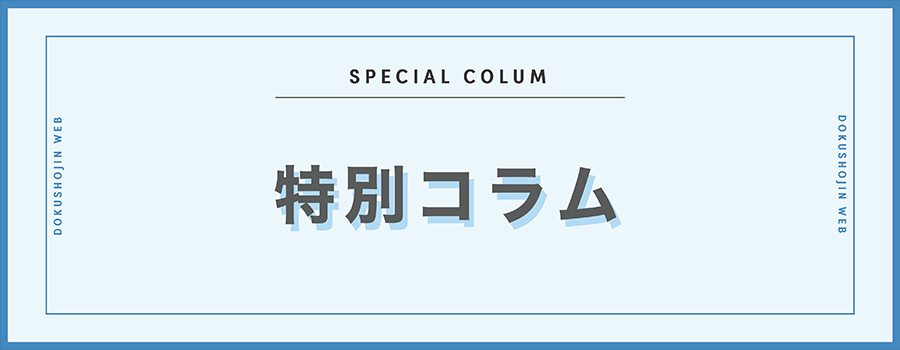
-2-1024x684.jpg)
二〇二二年に亡くなった映画監督、ジャン=リュック・ゴダールの世界を体験する展覧会《感情、表徴、情念 ゴダールの『イメージの本』について》が、七月四日より、東京・新宿歌舞伎町の「王城ビル」(新宿区歌舞伎町1-13-2)で開催されている(八月三一日まで)。本展覧会キュレーターであり、晩年のゴダールの右腕であった、スイスの映画作家ファブリス・アラーニョ氏にお話をうかがった。新宿におけるインスタレーションの設営から、新作『湖』(二〇二五年ロカルノ映画祭のコンペ選出)の関係者上映のためにパリへ直行してきたファブリス・アラーニョに付き従い、インタビューする機会を得たものである。この対話は、パリでの上映後ローザンヌへと向かう帰路の最中に自然と始まり、大部分はリヨン駅のレストラン「ル・トラン・ブルー」で繰り広げられた。(翻訳・インタビュー構成=久保宏樹)(編集部)
リヨン駅
HK〔久保〕:この「ル・トラン・ブルー」にはよく来られるのですか?
FA〔アラーニョ〕:私が初めて訪れたのは、一九九八年に遡ります。映画学校の卒業制作の作品に出演してくれる女優を探していた時のことです。その女優はパリに住んでいました。なので、まさしくこの場所で会う約束を取り付けたのです。その女優は、イリーナ・ブルックといって、舞台演出家のピーター・ブルックの娘です。私は、彼女の演じる姿をローザンヌの劇場で見る機会があったので、一度会ってみたかったのです。そんなこともあって、この場所に来ました。スイスから列車でついて、そのまま誰かにあって、そして……。
HK:そうですね。この場所は、スイスとの窓口として理想的な場所です。
FA:そして、落ち着いていて感じのいい場所でもある。長居することも気になりません。
HK:このリヨン駅を出てすぐのところには、ホテルがあります。そこがゴダール御用達のホテルだと、たびたび耳にします。
FA:はい。駅を出てすぐのところにある「メルキュール」です。ジャン=リュックのおかげで有名になっています。ゴダールは、そのホテルによく滞在していました。時おり、私たちアシスタントもそのホテルに泊まらせていました。面倒ごとから解放されるために、そのホテルを選んでいました。スイスからリヨン駅に到着して、そのままホテルに向かい、すぐに寝るということが可能だったからです。
HK:このリヨン駅という場所は、スイス関係の人にとっては馴染みが深いところですね。
FA:はい。それから二〇〇一年にも、この場所でキャスティングを行いました。それは私自身の作品のための、役者の試し撮りを兼ねていました。
HK:その当時はまだゴダールと一緒に仕事はしていなかったのですか?
FA:私がジャン=リュックと一緒に仕事を始めたのは二〇〇二年からです。『愛の讃歌』からです。
HK:『愛の讃歌』は、アンヌ=マリー・ミエヴィルと一緒に仕事をしていた時期とその後の過渡期に当たる作品ですよね。その作品をきっかけとして、ミエヴィルとの仕事上の関係が失われていく。
FA:はい。ジャン=リュック自身は、アンヌ=マリーと共作関係が終わったとは言っていませんでしたが、一般的にはそのように言われます。彼女の名前は『アワーミュージック』のスタッフロールにも残っています。といっても、それは給料という形で彼女にお金を渡すためでした。なので実際のところ『愛の讃歌』は、『イメージの本』に至るまで続く、五本の連作の一編でした。
『愛の讃歌』、『アワーミュージック』、『ゴダール・ソシアリスム』、『さらば、愛の言葉よ』の四本の作品があり、それらが『イメージの本』へと結実していったのです。そして、パリの劇場メナジェリー・ド・ヴェールで行われたインスタレーションへと繋がっていったのです。
メナジェリー・ド・ヴェールで行われたインスタレーションのタイトルは、「イメージの讃歌」でした。『愛の讃歌』から『イメージの本』までを取り扱ったものです。
HK:その展示を思い返すと、『イメージの本』の抜粋映像が流れていて、さらには別の部屋では『愛の讃歌』以降の映像の抜粋が流れていました。しかし、九〇年代以前の映像はほとんどなかったように覚えています。
FA:その場でも九〇年代以前の映像は流れていました。『新ドイツ零年』、『映画史』、『リア王』……。『ヌーヴェール・ヴァーグ』からの引用もあったと思います。
ゴダールとの最後の日々

HK:晩年になっても、過去の自分の映像から本当にいいショットを何度も使い回していたようにも思います。『シナリオ』においても、『はなればなれに』の男二人が拳銃で殺し合うシーンがあったように記憶していますが、それはアラーニョさんのアイデアだったのでしょうか?
FA:引用された映像は、全てジャン=リュックの指示に基づいています。しかし、その映像を、彼自身が目にすることはできませんでした。第一部にあたるDNAを見ることはできていました。第二部の「MRI」に関しては、第一部を見せた翌日に亡くなってしまったので見ることができていません。「DNA」の部分は、一緒に制作を進めることができました。亡くなる前の週の金曜日に、彼のベッドの上に一緒に腰掛けながら、引用すべきものを探して……何をするべきかすべて指示を受けました。「DNA」の映像に関しては、私のパソコンを用いながら一緒になって……。その時にはなぜ私に会いたがっていたのかもわかっていませんでした……。
その瞬間に至るまでに関しても説明が必要ですね。とても長い話なので、簡潔に説明します。ジャン=リュックが、死を決意したのは、死の十日程前のことです。死から二週間前、私とジャン=ポール・バッタジア〔ゴダールのもう一人のアシスタント〕は彼のアトリエにいました。彼が亡くなったのは火曜日なので、ちょうど一三日前に当たる水曜日のことです。
その水曜日からさらに遡ること一週間前の水曜日には、ジャン=リュックを病院を連れていきました。ジャン=リュックは、何も食べることができなくなっていたので、食欲を少しだけでも取り戻せるようにと五日ほど入院する予定だったのです。私は彼を何度か病院へ連れて行くことがありましたが、数日の滞在が予定されていても、いつも通りなら翌日には、「すでに家に帰ったから、病院へ荷物を探しに行って欲しい。帰るための書類にもサインも済んでいるから、ただ病室に残した荷物を探してきてくれ」といったようなメッセージが送られてきたのです。しかし、その時は違いました。最後まで病室にいたのです。私が彼を探しに行った時には、陰気な表情をしていました。気難しくなっているわけでもなく、単に冴えない表情だったのです。頭はしっかりしており、いろいろなことに考えをめぐらせているようでした。決して悲しんでいるわけでもありませんでした。そんな様子を見ながら、私は彼をアンヌ=マリーの家に連れて帰りました。その時には、彼は、二本の杖を用いながら自分で歩いていました。アンヌ=マリーの家についた際には、私とアンヌ=マリーで支えなければいけませんでした。もう長くはないだろうなとは思いましたが、すぐに死ぬような状態ではなかったのです。肉体的には、まだ大丈夫だったのです。膝に問題を抱えていたことを除けば、九一歳の肉体としては充実した状態だったからです。
ジャン=リュックを家に連れ帰ったのは、月曜日のことでした。そして翌日の火曜日には、私たちは彼の家で再会しました。その日は、本当に暑い日でした。彼は「喉が渇いた」と仕切りに訴えていました。その暑さが原因だったのかはわかりませんが、体調がすぐれない様子でした。それでも、仕事を進めることにしたのです。そして、同様にして水曜日にも会いました。いずれにせよ、「DNA」「MRI」とジャン=リュックの頭の中にあったアイデアを作品として仕上げなければならず、その脚本に手を加えていく必要があったのです。その脚本は、まさに『シナリオ』に他なりませんが、ジャン=リュックにはもはやそれを完成させる気力が残っていなかったので、「『シナリオ』を予告するためのもの」になるはずでした。
HK:その時点におけるタイトルは何だったのでしょうか?
FA:その時点では、まだ決まっていませんでした。しかし、『ベレニス』〔ラシーヌの戯曲〕やアッサ・トラオレ〔フランスのアフリカ系人権活動家〕などを映画に組み入れることは断念していました。そして、「DNA」と「MRI」の二つの部分へと分かれていったのです。「DNA」は生物としての基本的な部分です。そして、「MRI」はジャン=リュックの身体の不自由を表しています。彼は自宅の階段が登れなくなったりなど、身体的弱点を抱えることになっていました。
いずれにせよ、Arte〔アルテ放送局〕に、映像を渡さなければいけませんでした。Arteとの契約があったので、もし映像がないのであれば、契約不履行となり返金をしなければいけなかったからです。なので撮影をしなければいけませんでした。
その水曜日には、翌日木曜日にジャン=リュックの身体的不自由さを簡単に撮影することを話し合ってもいたのです。そして、その水曜日には、基礎的な編集を自分で行えるようにと、ビデオモンタージュの装置のケーブルを最低限でいいので再び繋ぎ直すことを、ジャン=リュックは私に指示しました。なので私は、正しく繋ぎ直すために、すべてのケーブルを抜くことから始めました。しかし作業を始めるや否や、ジャン=リュックが疲労の色を隠せなくなり、「本当に疲れた。腸に問題が起きてる」と言い始め、私とジャン=ポールにアンヌ=マリーの家に連れ帰ることを訴えたのです。なので私たちは、彼をアンヌ=マリーの家へと連れ帰りました。そして、それぞれの家に帰ったのです。正確には、ジャン=ポールはホテルへと向かい、私は自宅へと帰りました。
翌日には撮影をするために落ち合うことになっていました。そして、銀行にも一緒に行く予定になっていました。しかし、ジャン=リュックから「本当にひどい一夜を過ごした。全ての約束をキャンセルしてほしい。また後日、体調の良くなった際に会おう」とメッセージが送られてきました。私たちは、すでに似たような状況を経験していたので、大したことだとは思いませんでした。なので、これから先に起きるかもしれないことをの心の準備をしなければいけないけれど、まだ大丈夫だと鷹をくくっていたのです。永遠の別れが訪れるのは、半年後、一年後、二年後のことであり、まだしばらくは大丈夫だと安心していました。そのまま数日経ちました。日曜日が過ぎるまで、私たちの間には特筆することは起きていなかったのです。
しかし月曜日になって、ジャン=リュックの近所に住んでいる税金問題を管理している人物から、「昨日ジャン=リュックに会った。Exitへの登録を頼まれた」と連絡を受けたのです。Exitは、自殺幇助のための団体です。その知らせを知った時、「彼は今すぐ死にたいのか」と困惑してしまいました。そうした決断を私たちに知らせるのが本人ではなくて、税理士だったのです。その翌日に私は、ジャン=リュックから「銀行問題のためにアンヌ=マリーの家に来てくれるかい。前の週までには銀行問題を片付けなければいけないんだ」というメッセージを受け取りました。なので、私はアンヌ=マリーの家に向かったのです。しかし、私は動転していました。その知らせを受けた時から、少しも落ち着くことができなかったのです。私たちの側からメッセージを送ることもできませんでした。知らせを伝えてきたのが、彼自身でないことに私たちは不気味さを感じていたのです。まるで、扉が閉ざされてしまったかのような印象を受けていたのです。そんな状況でしたが、ジャン=リュックから「会いに来てくれ」という要望を受けたので、会いに行きました。そこにいたジャン=リュックは、気は立っていましたが、いつも通りのジャン=リュックでした。彼が苛立ちを覚えていたのは、その団体に対してでした。自殺幇助に至るまで、長い期間が必要だったからです。私はジャン=リュックに対して、「半年ほど必要なのは、そんなに大したことではない。殺してくれと頼んだから、すぐに殺してくれるようなものではない。あなたは失病を抱えているわけではない。ガンでもないし、死にかけているわけでもない。頭はしっかりしているじゃないか。時間がかかるのは、当然のことだ」と言いました。彼は、気を紛らさせるためのアイデアを必要としていました。そんなこともあって、私はキオスクへと新聞を買いに行きました。いつも通りの日常が少しだけ戻ったのです。
そのまま木曜日までは何も起きませんでした。しかし、その木曜日にまた税理士からの連絡を受けました。「うまく行った。色々と手を尽くした。日が決まった。来週の火曜日だ。もし最後の言葉を交わしたければ——税理士はもしとさえ言ったのです——、強制するわけではないが、月曜日に会いに来ても良い。しかし義務ではない」。そのことに関しては、私はもう何度も色んなところで語っているので、すでに他のインタビューを通じて知っているかもしれません。しかし、私たちは、まるで水の外に投げ出された魚のようになってしまったのです。その水の外の魚というイメージは、真に私が感じていた状態です。少しも身動きが取れなくなっていました。さらには、そのことを伝えてきたのが、ジャン=リュックではなくて、ちょっとだけ見知ったあまり好きになれない男だったのです。税理の人間には、冷淡な一面があります。そして翌朝、その冷淡な男からまた連絡がありました。「よく聞いてほしい。ジャン=リュックが、五、六枚の写真のためにあなたに会いたがっている。何時頃に来れるか教えてほしい。こちらから彼には伝えておく」。私は、適当に午後の一五時くらいなら大丈夫だと返事をしました。そしてそのまま彼に会いに行きました。私は、どうして彼が五、六枚の写真、イメージを必要としているのかわかりませんでした。なので、私は撮影機材を手に取り、さらには、もしかして映像やイメージなどを探さなければいけないのか、もしくは映像の編集をしなければいけないのかもしれないとも思い、パソコンも持っていくことにしたのです。要するに、一通りの道具を持っていくことになったのです。
そして、アンヌ=マリーの家で、ジャン=リュックに会いました。彼は、微笑みを絶やさず穏やかに、小さなベッドに腰掛けていました。そして「ファブリス、こっちに来てくれ」と言ったのです。なので私は、彼の目の前に行きました。彼は行儀良く座ったままノートブックを広げて、説明を始めました。「冒頭では、このようなイメージが必要だ。それが『シナリオ』だ。それがシナリオの映像だ。それから写真を変える。私のiPhoneにある写真を使ってほしい。カメラロールの一番終わりにある写真だ」。そんな風にして彼は私に写真を見せました。私は一つ一つ理解していきました。そして、それらの痕跡を留めておくために、その時持って行った小さなカメラとマイクで、彼の指示を記録しました。それから、彼は「DNA」に関しての脚本、つまり「DNA」のモンタージュを私に見せて説明しました。「DNA」では、いくつもの写真が用いられます。その写真は、ジャン=リュックのスマートフォンに残されていました。そうしたことに関して、彼は私に話をしたかったのです。ジャン=リュックは、デッサンを行っていました。なので、何を必要としているのかは、とてもはっきりとしていました。ライフルを担いだアメリカ兵の写真は、『アワーミュージック』の冒頭のものです。彼は、そのイメージをデッサンしていたので、どのイメージであるかは本当にはっきりとわかりました。それから、二つの動きのあるシークエンスが続きます。つまり、二つの映像です。それを探さなければいけませんでした。一つは『新ドイツ零年』のものでした。その作品は——私はジャン=リュックとの仕事のために時折必要となるので——Vimeoにアップロードしてありました。なので、私のパソコンを通じてVimeoにログインして、映像へとすぐに辿り着くことができました。そのまま必要なシークエンスを選び取ることができたのです。ジャン=リュックは私の目の前で、必要なシークエンスを自分で選び取りました。なので、本当に彼の望んだ通りの映像になっています。それから、パゾリーニの『アポロンの地獄』のシークエンスを、DVDを用いて長い間探すことになりました。ジャン=リュックは、鋭い目の開口部を備えた兜を被った人物をデッサンしていました。私たちは、その映像を探して、映像を漁ることになったのです。三〇分以上の時を費やしたかもしれません。DVDというメディアを通じて、映像を早送りしたり巻き戻したりして、必要とする映像を探すのは本当にうんざりするような作業です。それに加えて私たちは、ポータブルDVDプレイヤーで作業をしなければいけませんでした……。インターネットを通じて探しもしましたが、本当に時間を要する作業でした。ジャン=リュックは私の横に腰掛けていました。しかし、ある時から、疲れのためか、私にもたれかかる状態になっていました。本当に奇妙な感じがしました。私に全体重を預け、もたれかかっていました。私は、彼の体温を生々と感じることになっていました。そうした不思議なことが起こっていたのです。私たちは二人きりでした。彼は私にもたれかかり、私は何かを探している。それは、ある意味では愛情のようなものだったのかもしれません。ジャン=リュックは、私の座っている側とは別の側に横たわることはせずに、まさに私の二の腕に寄りかかっていました。私たちは探し続けました。そして遂に、まさしく必要としていた、デッサン通りの本当に短い映像を見つけ出すことができたのです。それからジャン=リュックは「その映像をスローにしなければいけない」と言いました。それぞれの映像が二〇秒きっかりになるように、スローにする必要があったのです。合計で一三の二〇秒の映像が用いられることになりました。
それとは別に面白い出来事もありました。作業の終わりに、ジャン=リュックは、ジャン=ポール・サルトルの『シチュエーションIV』〔サルトルのエッセイ集の四巻〕を探しにいくように私に命じたのです。その本は、アトリエの左の机の下にあるということでした。私はアトリエに行って、本を探したのですが、見つけることができません。私が長々探していたので、「本は見つかったかい」とジャン=リュックからの電話がありました。しかし、見つけることができません。そんなに大したことではないと言うので、そのままジャン=リュックのところに戻り、ジャン=ポールに電話をかけました。ジャン=ポールは、例の一件以来、水の外で泳げない魚状態でした。本当に何もすることができなかったのです……。それが映画作りの指示を与えるや否や、水を得た魚の如く動き始めたのです。「ジャン=ポール?今、ジャン=リュックと一緒にいるんだけど」「何?本当かい?」「『シチュエーションIV』という本を探しているんだ」。彼はジャン=リュックは死ぬのだとばかり言って塞ぎ込んでいたので、飛び上がって驚いた様子でした。ジャン=リュックのために本を探したりDVDを探しに行くといった、毎日のありきたりな問題が降りかかってきたのです。突如として、日常が帰ってきたのです。そして、新たな仕事をこなさなければいけなくなりました。要するに、生気を再び取り戻す必要があったのです。彼は死んでいたわけではありませんが、ある時点から動きが止まってしまっていたのです。そして、彼は本を探すために、パリの本屋や古本屋に電話をすることになりました。私の側では——ジャン=リュックとの面談が終わった後に——もしかするとローザンヌの古本屋で探している本を見つけられるかもしれないとかもしれないと考えました。ジャン=ポールはパリでの調査を続け、私はローザンスで探す。「私は月曜日に、別れの挨拶を告げるためにジャン=リュックに再び会える。それだからあまり気にかけることはない」。そんな風に考え、私はローザンヌへと急ぎました。古本屋の閉店時間へと間に合わせるために、車でロールから大急ぎで向かったのです。ローザンヌの街の外側では渋滞が起きていました。私は、車を駐車して、古本屋に向けて走ったのです。古本屋には、一八時二分に到着しました。閉店時間を過ぎていました。
しかし、その時には必要に迫られていたのです。もしサルトルの『シチュエーションIV』を見つけることができたら、再び生きることができる。映画が生き延びることができる。最後まで映画を作ることができる。ジャン=リュックが、死を忘れるかもしれない。もしその本がなければ、その結果は……。結果として、私たちは本を見つけることができませんでした。翌日になって、もしくは同日の夜になって、ジャン=ポールから連絡がありました。「本を見つけた。明日パリに探しにいく。スキャンを送る」。土曜日にそのスキャンは送られてきました。それを口実にして、私はジャン=リュックに連絡をしました。「月曜までに終わらせなければいけない『シナリオ』の編集に関してまだわからないことがある」といったようなことを言ったと思います。会話はあっという間でした。その日の夜に会う約束を取り付けました。そして、ジャン=ポールから送られてきたテキストを印刷しました。そのテキストを片手に、ジャン=リュックを訪れ、色々と撮影したのです。そうすれば、土曜の夜には「DNA」の編集を終えることができるからです。私は、月曜には「DNA」をジャン=リュックに見せたかった。『シナリオ』に必要なこと全てを記録することができたので、私はジャン=リュックへノートを返しました。私の頭の中には色々と考えがありました。そうすれば、彼は色々と付け加えることができる。仕事を続けることができる。まだ変更を加えることができる。創造を続けられる。きっと死のことも忘れてくれる。そして私は、その日の夜に編集を終えました。しかしいずれにせよ……「DNA」の映像からは死が感じられます。映画作家が、一つ一つの映像を通じて死を語っている。その死の瞬間が訪れることを理解させられるのです。非常に個人的なことです。死の前の喪に立ち会わなければいけないのです。死をあらゆるところで見ることになります。そして、それを各所で見せているのがジャン=リュックに他ならない。トカゲの形をした舌の映像でさえ、死を感じさせます。黄色と不快な緑による、酸敗したような不気味な映像です。死の味を感じさせます。死というのは、鼻を刺すようなものに違いありません。フーガ(=遁走)のシーンもあります。ある人が、別れを告げている。若い女性に向かって別れを告げている。姿をくらますロシア人の姿も見える。そして別の人は、それをバッハの最後の未完成のフーガだと言う。そうしたことが、各所に見出されるのです。パゾリーニの映像に関しても同様です。兜の目の穴を通じて、死が近づいていることが感じられるのです。
私は、そうした映像をその日の夜に編集しました。日曜日には、編集とは別のことを行いました。そして月曜日に、その映像をジャン=リュックに見せに行きました。その日のジャン=リュックは、とても穏やかで微笑みを絶やしませんでした。ジャン=ポールもその場にいました。ジャン=リュックは、脚本に再び手を加えていました。赤字で指示を書き込んでいたのです。私は「信用している。今後、第二部の編集をする」と告げました。その場でジャン=リュックから第二部の説明がありました。最後の映像は、その場で撮影しました。最後の映像を撮影して、抱き合い、泣いて、私たちは永遠の別れを告げました。
HK:それから先に会うことはなかったのですか?『シナリオ』の最後となる映像の撮影の瞬間が、最後の瞬間になったのですか?
FA:その映像を撮影した後、少しだけ話す時間がありました。私は、再びカメラを廻しました。しかし、撮影した映像を再び見返すことはしていません。私たちは、「本当に確かな決断なのか。その予約を撤回したくないか」を確認しました。彼からの返事は、「したくない。今か、六ヶ月後かだ」でした。しかし、彼の思考は、普段通りのものでした。死について話したのです。
HK:今語られたことは、本当に生々しくて少し涙が誘われてしまいました。
FA:翌日の十時ごろには、本当に多くの電話がかかってきました。情報が漏れていたのです。メディアがひっきりなしに電話をしてきて、私たちは悲しみに浸る暇もありませんでした。しかし、それはそれで私たちにとって良いことでした。
これが『シナリオ』にまつわる話の全てです。
『ロール ワークショップ 旅』
HK:死後もゴダールの家を管理していましたよね?
FA:私たちで、家を保存していました。死の六ヶ月後には、家の撮影もしました。
HK:三〇分ほどの短編映画のことでしょうか?家の内部を詳細に撮影していましたよね。
FA:その作品は、今朝、マルセイユのFID〔国際ドキュメンタリー映画祭〕で、ワールドプレミアとなる上映がありました。今私がこの場にいることからわかるように、その作品はたった一人で映画祭に行っています。
HK:『ロール ワークショップ 旅』が心を打つのは、様々な資料が一つ一つ詳細に見せられるからです。
FA:その作品が人を魅力するとしたら、それは一つの本から別の本へとの関係を見せること、つまりジャン=リュックの考えの軌跡をみることができるからです。一つ一つの本は、何の考えなしに並べられているわけではありませんでした。考えに基づき整理されていたのです。つまり、ジャン=リュックの頭の中を想像することになるのです。馬鹿の一つ覚えみたいにいつも同じ例を出してしまうのですが、記憶に焼き付いていることがあります。ジャン=リュックは、『愛の讃歌』を『負債論:貨幣と暴力の五〇〇〇年』〔デヴィッド・グレーバー〕の上に置いていました。面白い考えです。負債と愛。その間には何かがある。
HK:愛と負債に関して、赤子と母親の関係に関しても、ゴダールは似たようなことを行なっています。七〇年代のテレビ作品〔『6x2』〕だったと思いますが、その中で赤子と母親の写真が出てきます。写真の上に、愛と空腹と書き込んで円上で繋げていました。
FA:それも愛です。しかしそうした細部を見せること以上に私たちに大事だったのは、ジャン=リュックの考えを見せることだったのです。物質崇拝のようにしてジェン=リュックを見せることとは異なります。例えば、灰皿の上に置かれたまま残された葉巻があります。そこに葉巻があること自体は驚きではありません・しかし、その葉巻のブランドは「ロメオ・イ・フリエタ」〔ロミオとジュリエット〕です。そうしたことが、私の心の琴線に触れました。そして、その映像の上には『愛の讃歌』の音を被せました。なぜなら、その後続く五本の作品の第一作目だったからです。『愛の讃歌』には、他の作品以上に親密なものがあるように思います。それだけで別の世界が成り立っているようです。死と天国を感じさせる。そうでありながらも、隠しきれない感情の親密さがあるように思います。さらに、私に対してはそれ以上に語りかけてくるものがある。そんなこともあって、『愛の讃歌』に対するちょっとした思い入れがあります。
最後の映像は、ジャン=リュックが壁に貼り付けたイメージで構成されたトーテムです。最後に映し出されるイメージは、最初の「シナリオ」〔『シナリオ』最初期の企画の脚本〕の裏表紙でもありました。そのイメージは本当に見事なものでした。杖を二本ついた、顎髭を生やした男がいる。その周りに、指を使って描かれた、黄色、赤、青の色斑がある。それはあたかも、一人の老人が色彩の森の中を散歩しているかのようです。その森は色彩の天国と言えるのかもしれません。そして、ジャン=リュックは、そのイメージをトーテムの最も低い位置に配置しました。その上には、苦しみを表すイメージが数枚ありました。そして中央には、ロクシー〔ゴダールの愛犬〕の写真がありました。そして、最も高いところには映画を表すイメージがあったのです。
私たちは、そのトーテムの全景をまず収めた映像を入れました。その後、作品の最後には、トーテムを下へと降っていき、「シナリオ」の裏表紙のイメージへと至るようにしたのです。トーテムを徐々に下ることで、死のイメージ、窓のイメージを通過して、裏表紙のイメージへと至ります。そのイメージは、「シナリオ」の原本の裏表紙を使って詳細に撮影しました。そして、作品の最後の映像としたのです。その映像に対して、どの音を使用するべきかは悩みました。しかし、ある時に、何を使うべきか閃きました。そして、合わせてみたところ、うまく行ったのです。私が用いたのは、『アワーミュージック』の「天国」の音です。
ゴダール財団
HK:ちょうど今から一ヶ月ほど前に、家賃を支払うことをやめて、家の保存を終えています。その際に、家の中にあったものは、美術館などに売り払ったのでしょうか?
FA:そうしたことも考えましたが、結局はやめました。私たちの考えにあったのは、ジャン=リュックの住まいを別の場所で再現するということです。そうでなければ毎月二〇〇〇スイスフランの家賃を支払続けなければいけないません。私たちが最初に考えたのは、アーティスト・レジダンスのようなものでした。しかし、そのようにして使うためには、家が小さすぎました。博物館にするという考えもありましたが、ジャン=リュックの仕事場を見せるというのは、本当に難しい行いです。とても狭い空間なので、一人か二人入るのが限度です。なので、人々に見せることはできません。私たちが撮影したようにして、一本の作品を制作することはできました。しかし、それ以上のことはできませんでした。そして、私もいつまでも二〇〇〇スイスフランの家賃を払い続けることはできません。なので、家を引き払うことを決意したのです。そして、美術館に提案をしました。
以前、プラダ財団〔ミラノの現代美術館〕でインスタレーションを行ったことがあります。「オルフェのスタジオ」と題されたそのインスタレーションは、ジャン=リュックのサロンを模したものでした。テレビやスピーカーを並べて、『イメージの本』を上映したのです。ジャン=リュックは、コクトーの『オルフェの遺言』に着想を得たアイデアを持っていました。そのアイデアは、映画の放映環境に関するものです。つまり、作品を彼の家の当時のサロンで上映する。作品が編集されるのと同時に、作品が上映される。ジャン=リュックは、オルフェとエウリュディケーを結びつけることを考えていた。つまり、制作、製造、要するに編集室と上映を一体化させる。そうした考えを、彼はプラダに提案したのです。しかし、その当時は、その考えに基づいて何かがなされることはありませんでした。
今日私たちが探しているのは、そうした考えに興味を持ってくれる財団や機構です。現状では、どのようになるかわかりません。家は空っぽにしました。家の中にあったものの目録は詳細に作成しました。全てを詳細に撮影もしています。配置も完全に記録してあります。家の中全体も、iPhone15proを用いて3Dで撮影しました。その3Dのイメージは、写真と映像のあいだのようなところがあります。寝室から、階段、仕事部屋、編集室至るまで、その中を自分の好きなように見て回ることができます。その3Dのイメージは、撮影を何度も行ないました。まるで、部屋というパズルを解くかのような体験となりました。
それとは別に、私個人の企画があります。企画以前の状態なので、現状では、単なるアイデアといったほうがいいかもしれません。その考えとは、「ジャン=リュック・ゴダール財団」を作ることです。その創立が、しばらくの間は私たちの最も大きな仕事となる予定です。彼の仕事の全てを管理するためには、ある種の機構が必要になります。彼の映画の全て、作品の全てを管理する必要があります。彼が行ったこと全ての目録を作成する必要もあります。彼が書き残したもの、発言したもの。仕事の周辺にあったもの。まずは複製だけだとしても、そうしたものを集めていかなければいけません。さらには、彼の作品を修復するため、保存するための予算も必要になります。それから三つ目の役割として、彼の作品を見せる、伝えていくということも必要です。それは、あくまでも創造という形を通じて、つまりインスタレーションの展示によって行っていきます。出版という形をとることもあるかもしれません。私が映像インスタレーションを通じて行っているのは、映画のフォルム〔形式〕を探しながら、各々の作品を解体するということです。
パリのメナジェリー・ド・ヴェールで行われた展示も、フォルムの探究の一面がありました。ジャン=リュックの作品をより感じ取るために。彼の作品が生き続けるために。彼の作品が、ショーケースやスクリーンの中に固定されてしまい凝固したものになってしまわないために。これから先も、ジャン=リュックが行っていたようにして、私たちが仕事を続けられるように。または他の人々同様の方法で仕事を続けられるように。または全くことなる方法に基づく仕事の可能性を費やさないために。フォルムに考えを与えて、時には挑発するような試みが必要なのです。
私が望んでいるのは、反アカデミズムに基づく機構です。ジャン=リュック・ゴダール財団は、デジタル映画のフォルムの研究、またはVR映像やAIの欠点についての研究をするように仕向けることができるかもしれません。
HK:CNRSのようにですか?ゴダールは時折CNRS〔フランス国立科学研究センター〕と自身の仕事に関して言及していました。
FA:そうです。しかし、反アカデミズムという考えに基づいてです。つまり、規則や大層なことを探求するのではなく、現場を直接訪れ探さなければいけません。デジタル映像は、指示を必要としています。どんな指示をしたら何が起きるかを、洗いざらい確認していく必要があるのです。
新作『湖』と見えないもの
HK:そうした考えは、企画書やシナリオを何よりも先に求めるCNC〔フランス国立映画センター〕の考えと相反していますね。
FA:全くその通りです。ジャン=リュックも同じ考えを支持していた。私が、自分自身の作品で行ったのは、——色々と説明長になりたくないので決してその考えを直接的に表明してはいませんが——実験することでした。私の映画には、脚本となるものがほとんどありませんでした。曖昧なアイデアだけを持って撮影に行くことがしばしばありました。そんな風に撮影に向かうと、自然光、流れていく雲、風、立ち現れる光の反射、湖畔の歩行者の姿を受け入れざるを得なくなります。そして、それらを撮影することになる。前もって予測されたことではありません。兆しに敏感に反応しなければいけなくなる。感情を伴った兆しは、あらゆるところに見出すことができます。それゆえに私の映画の冒頭には、メルロ=ポンティの引用があります。とても単純なことについてです。
可視の特性。見えるものは、眼が走査したものではなくて、感性に触れたものである。感性に触れるものは、自身に欠けているものである。つまり、不可視である。なので、見えるもの、自身の中にあるもの、自身に欠けているものの間には繋がりがある。要するに、見えるものとは見えないものなのである。
彼の意見に本当に同意します。似たような考えが、私の映画の中にはありました。
HK:そうした考え方は、ストローブの考えに近いところがあるようです。
FA:そうなのですか?ストローブについては、私はあまり知りません。もしかするとストローブたちには、そうしたアイデアがあったのかもしれない。私は、学識豊かではありません。家に篭って何かを練り上げるような行いが好きではないです。私は実践家です。しかし、初めは建築の図面の勉強をしていました。少しだけ技術者の学校に通ったこともあります。私は発明家になりたかった。しかし、発明家の学校は存在しない。技術者学校はあっても、発明家学校は存在しないのです。そうしたものがあるなら行ってみたかったのですが、不可能です。なので、技術者は発明もするのだと考えながら、技術者学校へと通いました。しかし、そんなことはありませんでした。技術者は、構造、フォルム——-それは実際にはフォルムですらありません——を発展させます。彼らが発展させるのは、実用機械の振動に耐えるプラスチック部品のようなものです。実際には何もしていません。私が発明したかったのは、月に行くための機械です。ジュール・ヴェルヌやビーカー教授〔『タンタンの冒険』に登場する発明家〕ようになりたかったのです。そんな失望の結果、図面への興味もあったので、建築へと関心を移しました。しかし、オフィスにこもって拡大鏡を覗き続けながら、延々と家を作るようなこともしたくなかった。そんな時に、演劇とマリオネットの世界に出会いました。マリオネットの完全な自由さに魅了されたのです。なぜなら、マリオネットは実践によって成り立っているからです。実際に手を動かして練習をする以上のことはできません。しようと思えば理論化することもできます。マリオネットに関して論文を書いている人たちもいます。しかし、マリオネットはあくまでも実践です。つまり、操作です。手の動きによって操られる人形である。手によってこそ成り立つのです。
HK:初長編となる『湖』は、どのようにして仕事を進めることになったのですか?脚本自体はあったはずです。
FA:破棄することになった脚本がありました。
HK:その企画とは、数年前に企画されていたもののことでしょうか?
FA:私がカンヌの「アトリエ」〔映画監督に予算を見つける場を提供するカンヌ映画祭の一企画〕に選出された際の脚本は、すでに破棄した後のものでした。なぜなら脚本を書くにあたって、室内=昼、屋外=夜、対話、アクション、”演技の意図”のような脚本にとって必要なだとされることに基づいた書き方になっていたからです。ある時には、もう我慢ならないものになっていました。ありもしないことの心理的動きを想像しなければいけなかったのです。それとは異なり、映画もしくは企画の真っ只中においては、不可視に対する可視の特性と同じことが起こります。その結果として、本当に心の琴線に触れたものが多々見えるようになります。それは、絵画でもあるかもしれません。または、音楽、文学、詩であるかもしれません。それは、海にまつわる物語であるかもしれないし、デュラス、ヴァージニア・ウルフ、フローベール、またはその時に私が読んでいた全てであるかもしれません。そして、そうした一節が、ふと語りかけてくるのです。それこそがまさしく、その馬鹿みたいなシーン割りで書かれた脚本の甘言を乗り越えて、私が表現したかったことです。私が本当に望んできたのは、単に、死と紙一重の状態にある人を撮影するといったことでした。
HK:最終的に作品として結実することになったいくつものアイデアは、撮影した後に生まれたものなのでしょうか?編集された映像を見ると、何度も繰り返されるモチーフが出てきます。手の映像が何度か繰り返されていましたが、冒頭の手の映像を見た際には、少しだけゴダールのことを考えてしまいました。『イメージの本』の冒頭と同じく手の映像だったからです。
FA:私は、作品を作るにあたって、いくつものメモ書きをしていました。死と紙一重の状態、俳句、デュラスなどなど。脚本の左側のページは、原則的に白紙でした。そして、そこにそうした言葉を書き込んでいきました。その白紙のページを通じて、映画が育まれていくことになったのです。
いずれにせよその白紙のページの書き込みが、ある時から脚本以上に多くのことを物語っているように私には感じられたのです。そして、私はすでにその脚本に嫌気がさしていました。なので脚本を投げ捨てて、その書き込みのページだけを残して、寄せ集めたのです。それが脚本となりました。「今日は湖に行く。撮影をするのは、死と紙一重の人」といったことだけが書き込まれていました。まるで俳句を撮影するような方法です。もし俳句の言葉に真に耳を傾けて、ワインを味わうようにして感性を研ぎ澄ますことができるのならば、場の雰囲気を真に掴み、味わうことができます。そんな風な行いができるのであれば、カメラをそれまでとは同じように扱うことはできない。別の見方をすることになる。別の動きをすることになる。俳句を撮影せずとも、俳句を撮ることができる。もしその調の一部を成すことができるのなら、例えば太陽が短調の和音として聞こえてくる。その瞬間こそが、撮影すべきものなのです。モノが可視化されるのは、自分が不可視を備えているからです。テキストが自分の不可視を定義する。そして、それが自分の見るものへとなるのです。
HK:作品を見て終始印象深かったのは、音響効果です。しかしながら、その音がなかったとしても、映像が機能するようにも思いました。
FA:音響を耳障りに感じましたか?
HK:音が、映像を補足するような作りにはなっていませんでした。音だけで独立していました。同時に、編集の力が見えました。つまり、その作品の力強さは、映像の力だけによるものではない。音響は、映像とは別の次元に属しているようでした。用いられている音は、同時録音の音ではありません。それぞれの映像に連続性を与えているのが音響効果であるようにも見えます。しかし、それぞれの映像の繋ぎ自体も本当によく考えられている。たとえ音を消したとしても、無声映画のようにして映画自体がしっかり機能します。だから面白かった。そこには映像のテープがあって、音のテープがある。それぞれが独立したままでも十分に機能する。しかし、その二つが反響し合うことによって、全く異なるものが喚起される。湖の雰囲気が立ち現れてくる。それが本当に面白かったです。
FA:編集はまだ終わってはいません。まだ変更を加える予定です。
HK:台詞による対話などを付け加えるということですか?現状のようにして、無駄な説明が一切ないままで十分に思えます。
FA:それとは正反対の方向に向かっています。言葉は必要ありません。
HK:少しだけミケランジェロ・フラマルティーノのことも考えました。
FA:私はフラマルティーノの映画については、全く知りません。自身の直感に基づいて、作品を作りました。
HK:ムルナウの『サンライズ』についても考えました。
FA:『サンライズ』に関しては、オマージュと言えるところがあります。死と紙一重という点において、また湖という点において似通ったテーマです。
いずれにせよ、今朝作品を見た人たちが出来を気に入ってくれたようでとても安心しました。映画における〈時間〉に気を配っているのが私だけでないことがわかったからです。
昔のことですが、私の卒業制作の『日曜日』という作品は、カンヌのシネフォンダション〔若手映画作家の発掘育成プログラム〕に選出されました。選出された後になって、選出委員の人々が私の作品を「ひどい出来」だと考えていたことを知り、本当に驚きました。しかしロラン・ジャコブ〔当時のカンヌ映画祭ディレクターのジル・ジャコブの息子〕が、どこかの映画祭で私の作品を見て気に入っていたのです。彼は私が何をしたいのか、作品を通じて何を表現したかったのかを本当によく感じ取ってくれていました。
私はロラン・ジャコブに、初長編となる『湖』を真っ先に送りました。彼がカンヌの選出を行なっていたということもありますが、それ以上に……。私は、シネフォンダションに選ばれた作品を下地として、初長編を完成させるに至るまでに二五年かかりました。その二五年の間に、私はジャン=リュックの映画のためにカンヌにしばしば行っていました。なので。長編が完成した時には、私たちはすでに見知った仲になっていました。残念ながら、彼はもうすでにカンヌの選出をしていませんでした。しかし、とても美しい返事を送ってくれた。「この作品は少しもゴダール風ではない。そして、本当に君自身の作品になっている」。
HK:今朝の上映を見て少し驚きました。一般的に言って、映画作家の元アシスタントが作品を作ると、その影響から抜け出すことができないまま、そこそこの作品を作るだけになってしまいます。しかし『湖』は、本当に個人的な映画になっていたからです。
FA:ジャン=リュックの影響は、冒頭に引用したメルロ=ボンティのテクストだけです。
HK:個人的な映画でありながら、本当にスイス的な映画だと思いました。空気感、天候の移り変わりのようなものが見事に捉えられ、映像となっている。アメリカ人がスイスで映画を撮ると、ポストカードのような決まりきったスイスの姿になってしまいます。スイス固有の雰囲気を撮ることができません。『湖』は、本当に多くの色に溢れていました。少しだけシュミットの『パロマ』の山頂のシーンのことも思い出しました。本来、スイスにおける映像はあっという間に変わるものである。ディアブルレのような山の上にいると、雰囲気が一瞬一瞬と瞬く間に違ったものに変わります。そうしたスイスの一瞬を捉えた映画を作ることができていると感じました。僕の知る限りでは、他のスイス人映画作家はそうしたことを捉えることをあまりしていない。
FA:とりわけ湖についての作品を撮った映画作家はいません。湖自体を、舞台装置として使った初の作品です。湖畔で撮られた作品や湖を横断する作品はたくさんあります。しかし、湖上を映画の空間として用いてる作品はありません。
「不可視」に関することですが……。「不可視」は、メルロ=ポンティの言葉を知る前に行ったインスタレーションのタイトルでもありました。そのインスタレーションは、ヴヴェイで行われたレマン湖を描いた画家についての展覧会のために作ったものです。ジャン=リュックが頻繁にレマン湖を撮影していたこともあって、映画におけるレマン湖についてのビデオを作るように私に依頼があったのです。私は、映像を編集してビデオを作りました。しかし、実際には単なるビデオ映像以上のものを作りました。その時にも、映像が繰り返されるように色々と調整したのです。そして、「不可視」というタイトルをつけました。私が絵画において素晴らしいと思うのは、「見えるものを見せる」ということです(それは、メルロ=ポンティの引用でも言われていることですが、インスタレーションの際には、その言葉のことは知りませんでした)。その展覧会のために、苦しみの最中にあったフェリックス・ヴァロットンのことを考えました。彼は湖畔の高い位置から見下ろすように湖を描いた。しかし、描いている最中のヴァロットンは、喪失、死、愛されないことの不安などの苦しみの最中にあったのです。それでも湖を描いた。その感情を見ることはできません。画家は、その見えないものを表現するために、見えるものを見せるのです。私はそれを「不可視」と考えました。
後になって、ジャン=リュックがメルロ=ポンティの言葉を見つけてきました。そして、「抽象的だ」とか「神秘的だ」とか言っていました。しかし私には、とてもはっきりとわかる内容でした。つまり、画家は、見えるものを通じて見えないものを表現している。そして精神は、自分の中にある不安などの感情を見せることになる。
HK:作品の最後に引用される言葉は、作品を作り始める前からあったのでしょうか?
FA:その引用は、ハインリヒ・フォン・クライストの言葉です。その言葉は、脚本の脚注、つまり左の白紙のページにメモされていたものです。それとは異なりメルロ=ポンティの言葉は、作品を作り始めた後に加えました。作品全体を統括する言葉に思えたからです。ハインリヒ・フォン・クライストの言葉は、たまたま彼の詩を読んでいた際に見つけました。「裂け目が本性を立ち現させる」という言葉に、強い感銘を受けたのです。なので、その言葉をメモしておきました。そして、それ以前にあったヨットレースに夢中になる人々の話などの代わりに、その言葉が脚本となり、物語のあら筋になりました。
映画を“展示”する
HK:映画の〝展示〟を行うというのは、ゴダールではなく、アラーニョさんのアイデアだったのでしょうか?
FA:現在の展示は私の考えです。しかし……物事は、少しずつ出来事が積み重なる中で生み出されていきます。ことの発端となったのは、二〇一五年の試みです。『さらば、愛の言葉よ』の後に、冗談半分で「3Dの後は、3Eだ」〔Écran=スクリーン〕と言って、三つのスクリーンで実験したことがあったのです。奥に一つスクリーンがあって、左右に二つのスクリーンを並べ、三連祭壇画のようにしました。ジャン=リュックの家でケーブルを整え、『さらば、愛の言葉よ』を上映してみたのです。三つのスクリーン上に、僅かばかりの偶然性を伴いながらも似たような映像を、漠然と、それぞれの映像が独立しながらも予測不可能となる状態で上映してみました。DVDを用いて行いました。それ故、真に必要な技術を用いて行われたわけではありませんが、DVDでもそれぞれのシークエンスを上映することはできます。異なる映像をそれぞれ見せることができるということです。結果として、偶然性に支配されることになる。各スクリーンに出力されるのは、同じDVDの映像ではありません。ある瞬間には、異なる映像同士が、偶然同じ場で上映されることになります。私たちは、そうした映像を、ジャン=リュックへインタビューをするために訪れていたジャーナリストに見せました。二〇一五年の三月のことです。「So Film」という――サッカーマガジンの「So Foot」に似た名前の――批評誌を創刊した男でした〔映画批評家ティエリー・ルナス〕。その男は日曜日の夜に家に来たのですが、ジャン=リュックは、心臓の問題を起こして、そのまま……。
HK:その一件に関しては、ミトラ・ファラハニの映画『See You Friday, Robinson』にも出てきます。
FA:その一件です。ジャン=リュックが心臓の問題を起こして、病院へと運ばれたのは紛れもない現実でした。作品の中で見せられているのは、現実ではなく、映画内の〝現実〟ですが、二〇一五年に起きた出来事です。三つのスクリーンを用いてスクリーンを複数化する試みは、心臓発作の年であるその時点で止まってしまいました。
その後二〇一九年に、パリ郊外のナンテールのアマンディエ劇場での展示がありました。展示のために、映像を上映するための技術的方法を見つけなければいけませんでした。DVDで映像を上映することは避けたかったのです。DVDプレイヤーは技術的な面においては、あまり信用できるものではない。さらに、私たちは、可能な限り高画質の映像を流したいと考えていたと思います。それに対して、ある時ジャン=リュックが発見をしたのです。アイデアの大元は、ジャン=リュックの着想に基づくものです。ジャン=リュックは、小型コンピューター「ラズベリー パイ」に関する広告記事を、私が買ってきた新聞の中に見つけた。記事によると、この機器は映像を上映することができる。「これで3Dの上映ができるだろう。3Dで上演するのも悪くないはずだ」と言ってきました。私は了承しました。そして一つ、二つとラズベリーを注文したのです。機械を手に入れるのには、少し骨が折れました。それでも何とか手を尽くして、手に入れました。三〇ユーロほどの実に小さいものでしたが、コンピューターのマザーボードを備えていました。HDMIケーブルを繫いで、Linuxのプログラムを通じて、映像を高画質で流すことができるものでした。
そんな経緯を経て、ラズベリーは私の机の上にずっと置いてありました。二〇一九年の段階において、ラズベリーをメディアプレイヤーの代わりに用いて、アマンディエ劇場のインスタレーション上映に使用する考えが、私たちの中にはあったのです。インスタレーションのためには、結構な数の機械が必要でした。おそらく二〇、三〇のラズベリーを用いたはずです。規模としてはとても大きな展示で、後に続くインスタレーションの最初期のものでもあります。しかし実は、もっと以前にも遡ることができます。「Isadora」〔デジタル映像のリアルタイム操作ソフト〕を用いて展示をしたことがあったのです。最初の試みは、パリのグラン・パレで行われた「ピカソ・マニア」という展覧会のための企画でした。様々なメディアで取り上げられたピカソの作品を元にしたものでした。ジャン=リュックは、『勝手にしやがれ』の中でピカソの絵画をいくつか引用していたので、企画者から依頼があったのです。その企画のために「Isadora」を用いる機会がありました。
それから、二〇一九年のアマンディエの企画の前にも、二〇一八年の終わりには、最初の一歩となる別の企画がありました。ローザンヌのヴィディ劇場において『イメージの本』のインスタレーション上映を行ったのです。既に特定の空間における上映環境で演出を行うものでした。劇場の内部には観覧席がありました。私たちは、家具の上にテレビのモニターを設置し、絨毯を敷き、映像から離れたところにスピーカーを配置しました。しかし、空間内のスクリーンの数は一つでした。
HK:その上映企画については覚えています。当時、『イメージの本』はフランスでは上映されることがなかった。配給会社も決まっておらず、上映の機会もなかったので、スイスまで観に行く必要がありました。
FA:ジャン=リュックは、『イメージの本』がフランスにおいて、映画館で上映されることや、相応しくない形で公開されることに反対していたのです。そんな経緯もあって、二〇一八年の「劇場=スクリーン」が、最初の第一歩でした。それより以前のちょっとした小噺があります。カンヌに向けて、『イメージの本』の映像の色調を調整しいていた時の話です。ジャン=リュックは、テレビモニターで映像を修正したり、動きを考えたりしていました。元のファイル自体には、その動きは含まれていませんでした。その映像効果を生み出していたのは、テレビのモニターだったのです。作品のプリントを作るためには、彼がモニターを通じて見たままのものを、映像として加工していかなければならなかった。私は二つの映像を、同時に流して見比べる必要がありました。一方には、ジャン=リュックのスクリーン上の映像があり、他方には私のモニター上の未加工状態の映像がありました。最終的に、私の手元のファイルをジャン=リュックのものと似たようなものにするために、色調を調整していかなければなりませんでした。二つの映像を同期させるための満足いく方法は考えつきませんでした。そのため、一方の映像を停止しては、もう一つの映像を再生するといった方法で行っていったのです。そうすると、二つの映画が目の前にあり、二つの瞬間を同時に見ることになります。とりわけ三部における列車の映像などが、顕著たる例です。そこには、ジャック・ターナー『ベルリン特急』の長いトラベリングの映像等が含まれている。そうした映像を二つのスクリーンを通じて上映しようとすると、少しのズレが生み出されます。効果は、とても面白いものでした。二つの映像が同時に上映されること自体、面白い試みになるのではないかと感じられた。その体験が頭の片隅にずっと残っていたのです。
それからヴィディ劇場の上映空間を演出する企画があり、つづいてアマンディエ劇場の企画がありました。アマンディエでは、小さな機械を用いて再生映像のプログラムをするなど、本当に細かなことまで行い、映像を順路に配置することにしました。
ニヨン/ベネチアの展示
FA:二〇一九年末から二〇二〇年にかけてはニヨンの「ヴィジョン・ド・レール」〔ニヨン国際ドキュメンタリー映画祭〕における企画がありました。映画祭は、ニヨン城〔歴史博物館〕を会場の一部としており、城の一階部分を自由に使うことができました。映画祭の総合監督からジャン=リュックに、この空間で何かすることはできないかと依頼があったのです。ジャン=リュックは断りました。映画祭が依頼したのは、彼の描いた絵の展示とか、その種のことだったと思います。ジャン=リュックは拒否した。しかし私は何かをしてみたかった。『イメージの本』を単に二つのスクリーンで上映するのではなく、空間の中で解体し、第一部、第二部、第三部、第四部、第五部、そして「アラビア」のように分解して、多くのスクリーンを通じて上映する。それによって訪れた人が映画の中に入り込み、散策できるようにしたかったのです。映画を分解し再構築する。そのために、再びラズベリーを買い、プログラムを行いました。アマンディエの劇場の同じ映像を繰り返すだけのものとは異なります。ニヨンの展示のために私が新しくプログラムしたのは、より複雑なものです。たとえば一つのファイルに十篇の映像の断片を挿れたとすれば、その映像がランダムに選ばれ上映される。全ての映像の上映が終わった後は最初に戻り、別の順序で再びランダムに上映される。その順序での上映が終わったら、また新しく別の順序での上映が始まる。毎回の上映の順序を、全く新しいものにしたのです。そうしたプログラムの方法は、インターネット上にあった情報を寄せ集めて、試行錯誤を繰り返しながら作り上げて行きました。
映像のモニターを地面に置くよりも、舞台装置の一部のようにしたらいいのではないかとも考えました。IKEAの棚を用いて、空間を再構築できるだろうと考えたのです。その棚は、まさしくジャン=リュックが使っているものと同じものに他なりません。棚の様子は、「偉大な黒板」(Le grand tableau Noir=アラーニョが出版したゴダールのノートブックの一つ)で確認することができます。ノートの冒頭、ジャン=リュックは「演出を統括するシナリオ」という言葉を使っています。そして、モンタージュの棚を見ることができる。IKEAの「Ivar」という棚で、彼が昔から使い続けているものです。『JLG/JLG』においても、テーブルランプの近くの本棚が出てきますが、それはIKEAの棚です。『パッション』においても、ハンナ・シグラとイザベル・ユペールと一緒になってIKEAの棚が登場します。そんなふうにして、IKEAの棚は、必要に応じて、色々と調整することができるのです。それ故、IKEAの棚を舞台装置のひとつとして使おうと考えた。
ジャン=リュックの思考の奥底、彼が仕事をする私的な空間を表現するために、テーブルランプも使うことにしました。その光の下においては、くつろいだ感じがし、温かみが感じられます。ジャン=リュックの考えの、その繭が持つ、ちょっとした温かみを感じることができるのです。そんな考えを通して、ニヨンの展示は構成されました。ジャン=リュックは、展示の様子を気にしていました。一般公開される三日前、私は彼を迎えに行き、展示会場を案内しました。
彼は、自身の作品が空間の中で分解されるのを本当に喜んでいました。舞台装置が、映画の内容そのものと自然に一致するような働きが至る所に見られたからです。たとえば「中央地帯」は、実際に展示空間の中央に位置していました。もし「中央地帯」を見ているのであれば、その周りにあるすべての映像の音を聴くことになります。作品の上映時間の真ん中辺りが、空間の中央にも重なっています。
その展示空間の中央にいた際、記憶に焼きついたことがあります。目の前から列車の音が聞こえ、背後からは「リメイク」や「法の精神」の章の音が聞こえ、さらには、けたたましい「アラビア」の音やアヌアル・ブラヒムの曲、アフリカやアラビアの音楽が聞こえてくる。この中央においては、一組のカップルの姿を見ることになります。男女は時間が過ぎるのを待ちながら、抱きしめ合っている。男女が待っているのは、時間であり、死であり、そうした種類のことです。これがニヨンの展示でした。
その後、ベネチアの展示がありました。ジャン=リュックは関係していませんが、私は、二〇二一年の建築ビエンナーレのスイス館の共同キュレーターを務めることになったのです。スイス館から、ビデオインスタレーションの依頼を受けました。当時、インターネットで検索をしていたら、あの小型コンピューターのラズベリーをハッキングすることができるとわかりました。結果ハッキングによって、再生や停止などの操作を遠隔で行うことが可能になりました。ハッキングのためには、二〇一五年のグラン・パレの展示のために使った「Isadora」というソフトが必要でした。グラン・パレの「ピカソ・マニア」のためには、先ほど言ったように、三つのプロジェクターを用いて、三連祭壇画のようなことを行っています。ピカソの作品、メディアに表象されたピカソの作品、ジャン=リュックの映画に引用されたピカソの作品を、ランダムに旅できるようにようにプログラムしました。三連画の形式を用いてです。「Isadora」の可能性を探求してみたかったのですが、どのようにしたら二〇枚のスクリーン上の映像を管理できるのかは理解できていませんでした。二〇もの映像を、同時に出力できるコンピューターは存在していなかったからです。そんな経緯もあり、ラズベリーをIsadoraでハッキングできると知った時には、試してみたくなりました。そして、ベネチアの建築ビエンナーレのスイス館のためにプログラムをしてみたのです。
HK:そこで用いられた映像は、ゴダールの映像とは関係なかったのでしょうか?
FA:ジャン=リュックの映像ではありません。私が国境沿いで撮影してきた映像です。スイス館の企画は、スイス国境に関するものだったからです。テーマとなったのは「国境の厚さ」に関してです。展示は模型によって成り立っていました。小型トラックに乗って、スイスの国境をひと回りしたのです。国境のそばに住む人々たちの姿を模型にして展示しました。彼らがいかにして国境を体現しているかを、模型を通じて伝えたかったのです。私は、そうした人々の姿を撮影しました。二〇二一年の企画です。
インスタレーションの本質
FA:二〇二一年の終わりには、ベルリンで展示する提案を受けました。ニヨンの展示を再利用しました。しかしベルリンの展示会場はニヨンとは違い、窓も古い壁もない、真っ白な壁に囲まれた美術館のような空間でした。ニヨン城の空間は素晴らしかった。古い壁があって、歴史を感じさせる寄せ木張りの床などで造られている。外へと開かれた窓もありました。窓は、外の風景を映像の中に取り込むことを可能にしました。窓から見える風景が、まるで映像の一部のようになった。ニヨンにおいては、私は椅子をいくつか部屋の角に配置しました。人が座る場所を、文字通り角に置いたのです。とてもいいアイデアでした。まるでカメラを移動させるかのようにして、好きな位置に椅子を持っていくことができた。カメラを動かすのではなくて――カメラというインターフェースなしに――見る人を動かすことができたのです。それによって面白い現象が起こり得ます。ある瞬間には、映像を取り去って、窓の前に見る人を配置するだけで十分になる。芸術とは束の間のことに過ぎません。感情があり、それを伝える。何かを見た時、誰かと一緒に何かを体験した時に、感情が昂ります。その感情を他の人に伝えるために、絵画や音楽などの表現を用いる。人々は、作品を見たり感情を受け取ったりするために、その場を訪れることになります。もし仮に、そうした伝達を直接的にできるのであれば、それ以上にいいことはない。映像を取り去り、直接伝えればいいからです。絵画、演劇、文学、詩などのあらゆる芸術表現を取り去り、直接伝達すればいい。ニヨンの展示は、ある瞬間には、ほとんどそのようなものになっていました。『イメージの本』を解体していく。ある瞬間には『イメージの本』のイメージは必要なくなる。そこに残るのは椅子と窓だけです。極論を言うと、そのようなものです。
HK:本質だけが残るわけですね。
FA:ええ。物事の本質に行き着くのです。それは作家自身の居る場所にさえ辿り着いています。物事を見るのが観客自身になるので、観客は作家になるのです。作家は、世界を見るために作品を必要としません。作家は、世界を見るという行為を実践しつづけているのです。自分の見たものを伝えるために、作品を作らなければいけません。もし仮に、それを伝えるために作品を作らなくてもいいとしたら、本当に素晴らしいことです。
HK:それは、ある意味で、インスタレーションを通じて、ゴダールの編集台に戻るということになるのではないでしょうか?
FA:はい。編集台に留まり続けるということになります。編集台である場所に居つづける。先ほど話したIKEAの棚も編集台の一つです。インスタレーションは、その編集台を巨大に破裂させたようなものです。私たちはその中を歩き回ることになる。私の短編映画『ロール ワークショップ 旅』も同じ考えに基づいています。森のように木々が生い茂る編集台の世界の中を、ネズミの如く彷徨っていく。
ベルリン/パリ
FA:ベルリンの企画においても、同様の考えを持っていました。私はできる限りのことを行いました。ベルリンは、ドイツ人の如く、キッチリとした場所です。私は、展示空間の中のあらゆるものが整列されないように、精一杯手を尽くしました。結果、展示の全体が木製の棚でできた森のようになりました。
ベルリンの次には、パリのメナジェリー・ド・ヴェールの展示がありました。この企画では、遠隔でファイルを操作するためのハッキング技術を再び用いて、インスタレーションをするのが良いと考えました。その技術を、ジャン=リュックの映像のために使ってみたかったのです。展示のために、五台のコンピューターを使用しました。五台のコンピューターが同時に仕事をすることになった。チュール〔レース地の生地の一種〕も使うことにしました。どんな効果を生み出すかとても気になっていました。その薄い布は、出現と消失を可能にする手段でした。布をスクリーンと見立てて、正面からプロジェクターの光を当てると、普通のスクリーンのように光を通しません。反対に、後ろから光を当てると饒舌になります。面白い効果を生み出してくれるのです。
HK:チュールに関しては、よく覚えています。マックス・オフュリュスの『快楽』のダンスシーンが、部屋中に張り巡らされたチュールのスクリーンの上に映し出され、死のイメージと反響しあっていました。
FA:パリの展示では、その種の連関を絶えず起こすことに成功しました。また閲覧順路の始まりを小さな扉にしました。スイス館の展示において学んだことです。展示の準備を始めた時、スイス館を設計した建築家の考えていたことについて思うことがあったのです。その建築家はジャコメッティの弟です〔ブルーノ・ジャコメッティ〕。彼は、スイス館の正面の大きな扉から人々が入ることを考えていた。しかし一緒に作業していた彫刻家と私は、順路を逆にして、裏口にあたる小さな扉から入場し、正面の巨大な扉から退場する方が面白いことに気づいたのです。大きな扉を通じて見終わった観客を外に出すのは、見事なアイデアでした。「ほら見てごらん。君たちが見なければいけないのは、この世界だよ」と語りかけるようなものです。真に見るべきは、私たちが展示で見せたものではない。それは単なる道筋に過ぎません。本当に美しいのはこの世界です。作品を見ることではありません。
HK:そうした考えは、ゴダールの死後に生まれ出たものなのでしょうか?
FA:裏口から入って正面口から出るというアイデアは、彼の生前からあったものです。ジャン=リュックも納得していました。考えが生まれたのは、二〇二一年のことです。「イメージの讃歌」となるアイデアは、二〇二一年の段階でジャン=リュックと一緒に……。言うなれば考え自体は、私たちの中にあったのです。しかし、ジャン=リュックは去ってしまいました。私たちは、それでも展示を行うべきかどうか、判断を迫られることになります。ジャン=リュックの死を利用するような気がしてならなかったのです。しかし最終的には、私たち自身で、私たちが行なってきたことを生きながらえさせなければいけないと考えました。たとえいなくなったとしても、こんな風にしてジャン=リュックは生きつづける。だから展示を行うことにしたのです。要するに、アイデア自体は以前から存在していたものです。ベネチアの技術を用いて、さらには裏口から入って正面口から出る。そんなアイデアに基づいて、メナジェリー・ド・ヴェールの順路は構成されました。楽屋口から劇場に入場して、一般入口から退場する。私の考えでは、芸術家や作家とはそのようなものだったのです。作家、芸術家とは、受け止める人なのです。
HK:今言われたことは、とても詩的に聞こえます。その内容を次のように言い換えることもできます。〝全ては観客の中で起きる〟。芸術の世界を通過することで、現実の世界を真に見ることができるようになる。
FA:あらゆることは自分の中で起きる。芸術家は、自らすべき仕事をなしている。各々が自分にしかできないことを行う。しかし……もし観客となる人が、その表現を感じることをできないのであれば、表現されたものを自分の中で作り変えることができないのであれば……。芸術は、見る人の中で、自分なりに再び作り替えられる。なぜなら、自分の中に欠けているものがあるからです。自ら不可視のものがある……。自身の好奇心が、自ら与えるものによって育まれることを欲しているのです。しかし、それは自分自身の問題であり、芸術家の問題ではありません。芸術家は、自分なりの方法でそうしたことを示しています。しかし、それを簡単にこなしているわけでは……。
HK:アラーニョさんが現在行っていることは、とても素晴らしいことです。今日世間に溢れているゴダール神話を解体する行いに他ならないからです。
FA:神話と共に生きることはできません……。
HK:今年も、リチャード・リンクレイターによる神話の新たな一遍〔『ヌーヴェル・ヴァーグ』〕がつけくわえられたばかりです。
FA:私は見ていませんが、いい出来だと聞きます。しかし……奇妙な感じがします。ジャン=リュックが急に歴史上の人物になってしまいました。すでに二人の人物がジャン=リュックを演じています。
HK:一人目に至っては、フィリップ・ガレルの息子〔ルイ・ガレル〕でしたね。
FA:一本目の映画〔『グッバイ・ゴダール』〕が作られたのは、ジャン=リュックの生前でした。彼の本心はわかりませんが、少し得意になっているようでした。それと同時に、嫌悪感を覚えているようにも見えました……。さらには、その作品が作られたことによって、実生活においては迷惑を被っていました。
インスタレーションに話を戻すと、今まで話をしたように、少しずつ発展していったということです。メナジェリー・ド・ヴェールでは、『イメージの本』を駆け足気味に編集しなければいけませんでした。展示会場の設営上の制限もあったからです。ネット回線の問題など、多くの問題に対処しなければいけませんでした。
ある時には、「何の作業をしているのか」と自問してしまいました。チュールのスクリーンを設置して、プロジェクターを設置するなどの作業を、同時にこなさなければいけなかった。ベルリンで行った棚の展示のために、第一章「リメイク」の全ての映像を集めたファイルがありました。三台のラズベリーには、「リメイク」の全ての映像のファイルが入っていた。第二章「サン・ペテルスブルグの夜話」の全ての映像が入ったラズベリーが四、五台ありました。メナジェリー・ド・ヴェールの展示の際に考えたのは、全てのラズベリーに『イメージの本』全ての章の映像が入ったファイルを入れるということでした。そしてシステムに上映を命じることにしたのです。「今から「リメイク」に関する映像を、自らのデータソースに基づいて、好きな順序で一斉に上映せよ」。そのような指示を、プログラムのコードにして書いていきました。「リメイク」の上映を、それぞれのコンピョーターが一斉に行う。花の讃歌、列車などについて、各コンピューターが独立しながらも一斉に上映を行う。様々な映像が混じり合うことになりますから、非常に興味深いものになります。
さらに私は考えを発展させました。全体の映像を、ダンスにまつわるものを流すように指示したり、「法の精神」の章に関わるものにするように命じたり、それらを混ぜ合わせるように指示をしました。つまり、映画の全容は決して見えないようにしたのです。
上映環境が劇場だったので、座席を並べて、映画館のように上映することもできました。座席から距離のあるスクリーンに上映することも可能です。また映画上映に関して演出することもできた。空間の奥行きを利用したものであったとしても、映像と音によって成り立つ映画を、そのまま見せることもできました。しかしながら映画とは、スクリーン上に映された無味乾燥としたものだけに留まるものではありません。作品自体を演出することも可能なのです。単にスクリーン上に上映しただけでは、『イメージの本』を見ることはできません。章ごとに分かれていないからです。自分自身が「中央」の章に位置し、その周りを他の章が囲んでいる。自らの身体を移動させることで、初めまたは終わりに向かっていくことができる。そうしたことは、自らの目の前に作品がないと体験できません。
ポルトガルから新宿へ
FA:パリの企画の後には、リスボンの展示がありました。ここでは、それぞれの展示空間が章を提示するようにしました。会場は五つの部屋によって構成された、床が軋む古い木製の邸宅でした。五つの部屋は連なっており、それぞれの部屋には扉が二つありました。全体を一つの順路と見立てることが可能だったのです。建物の中央には、階段が備え付けられていました。私は「リメイク」の上映を、その階段で行うことにしました。階段を登った先の床には幾つものテレビモニターを配置し、「サン・ペテルスブルグの夜話」を流しました。上映場所からは、反対側に「リメイク」を見ることができる。反対側から「リメイク」の章に戻ることになるのです。ここでは、展示スペースに入ってくる人々の姿も見ることができました。観客にとっては、自分自身のリメイクを見ることにも繫がります。順路を進んでいくと、列車の展示があります。そこには肘掛け椅子のような座席を配置しました。座席に腰掛け、反対側にいる人々を見ることができます。次の部屋には「中央地帯」があり、さらに「法の精神」です。全体を見渡すと、一章、二章、三章、四章、五章という流れにおおよそ沿っていましたが、実際には少し違います。二章、一章、三章、五章、四章という流れになっていた。順路を反対から辿って、四章、五章、三章、一章、二章という見方をすることもできた。「アラビア」に関する展示は、建物の外で行いました。中庭に見事な木があったので、その木に果物や花の如くモニターをぶら下げて、「アラビア」の映像を流したのです。
リスボンにおける展示は妙案でした。映画というものがそのまま表現されていたからです。章から章へと移動しながら作品全体を見ること、または遡ることができた。それを行っていたのは展示空間自体だった。これがリスボンの企画でした。
HK:それとは別に、ポルトにおける企画もありました。
FA:その企画は、ポルトの「オリヴェイラの家」〔映画博物館〕で行われたものです。リスボンの企画とは全く別物です。ニコル〔・ブルネーズ〕は、パリの展示を見ていましたが、ベルリン、ニヨン、リスボンの展示は見ていませんでした。それでも彼女は、メナジュリー・ド・ヴェールにおける展示をとても気に入ってました。そんなこともあって、パリで行ったことを、会場の一部で再現できないかと頼まれたのです。彼女は、ジャン=リュックの描いた絵の原画やシナリオの原本の展示を行いました。私は、パリのメナジュリー・ド・ヴェールの『イメージの本』のインスタレーションを、規模を縮小しながら展示することになりました。ポルトの企画自体は、どちらかというと資料などを見せるという考えに基づいていました。多くの資料と共に、映画のフォルム、イメージの探索、色彩、音などに関するビデオ映像の展示もありました。
HK:ポンピドゥセンター〔パリの現代美術館〕の展示のようになっていたのですか?
FA:それとは異なります。言うなれば、大学教授の行うような展示になっていました。
HK:概要を紹介するようなものになっていたということですか。
FA:内容を説明するものです。ガラスの中に作品を展示して見せる。そうした展示方法は、私は好きではありません。
HK:ポルトの展示は、ニコル・ブルネーズの企画だったのですか。
FA:そうです。カタログのようにして展示する企画でした。彼女は研究者です。原画なり原本なり、オリジナルのものを展示したがる。私は、オリジナルの展示は――ノートブックであっても――反対です。実際に、そうしたものを人々の手に委ねると、破られたり悲劇的なことが起こり得るので、実物を見せることはしたくない。しかし複製を作ることはできます。私たちは、実際にノートブックの複製を作りました。複製を展示することで、人々に見せることはできるのです。ノートブックを実際に手にすることによって、ノートブック本来の機能に関わる「めくる」という行為を通じて、内容に近づくことが可能となる。逆にノートブックをショーケースの中に入れて展示するのは、酷いことです。ガラスの箱の中では、死んだようなものになってしまう。棺桶に入れられてしまったのと同じことです。ノートブック自体と本来的に持つべき関わりを、私たちは持つことができなくなってしまうのです。
HK:そうやって考えていくと、映画というものは元々、現在アラーニョさんが行っているようにして上映することが許されていたのかもしれません。映画は本来的に、オリジナル〔オリジナルネガやマスターポジ〕を見せるものではなく、コピー〔上映用に複製されたフィルム〕を見せるものだからです。新宿の展覧会も、そうした考えに基づいているはずです。【註:オリジナルネガやマスターポジを見せるものではなくて、上映用に複製されたフィルムを見せるもの。同時に、現実に存在するものではなくて、撮影され記録された現実の複製を見せることでもある。】
FA:はい。新宿の企画は、パリのインスタレーションを、ビルの四階分のフロアに応用したものです。まずは、ジャン=リュックが「人間の真の条件とは、手で考えることである」と語っている場所があります。その同じ空間の延長に「リメイク」がある。展示のために、建物の五フロア、あるいは贅沢に六フロア分を使うことはできませんでした。実際に使えたのは、合計で四フロアです。そのため最初の階段を、導入部として利用しています。導入部の次には、「リメイク」と「サン・ペテルスブルグの夜話」の展示室があります。主にテレビモニターとプロジェクターを通して上映される映像で構成されています。ここでは二つの章が混じり合う興味深い状況が生まれています。映像が絶えず上映され、反響し合い、争いのようになっている。階段を昇り上の階に行くと、「線路の間の花々は旅の迷い風に揺れて」、「法の精神」、そして少しだけ「中央地帯」を扱う空間があります。展示全体の真ん中にあたるので、「中央地帯」を配置しました。さらに上の階に行くと、「幸福のアラビア」と再び僅かながらの「中央地帯」を扱う展示室がある。その後は、結論部を見るために階段を降りることになります。結論部によってインスタレーションの順路は終わります。しかし、展示全体を完全に納得できるものにするだけの十分な時間はありませんでした。ですから、まだ仕事を続けなければいけません。
HK:そうした作業は、日本の会場にいなくても可能なのですか?
FA:はい。ウェブカメラを用いて会場の様子を確認したり、その種のことを通して行います。想像によって補完していくのです。
AIを用いた仮想空間展示
HK:これから先に、AI技術を活用しようとは考えていますか?
FA:はい。反アカデミズムの財団において、AIに関して、一、二ヶ月ほどのワークショップを開催したいと考えています。芸術家や学生、さらには非芸術家と非学生を招いて、AIを締め上げて、何ができて何ができないのか、私たちはどのように活用することができるのかを探求します。そうした探求は、有用なものになるはずです。
HK:その財団に関してより詳しく教えていただけないでしょうか。「ヴィラ・メディシス」〔在ローマ・フランス・アカデミー〕のようなものを目指しているのでしょうか?それとも、ヨーゼフ・ボイスの「自由国際大学」のようなものを考えているのでしょうか?
FA:ボイスの考えに近いものです。
HK:つまり、あらゆる人に開かれた空間を作るということですね。ボイスのようにして、誰もが参加できるセミナーなどを開催することも考えられますね。
FA:ゴダール財団は、探求することを使命とします。
『さらば、愛の言葉よ』を準備するにあたってまず行ったのも、探求です。プロデューサーとの契約に際して、作品を作るための第一歩として「3Dミッション」という研究を行うことを、ジャン=リュックは了承させていました。その研究は、純粋なフォルムの探究であり、何の成果をもたらさない可能性もありました。なのでもし仮に成果を出すことができなければ、作品は存在しないことになります。しかしながら仮に作品が存在しなかったとしても、かかった経費を返金しなくてもいい。私は、その探究を担当しました。私が探究している間に、ジャン=リュックは、脚本を考えることになったのです。そうした映画作りの仕方は、本当に価値ある体験でした。あらゆる実験をすることができたからです。3Dを通じて何ができるか。3Dで裸を撮影したらどうなるのか。3Dで静物を撮影したらどうなるのか。3Dにおいて、二つの2Dの画面を交ぜわせたらどうなるのか。3Dと2Dの映像を同時に流したらどうなるのか。3D空間に2Dの映像を混ぜ合わせ、クローズアップとロングショットを同じ映像の中で共存させたらどうなるのか。さらには、そうした映像を二つへ分離させたらどうなるのか。そうしたことを実験していったのです。
なので、同じことをVR、ビデオゲーム、AIを用いて続けていこうと考えています。メナジュリー・ド・ヴェールから続く一連の展示において、ランダム上映をさせるために、擬似AIを使ってきました。なので、その延長上で発展させていくことを考えています。
他のアイデアとして、テレビゲームを作るというものもあります。ジャン=リュックの全ての作品、資料を集めたアーカイブです。そのゲームは、始まりも終わりもなく、好きな時に好きなように、ジャン=リュックの作品を横断するようにして旅をすることができるものです。例えば、『ソシアリスム』の「マルタン・ガレージ」を長時間にわたり見ることがあったら、AIが子供に関係することに興味があると判断して、他の作品の子供に関する映像へと導くことになります。そんなふうにして、ジャン=リュックの映画全体を、子供に関するもの、動物に関するもの、題目やテーマなどなどに基づいて、新たな方法で見ることができるようになります。映画が、時系列に沿って見ることから解放されます。異なる年代の映像同士が重なり合ったり、分離していくようなことが起きるのです。それが現状で考えている企画です。
HK:その企画は、現実空間で展開されるのでしょうか?それともVR空間で展開されるのでしょうか?
FA:その企画を現実空間で行うとしたら、それはインスタレーション展示になります。しかし、考えていることに相応しい空間が必ずしも見つけられるわけではありません。私が考えているその企画に関しては、現実空間においては相応しいところはありません。なので、プレイステーションのようなものを用いる予定です。そこでならば、必要に応じてアップデートしていくことが可能になります。さらには、「今日はちょっとゴダールをやろう。ロールのマルタン・ガレージを訪れてみよう」と気軽にアクセスすることが出来るようになります。そうしてゲーム空間に入り込んだら、そこには地中海へと開かれた新たな扉が作り出されているかもしれません。なので、そのまま今日の地中海へと足を運ぶような真似ができます。それは、豪華客船コスタ・コンコルディア〔『ソシアリスム』の撮影後に座礁〕が浮かんでいた海の上に繋がっているかもしれません。もしかすると『軽蔑』の地中海が急に現れるかもしれません。さらには、ロールのロケ地の現在が360度カメラで撮影された映像へと導かれ、そこを探求することが出来るかもしれません。それから、それらの映像が視聴空間の中で重なりあったり、『ソシアリスム』のシークエンスにオーバラップされるかもしれません。そして果てには、現実と反響するかもしれません。
HK:その企画はとても面白そうです。バーチャル空間に関心を持ち、自身の仮想美術館を作っていた晩年のクリス・マルケルと似たようなところがありそうです。
FA:マルケルがそのような仕事をしていたとは知りませんでした。いずれにせよ、そうした映画作家の探求は、映画研究のための場であっても、シネマテークであっても、誰もが参照できるようにするべきです。資料館のカメラやフィルムのように、動きを止めたものとして扱うべきではない。反対に、まさに生成変化していくものを見せるべきなのです。そうしたものを、あらゆる方面に発展させていくことが考えられます。あらゆるところで、それを見せるべきなのです。
(おわり)
<プロフィール>
★ファブリス・アラーニョ=映画作家・プロデューサー。撮影監督としてゴダール作品に参加。
★くぼ・ひろき=映画史研究家。パリ在住。