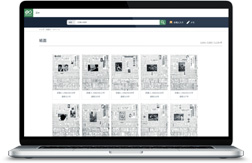お知らせ
【特別コラム】私たちは、原告にとどまらない救済、「全体救済」を求めているのです<佐藤嘉幸氏が聞く脱原発シリーズ#6>

――生業訴訟弁護団事務局長・馬奈木厳太郎弁護士インタビュー――
昨年九月、仙台高裁で「生業訴訟(『生業を返せ、地域を返せ!』福島原発訴訟)」の判決が下された。「生業訴訟」とは何を求め、その特徴は何だったのか。判決の内容に加えて、今後の最高裁での裁判闘争への見通しも含めて、「生業訴訟」弁護団事務局長・馬奈木厳太郎(まなぎ・いずたろう)弁護士にお話を伺った。聞き手は、筑波大学准教授・佐藤嘉幸氏にお願いした。(編集部)
生業訴訟とは何か
佐藤 今日は馬奈木厳太郎弁護士に、福島第一原発事故による被害の回復を求める「生業訴訟」の仙台高裁判決(二〇二〇年九月)と、群馬避難者訴訟、千葉避難者訴訟の東京高裁判決(二〇二一年一月、二月)についてお伺いしたいと思います。馬奈木弁護士は生業訴訟弁護団事務局長を務めておられ、後者の二つの訴訟にも協力者として関わっておられます。最初に基本的な前提を押さえておきます。福島原発避難者訴訟では、現在まで、高裁レベルで三つの判決が出ています。その中で、国の責任を認める判決が生業訴訟、千葉避難者訴訟の二つで出ました。高裁レベルでこうした判決を勝ち取ったことは、原発事故被害者にとって非常に大きな成果です。まず、生業訴訟の特徴からお話しいただけますか。
馬奈木 生業訴訟は、原告が福島第一原発事故の被害を受けた方々で、被告は国と東電です。求めているのは、原状回復と損害賠償(慰謝料)の二つです。原告は、昨年九月に仙台で高裁判決が出た第一陣と、福島地裁で裁判中の第二陣があって、合わせると五千名を超えています。被害の救済を求める裁判の中では、一番大きな原告団です。同様の原告たちが全国には一万人以上いますから、だいたい二人に一人の割合で生業訴訟の原告団に加わっていることになります。事故当時福島県にお住まいで、引き続き地元に留まった方もいらっしゃるし、県外に避難している方もいらっしゃいます。両方が原告になっているのは生業訴訟だけです。私たちは意図的にそうしています。地元に留まった方、県外に避難した方のいずれもが被害者であり、被害の救済を求めていく以上その実態をできるだけ詳らかにしたい。ならば、どちらか一方しか原告にいないのは望ましくない。従って原告は、北は北海道から南は沖縄までいます。また、被害を受けたのは福島県内だけではありませんから、隣接する地域(茨城、栃木、宮城県)の方も参加しています。福島県には五九の市町村があり、全市町村に原告がいます。これもそうなるよう努力してそうしました。オール福島という位置付けで考えているからです。年齢的にも、未成年者から九〇代まで全世代にわたっています。
原告の数が増えた要因としては、次のことが挙げられると思います。損害賠償の問題も大事ですが、むしろそれよりも原状回復を打ち出しました。この旗印であれば、より多くの人が参加しやすい。では、原状回復とは何を意味するのか。ほとんどの被害者の方が、「お金はいらないから元に戻してくれ」と言われている。この「元に戻す」という時期がいつなのか。普通であれば事故の前、三月一〇日となります。しかし、そうではないと私たちは考えています。その趣旨は、「元に戻せ」という言葉の真意がどこにあるのかを想像してみれば理解しやすいと思います。多くの原告の方がおっしゃいます。「こんな辛い思いは、自分たちで最後にしてほしい」。つまり、被害の根絶を求め、被害が生み出されることがない状態が、「元に戻す」という言葉の本当の意味であるわけです。そうすると、放射能のない、被害の元凶となった原発がない地域を作ることが、一つのスローガンになります。原状回復という言葉を、そうした射程の広い意味で使っています。
被害の根絶を目指すと今申し上げましたが、その点についてもう少し踏み込んでお話しします。それは、エネルギーとしての原子力にどう向き合うのか、その問題に行きつかざるを得ないということです。生業訴訟を一つの取り組みと考えると、裁判の中で「原発をゼロにせよ」という請求を立ててはいませんが、法廷外も含めた全体の取り組みとしては、脱原発を目標の一つとして明確に出しています。
福島県だけでも二〇〇万の県民がいます。原告団はその一パーセントにも満たない。しかし、原告以外の人たちが被害を被っていないのかというと、そんなことはない。そうすると、単に自分たちだけが裁判に勝って、何らかの救済を受けられただけでは、この問題が終わったことにはならない。だから私たちは、原告にとどまらない救済、「全体救済」も求めています。原告になっていない方も含めて、あらゆる被害者を救済してほしい。また、次の世代に被害が出ないとも限らない。そこまで含めて、あらゆる被害者を救済する。例えば、救済策を立法化する、制度化を図るところまでを求めている原告団なのです。
話をまとめると、国の責任を明らかにし、裁判で勝つことも当然のことながら、それで終わりでは決してなく、裁判を通じて原状回復、全体救済、脱原発の三つの目標を掲げている、ということです。それを目指す人たちが、福島県内の全市町村、あるいは隣接する地域にいて、避難した人、残っている人が一緒になって裁判をしている。そういう意味では、この裁判はかなり作り込まれた裁判です。被害救済の裁判はいろいろありますが、生業訴訟は独特の立ち位置に立っていると思います。
佐藤 生業訴訟は、被害に対する慰謝料を求めるだけにとどまらず、司法を通じて政策レベルでの救済を目指している、ということがお話を伺っていてよくわかりました。そうした方向性は最初から考えておられたのですか。
馬奈木 生業訴訟の場合、通常の裁判の作り方とは順序が逆転しているところがあります。一般的には、何か被害を受けた方が、困って弁護士に相談する。あるいは過去の公害事件であれば、健康上の被害などがあって、原因は何かを考える中で、企業や行政の責任を追及していく。しかし、今回は少し違います。二〇一一年に東日本大震災と原発事故があった当時、福島県内には弁護士が一五〇人ぐらいしかいませんでした。福島県民二〇〇万人に対してですから、相談者は大勢いても、対応できる弁護士の人数は、弁護士自身も被災していましたし、まったく足りていなかったわけです。そこで県外の弁護士に要請があって、私もそれに応じる形で駆けつけました。首都圏から応援に駆けつける弁護士も、日が経つごとに常連化し、お互い顔見知りになります。その中でどういう議論が交わされたかというと、農作物に出荷制限がかかったが、賠償はされるのか。震災のせいで仕事がなくなり収入が断たれているが、賠償請求できるのか。また、避難生活はいつまで続くのか、放射線物質による汚染のために故郷がなくなるんじゃないかなど、様々な相談が寄せられていましたので、そうした被害者の声を聞くにつれ、いずれどこかの段階で、国や東電に対して、大きな裁判を起こすことになるだろうというものでした。それならば、あらかじめ受け皿となる弁護団を先に作った方がいいのではないか。来るべき集団訴訟に向けて、事前の見通しを立てたわけです。そのことは、過去の公害裁判の経験からしても予想できることでした。
もう一つ。公害や薬害の裁判では、健康被害の原因や被害の程度が争点の中心となり、最高裁までいくと一〇年から一五年かかる。勝ったり和解したりしたとしても、そこからようやく制度化に向けての動きが始まる。そうすると、恒久的な医療対策のための制度を作るには、提訴から二〇年はかかります。私たちは、原発事故直後から、いずれ健康被害が起きる可能性もあるだろうと思っていました。しかし、被害が出てからでは遅すぎる。だから、初めから制度化を目的としたわけです。そこには医療対策や健康被害の問題も含まれる。つまり、過去の公害訴訟の経験を踏まえて、裁判を早めに始めるためにはどうすればいいか。そういった問題意識もありました。
大きくいって、今の二つの理由から、弁護団が先にできて、被害者の方たちと相談しながら、パッケージのような形でお示しをして、広く参加を呼びかけました。提訴は二〇一三年三月一一日です。最初は原告の数八〇〇名でスタートしています。それが今では六倍以上になっています。裁判の枠組みや目的に、多くの方に共感していただけたのだと思っています。
繰り返しになりますが、普通の弁護士は、依頼された問題に個別に対応すれば、仕事としては十分なんですね。福島の場合でも、避難者の方が弁護士に相談すれば、個別に対応する。その時は、どうしても目の前にいる人たちの問題に即して考えがちです。けれども相談者の後ろには、同じような人が数万人単位でいる。その人たちのことを想像できるかどうかは一つのポイントとなります。仮に想像できたとしても、一定の経験なり、過去にあった同様の裁判に関する闘いの知識がないと、今回のような裁判のイメージはわかないでしょう。逆に言えば、生業訴訟は、そのイメージがわく人たちがいて始まった。だから損害賠償の話をメインにしようとはならなかったのです。
佐藤 生業訴訟では、とりわけ原状回復という理念が特徴的だと思います。汚された大地や環境を元に戻す。これは原発事故被害者にとって最も根本的な要求であり、そうした要求ゆえに、避難された方、地元に留まった方の両方を包摂する理念としてうまく機能しているのではないでしょうか。
馬奈木 国や東電は、事あるごとに住民同士を分断しようとしてきます。例えば同心円で線を引いて、内と外で被害者かそうでないかを一方的に選別し、あるいは賠償金のあるなしや水準を変える。同じ自治体であっても、通り一本隔てて違うこともあります。そもそも被害を全てお金の問題に矮小化しようとしているところに問題があるわけです。何が被害や損害に当たるのか。その点が加害者である国と東電によって勝手に決められていて、損害に対していくら賠償を支払うのかも彼らによって勝手に決められている。その中で、被害者である住民の間で感情の対立が生じてくる。だから、向こうの作った土俵には絶対に乗ってはいけない、という思いはありました。そもそもごく素朴に考えて、被害者は何を求めているのか。お金なんかいらないから元に戻してくれ、というのが普通なんです。交通事故に例えるとわかりやすい。車を追突されて、一緒に乗っていた家族が亡くなったとしましょう。遺族は追突した人に向かって、「金を払え」とはいきなり言わないし、思わない。「家族を返せ」と思うはずです。実際問題として、賠償の基本は原状回復です。それができないならば、金銭で補填する。これが賠償の元々の考え方です。「賠償=金」ではない。その意味では、私たちはそうした理念に忠実であったし、被害者の方々の素朴な信条にもフィットする発想でした。多くの人から共感を得るためにも、お金を前面に出すよりは、原状回復を求めている裁判だということを打ち出したのが良かったと思っています。
生業訴訟の仙台高裁判決について
佐藤 現在争われている多くの裁判では、国と東電の責任が問われています。その中で、昨年九月の仙台高裁判決は、国と東電の責任を厳しく追及するという意味で、多くの人が納得できる判決でした。この判決文の厳しさは、これまでに出た原発事故関係の判決の中ではかなり際立ったものでした。例えば判決文は、東電に対して正当に規制権限を行使しなかった国の態度を、次のように厳しく断罪しています。
「平成一四年八月に一審被告東電から「長期評価」の見解の科学的根拠についてヒアリングをした保安院の対応は、国の一機関に多数の専門分野の学者が集まり議論して作成・公表した「長期評価」の見解について、その一構成員で反対趣旨の論文を発表していた一人の学者のみに問い合わせてその信頼性を極めて限定的に捉えるという、不誠実ともいえる一審被告東電の報告を唯々諾々と受け入れることとなったものであり、規制当局に期待される役割を果たさなかったものといわざるを得ない」(判決要旨八頁、判決文二〇九頁)。
馬奈木 責任論のレベルで言えば、一審判決よりもかなり踏み込んでいます。国と東電に責任があるという評価を加えるのみならず、結論を導くに当たっても、そこに至るまでの過程に関して、あるいは裁判官が示した見識も含めて、この種の裁判の中で最も水準の高いものだと思います。特に、国は何のために権限を持っていたのかという点で、期待されている役割を果たさなかったことへの強い批判と非難がにじみ出ています。例えば先ほど引用していただいたように、判決文は東京電力を「不誠実」だと断罪している。東京電力は事業者として、これほどの深刻な事故を起こさないために、当然一義的な責任を負うわけです。しかも、国の地震調査研究推進本部が二〇〇二年に公表した「長期評価」で、福島県沖で巨大津波地震が起こる可能性があると警告が発せられていたにもかかわらず、東電は、それを積極的に正面から受け止めて対策を取る決断をしなかった。対策を取るかどうか結論を先送りにし、津波対策工事のようなお金がかかることは極力後回しにしようとした。これが営利企業の性質であり、そうした傾向になりがちなのは経験的に明らかだ、と裁判所は認定しています。そして、規制する側の国は営利企業である事業者に対して、そこまで織り込んだ上でしっかり監督しなければならない、とまで断じているんですね。
判断の根底にあるものは何か。深刻な事故があったときに失われるのは、住民の命や健康、故郷といったかけがえのないものです。それらかけがえのないものを保護しなければならない。けれども、対策を取れば、事業者には、金銭的にも人的にも一定の負担がかかることになりますが、事業者は、経済的な利益を追求しなければなりません。そうした住民と事業者の双方の事情がある時に、住民の命や健康と企業の経済活動とを天秤にかけるべきではない、と高裁の裁判官は明快に価値考慮されたんだと思います。つまり、第一義は住民の命、健康である。それと事業者の損得の問題を天秤にかけてはならない。だからこそ経産大臣は規制権限を持たされている。深刻な事故が起きれば命と健康が失われる可能性があるから、そうならないように事業者を監督し、対策を取らせる権限を持っている。そのことを裁判所が判決文で認定しています。法令で権限が与えられている趣旨や目的から説き起こしている判決で、裁判所の価値序列は明快だと思います。
仙台高裁判決が出るまで、国の責任を認めない判決が多くなっていた時期があります。二〇一九年八月に、東電の旧役員に対する刑事裁判で、東京地裁が無罪判決を出しました。それ以降、国の責任を認めない判決が数多く出されています。仙台高裁判決によって、その潮目が変わった感じがあります。国の責任を認めなかった地裁判決の論拠を、仙台高裁判決は批判したわけですからね。仙台高裁の裁判官は、自分たちの判決がリーディングケースであり、最初の高裁判決でもあるので、他の裁判に影響を及ぼすことについて、かなり自覚的だったと思います。
他の判決との比較
佐藤 二〇一九年九月の東電刑事裁判の判決に触れていただきましたが、その判決は東京電力最高経営陣の刑事責任を全面的に免除する判決でした(海渡雄一弁護士インタビュー「東電刑事裁判の判決の誤りを徹底批判する」を参照。)。具体的な論点として、例えば国の地震調査研究推進本部(推本)が二〇〇二年に公表した長期評価の価値付けの問題が論議されました。判決は、この長期評価にはさほど信頼性がなかったと判断し、津波対策を行わなかった東電に責任はない、として被告を免罪したわけです。しかし推本は国の設置した正式な機関であり、それが出した長期評価を無視していいなどという判断は、裁判所の判決としてはあまりにも不自然です。それに対して生業訴訟の高裁判決では、長期評価は国の機関によって出された正式な文書であり、それを尊重するのは当然だと言っている。判決はまた、規制当局は東電に対してしかるべき規制をしなかったし、東電も津波対策を先送りにするばかりだった、として両者を断罪しています。
馬奈木 推本の長期評価は、福島県の沖合で大きな地震が起きて、津波が起こり得ることを指し示していました。推本自体が、法律に基づいて設置された国の機関です。ところが事故が起こった後になって、設置した国や東電が、推本が出した報告はたいしたものではないと裁判の中で主張するようになりました。しかし、そうした知見を無視していいのかどうか。長期評価が信頼できるものなのかどうかの判断は、確保されるべき安全性の水準の高低によって分かれてくるところです。典型的なのが東電の刑事裁判でした。確保されるべき安全性のレベルがものすごく低い。判決では、東電の対応は当時の状況において必ずしも不合理なものではなかったと言っています。その理由は、例えば当時の東電の対応について、行政機関や第三者から批判されたり、見直しを求められたりしていなかった、従って東電の対応をあながち責められない、といったものです。しかし裏を返すと、関係者みんなが弛緩した状態になっていたわけです。緊張感を欠いた状況だったのだから、何かあっても誰も責任を取らなくてもいい、という開き直った話になっています。
そうではないだろうと私たちは考えています。メタレベルで最も問題になるのは、確保されるべき安全の水準がどこにあるのか、それを考える必要があるということです。先ほど申し上げたように、何を守らなければならないのか、あるいは何を第一義に考えなければいけないのか、その設定の仕方で、水準の高低が変わってきます。深刻な災害があったときに失われるものは何かを考えれば、それはやはり住民の命と健康であり、それも広範囲かつ長期にわたる危険性があると考えた場合、当然ながら安全水準は高くならないとおかしい。そして、そのような安全水準の高さを前提にすれば、長期評価は当然無視できない知見だと評価されることになります。その最も基底となるべき価値序列に関して、東電の経済的な事情をあまりに重く見すぎているのが東電刑事裁判の判決です。
佐藤 同判決は、東電は営利企業であり、社会は営利企業の利益追求を程度容認しなければならない、という「忖度」を明確に示しています。その上で、東電に対する国の規制対応についても瑕疵があったとは言わない、という国への「忖度」も示しています。
馬奈木 その意味では、群馬訴訟の高裁判決が、東電刑事裁判と同系統の判決なんですね。企業あるいは国家の意思に応じる形になっていたと思います。ここでも、やはり第一義は何なのかが問われてきますし、最高裁でもその点が焦点になります。突き詰めていえば、住民の命や健康と企業の経済活動とは天秤にかけられないと判断するのか、あるいは命や健康を犠牲にしても企業の経済活動を優先する社会でいいと判断するのか、それが問われることになると思います。公害事件はずっとその点を問題にしてきました。例えば水俣で、住民の命と健康が破壊されましたが、そのことよりも一企業の利益の方が大事なのか。四日市でも阿賀野川でも同じです。多くの場所で同じことが常に問題になってきました。今回、また同じことが問題になっている。その意味で、原発事故がまさに公害であり、未曽有の公害だということを再認識させられます。
佐藤 今のお話から、宇井純さんの言葉を思い出しました。日本の戦後の経済成長は、地域住民に対して公害の被害を甘受させてもいい、言い換えれば廃棄物処理にコストをかけなくていいという考えと裏腹で成し遂げられてきた。そうでなければ、あれだけコストの安い生産はできなかったし、戦後の経済成長もなかった。経済成長や企業の利益追求を重視するのか、それとも人々の健康や命を重視するのかは国や企業の判断の根本的な分かれ目であり、前者の方向性が現在も支配的です。前者の判断に基づいて津波対策をせず利益のみを追求しようとした結果、東電は福島原発事故を引き起こしたわけです。
馬奈木 公害は、必ずしも戦後の高度経済成長時に特有な事象ではありません。もちろん、その時代に著名な公害が多く起こりました。しかし、そうした経済の特徴的な時期でなければ起きないのかといえば、そうでもない。少なくとも過去の出来事から見ると、これは資本主義そのものに内在している問題なのかもしれません。私たちは企業が儲けること自体を批判しているのではありません。儲け方にも良い悪いがあるでしょうという話です。そのルールがあまりにも緩い。住民の命や健康よりも企業の経済活動を優先しがちになるのは、資本主義というシステム特有の問題なのかもしれません。それをどう改めていけるかは長期的な課題だと思います。例えば、原発のコストが安いのは、原発の出すゴミ(つまり放射性廃棄物)の処理について考えなければ安いというだけの話です。ゴミの話をし始めた途端に、一〇万年単位の話になりますから、とんでもなく高いコストが明らかになる。恐ろしいのは、ゴミの話をしないで、とりあえず原発を始めましょうと、よくぞ言えたなということです。ゴミ処理の問題を脇に置いておくなんて、政策決定としてはあり得ない。それができたこと自体本当に恐ろしいですね。
佐藤 東京高裁では二つの判決が出ています。群馬避難者訴訟と千葉避難者訴訟の第二審は、国の責任を認めるか否かで大きく判断が分かれました。
馬奈木 すでにいくつかの論点について申し上げましたが、東京高裁判決でも、長期評価の信頼性について判断が分かれました。判断が分かれると、結論が自ずと違ってきます。特に群馬訴訟の場合、国に責任がないという判決が出ましたが、原子力損害賠償法、つまり今の日本の原子力推進の考え方に忠実な判決だったと思っています。原子力損害賠償法は第一条で同法の目的を定めていて、被害者の保護と、原子力事業の健全な発達に資することが目的だと言っています。教科書的には、被害者の保護と原子力事業の健全な発達と、二つの目的を持った法律だと解説されているはずです。しかし私の考えは違います。目的は一つしかない。何かあったときには多少のお金を払うから、原発をやらせろ、という宣言です。さらにいえば、お金で住民を黙らせることを宣言した法律だと思っています。その観点から考えれば、群馬訴訟の高裁判決は非常に一貫している。今の国が作った賠償基準より、多少お金は上積みした。文句があるようだから少しは払う。その上で、国の責任は認めない。
原子力損害賠償法の考え方によれば、責任は事業者にしかなく、国の責任は予定されていません。その発想に沿って、国に責任はないという判決を出しました。しかも長期評価については、それほどの信頼性はなかったとしている。つまり今の政権の政策に一石を投じる判決にはなっていません。昨年九月の生業訴訟判決とは全く違います。こちらは福島原発事故という過去の事故に対する責任を判断すると同時に、現在および将来の規制のあり方についても一石を投じる判決となりました。群馬訴訟判決だと、今後またどこかで万が一事故が起こっても、国が免責されることになりかねない。この群馬訴訟の判決と、国の責任を認めた千葉訴訟は、いずれも最高裁に進みました。最高裁でも、今の国の考え方に忠実なタイプの判決が出されるのか、あるいは住民の命と健康を第一義とした判決となるのか。頂上決戦がこれから繰り広げられていくことになります。
判決の背後にある「国家意思」
佐藤 馬奈木さんは、「二つの正義」という論考(『経済』二〇二一年四月号)の中で、次のようなことを言われていました。生業訴訟、群馬訴訟、千葉訴訟で原告は同じ主張をしているのにもかかわらず、どうして正反対の判決が出てしまうのか。司法の背後にある「国家意思」を考えざるを得ない、と。
馬奈木 同じ主張をし、同じ証拠を出せば、自動的に同じ結論が出るわけではありません。それは、いろんな事情が影響してくることだと思います。例えば私たちが、なぜ原告団を大きくしようとするのか。あるいは裁判の時、大勢の人に傍聴に来てほしいとお願いをするのか。またメディアの人たちにレクチャーして、ニュースで取り上げてもらおうと思うのか。そうした一つひとつの努力が、真っ当な判決を引き出すための不可欠な作業だと思っています。大きな熱量をもって、裁判所を説得できるかどうか。そうした様々な力学が働く中で、最終的な裁判所の判断が判決として示されるのだと思います。
国家意思に関して申し上げておくと、それはまさに原子力損害賠償法という形で具体化されているものですし、現政権が原発をやめない、推進するというのも一つの意思です。そして、これだけの被害に対していくら支払う、という賠償水準も示されています。事故後、国は、様々な施策を示しています。それを見ていくと、いくつかの考え方が明らかになります。原発利用を今後も続けていく、そのために新規制基準を作り、そこには避難計画を入れ込まないなど、一つひとつ判断して政策を形作ってきている。つまり一貫して、原発事故について国に責任があったという前提で政策を作ってはいません。まったく逆なんです。国は悪くない、責任はない。ただ国策として原発を推進してきた経緯があるので、そのことに鑑みて、法律上の文言で言えば「社会的責任」を負うと。これは法的責任ではなく、法的責任の否定です。あくまでも道義的な責任なのです。だから、国の法的な責任を否定する前提で政策が作られ、それがまさに国家意思として体現されている。そこに裁判所がどう向き合うのか。群馬訴訟の高裁判決は、はっきり言えば、行政追随という評価をする人もいるでしょうし、国の原発政策にお墨付きを与えたことになるのかもしれません。そう受け取られてもやむを得ない。なぜか。判決の論理を見ても、どれだけ手堅く判断したかを見ても、あまり説得的だとは思えませんし、私たちとは拠って立つ価値観が異なっているんじゃないか。おそらく裁判所は、証拠を見て判断するより先に、事故について国は責任を負わないという結論を、ある程度決めていたのかもしれませんね。そのように感じざるを得ない内容でした。
佐藤 その点については、東電刑事裁判も同様の印象を受けます。東電経営陣を有罪にしない判断が最初からあったと考えないと、あの判決は論理的とは言えないぐらい無理な論理を作り込みすぎている。もちろん、福島原発事故後には、国や東電の責任を認定する判決が何度も出されており、司法が変わった部分もあるかと思います。他方で、司法が「国家装置」であると如実にわかる判決も出ている。それが現状ではないでしょうか。
馬奈木 誤解がないように申し上げておくと、裁判官次第で判決が変わると、単純化して言ってしまうのも危険だと、私は思っています。敗訴した際に、「不当判決」だとか「司法は死んだ」という言葉が使われたりします。逆に勝訴すると、「司法は生きていた」と言われたりする。そのような評価には違和感があります。私たちは一審・二審判決とも勝っていますが、裁判官が最初から好意的だったとか、私たちを勝たせるつもりだったとか、後で振り返って思えるかというと、全然そんなことはありません。それぞれ厳しい局面がありました。裁判官も、基本的には職責を全うしようと思っている人たちです。あくまでも法と良心に従い、証拠に基づいて判断するのであって、どちらかに初めから肩入れすることはあり得ない。結局は、証拠や弁論、尋問などを通して説得できるかどうかだと思いますし、当事者席や傍聴席に多くの人が駆けつけて注視しているのか、メディアや署名など社会的な注目はどうなのかなど、裁判に向けられている熱量のようなものも含めて裁判の成り行きは左右されます。私たちもあらゆる手段を使って、裁判官に対する説得をしていく。その中で、裁判官がある時どこかで考えが動くとか、あるいは今まで思っていたことが確信に発展するとか、そういう場面が一つ二つ出てくるのです。そもそも生業訴訟について言えば、多くの人たちの共感を得て、政策を変えようという裁判でもあります。裁判所を説得できないようでは、共感も政策を変えようもないだろうという気持ちがあります。
原告として裁判を提起する場合、どのような請求をするのかは原告が決めます。裁判所はその原告が求めた請求についての判断を示すだけです。請求自体は原告が自由に決められますし、弁護士であれば請求が認められるかどうかについての見通しはある程度は立てられますから、判決で負けたとすれば、こちらの見通しが甘かったのか、主張を裏づける立証が弱かったのか、そのいずれかというのが一番ありえる話です。その自らの活動を振り返らずに、裁判官を悪く言う、裁判官次第で勝ち負けが決まるなどという評価が一般化すると、司法に対する信頼がなくなりかねません。やはり負けたら負けたなりの要因を考えないといけない。そうした流れが強まっていかないと、市民社会の成長には繫がらない。特に、裁判所は法的な適否を判断する場所であって、政治的な当否を判断する場所ではない、いわんや多数決の世界で決せられるべき問題について自分たちが多数を取れないことから裁判所にどうにかしてくださいと駆け込む場所ではないということは、最低限の共通認識とされるべきです。裁判官のせいで負けたとしか総括できなければ、日本の市民社会の未来は明るいとは言えません。
ふるさと喪失と民主主義
佐藤 生業訴訟では、ふるさと喪失慰謝料が認められましたね。具体的にその内容をお聞かせください。
馬奈木 避難指示区域内の人たちを中心に、ふるさと喪失に対する損害が認められ、中間指針の基準よりも賠償額が上積みされました。ふるさと喪失という損害があることを、高裁が認めたということです。これまで出ている判決で、避難指示区域内の人たちについては、ふるさと喪失に対する損害も含め、賠償額に関しては生業訴訟の高裁判決が一番高い水準となっています。しかし十分だとは思っていません。賠償が中間指針の水準に数百万円プラスされたぐらいでは妥当ではない。生業訴訟が結審したのは二〇二〇年二月です。あくまで裁判所は、その時点までの事情でしか判断しません。現に結審したときから一年以上経っていますが、この間も原告の人たちは故郷に戻れていません。いつ戻ることができるかもわからない。将来の分も含めて考えていくと、賠償額はいくらになるのか。この土地で生まれて、ずっと育ってきた人たちがいる。何代にもわたって住み続けてきた住民もいます。そういう人たちが持つコミュニティの喪失を、金銭で評価しろというのは乱暴な話です。逆に、いくらが妥当かと言われても、答えに困る部分があります。様々な無形的なものも含めて失ったことになるわけですから。習俗やお祭り、お裾分け文化のような習慣もあります。金銭で計算しづらい諸々を含めた総体として、ふるさとが失われてしまった。その評価が今の判決水準、あるいは国の定めた賠償の水準で十分見合っているかというと、納得する人は一人もいないはずです。その点は、これまでの公害と比較して、面的な広さを考えてもレベルが違う。こんなに大規模に広範囲にわたり、長期化した被害は、日本の歴史上初めてだと思います。
佐藤 原発は、人間と環境にとって極めて危険な放射性物質を使って電力を生産するため、一旦事故が起きると、広大な地域が影響を受け、それまでの生活、伝統すべてが破壊されてしまう。これは、原発というエネルギー生産システムに内在する根本的問題だと思います。
馬奈木 おっしゃる通りですね。その時に忘れてはならない視点は、エネルギーを得るために特定の人に犠牲を強いているということです。これは原発が初めてではなく、例えば石炭でも同じです。炭鉱労働者の人たちの多くがじん肺になった。エネルギーを得るために、特定の人にある種の職業病を強いていたわけです。原発では、事故が起きなくても、通常運転時に被ばくしている作業員の人たちがいます。エネルギーを消費する側の私たちは、逆ピラミッドのような形で、一定の労働者の人たちを被ばくさせながら、その上の方で「恩恵」を受けているという構造がある。もし私たちが、社会全体の合意として、一定の労働者の人たちを被ばくさせることをやむを得ない犠牲なのだと確認しているのであれば、それは確信犯としてそうするということで一つの立場だと思いますが、実際にはそのような国民的合意はないはずで、大多数の国民は単に無関心なだけにすぎません。例えば福島原発事故の直後、菅直人首相が東電に「撤退は許されない」と言いました。あの局面では、誰がトップでもおそらくあのような行動に出ざるをえなかったのかもしれません。でもよく考えれば、内閣総理大臣が、なぜ一民間企業に対してそんなことを言えるのか。あの当時のあの発言は、東電社員に「死んでくれ」と言っているようなものです。しかし、どこまでいっても東電は民間企業であって、東電社員は公務員ではないのです。こういうところにも、国民的合意がない中で原発政策が推進されてきたことの矛盾が表れていると思います。廃炉作業でもそうですね。なおかつ今のままだと、エネルギー基本計画の見直しで、またぞろカーボンニュートラルのためと言いつつ、再稼働が推進される。原発を新設しましょうといった話も出ている。それこそ深刻な矛盾だと思いますね。特定の人の「犠牲」や特定の地域の「犠牲」を前提にしたエネルギーシステムからの脱却が求められていると思います。
佐藤 つまり主権者全体が、自分たちも原発事故に対して責任があることを受け止めた上で、政治に関心を持たなければならない、ということですね。
馬奈木 主権者一人ひとりが国のあり方に責任を持っているし、政策を決められるという側面があるわけです。私たちが最高裁判決で国に勝てば、国に責任があったことが法的に確定する。その上で、国に責任を履行させるのは私たちなんです。そうやって変えられる、決められる強みも一方でありますが、他方で政治に無関心のまま、何も決めずに漫然と過ごしている恐ろしさについても、原発事故を経て、裁判を通じて問題提起したかったことの一つです。最高裁で勝ったとしても、「国」という人がいるわけではないし、判決の効果として自動的にいろんな法律ができるわけでもありません。被害者がただちに救済されるわけでもありません。結局最後は「国=私たち」が問われることになります。そういう意味でも、決して福島というローカルな話をしているつもりはありません。民主主義や、私たち自身の生き方に立ち返って考える、深い意味を持った裁判でもあると思っています。
最高裁での闘い、他の裁判との共闘
佐藤 ここからは、今後の展望についてお伺いします。三つの高裁判決が出ており、これらすべての訴訟が最高裁での審理に進みます。とりわけ生業訴訟について、今後の戦略をお話しいただけますか。
馬奈木 東電に加えて国も被告として、被害者が救済を求める高裁判決は三つ出ています。また、東電のみを被告とした高裁判決が二つで出ています。純粋に国ないしは東電を相手にした訴訟としては、高裁判決が五つ出ていることになります。特に国の責任を求めるものに限定すると、生業訴訟、群馬訴訟、千葉訴訟が最高裁に上告されています。この三つは、引き続き共闘してやっていくことになります。生業訴訟の判決は、他の一審、地裁レベルでの裁判にも影響がありますし、東電の株主代表訴訟、刑事裁判の控訴審も始まりますので、そちらにも影響があるはずです。そして、原発差し止め訴訟に対しても、一定の影響があると考えています。
先日水戸地裁が、東海第二原発について運転を認めないという判決を出しました。原発の差し止め訴訟は、従来地震の話がメインでした。例えば基準地震動が争点の中心で、あるいは活断層から想定して地震が起きたときに安全かとか、火山が噴火したときはどうかとか、専門性の強いややマニアックな点を争点として位置付けてきた訴訟でした。しかし、水戸地裁判決はこれらとは趣が異なります。深刻な災害が起きたときの避難計画に実効性があるかどうか、その計画の実現を支える体制があるのかどうか。そこに着目して、避難計画が実効的ではないから安全ではないと判断して、運転を認めないという判決を出しました。原発の差し止め裁判の中で、この点を判決のメインに持ってきて判断したのは初めてです。実は、公害訴訟などにかかわってきた人間からすると、水戸地裁型の発想がオーソドックスなんです。ごくごく普通に、ある施設の安全性を考えたときに、安全を何で測るのか。何かあったときに逃げられるかどうか。これが、多くの人から見て抵抗のない考え方だと思います。実は昭和の時代から、この考え方は取られています。有名な事件としては、大阪の千日デパートの火災や熊本の大洋デパートの火災で、大勢の方が亡くなった。昭和四〇年代のことです。事件がきっかけとなって、消防関係の法令が変り、避難経路を二つ確保するとか、避難誘導灯を付けることなどが義務付けられました。原発についても、考え方は同じであるはずです。施設に何かあったとき、内部にいる人だけでなく、周辺の人たちも含めて、安全に逃げられるかどうか。これは、命と健康を最優先に考えれば、当然のことです。ところが今までの差し止め裁判では、そこが焦点にはなってこなかった。裁判だけではないです。法令も、原発事故前には、放射性物質が原子力発電所の施設の外に出るという前提では作られていませんでした。安全かどうかの判断が、施設のなかだけで完結してきたのです。こうした考え方に対して、水戸地裁は、極めてオーソドックスな判断に立ち返りました。繰り返しになりますが、被害救済の裁判は、何を一番大事にしないといけないのかを根底に闘ってきたわけです。それが差し止め訴訟にも、いい意味で影響を及ぼした可能性があると思っています。そういう意味で、差し止めも訴訟も含めて、いい方向に潮目が変わりつつあると見ています。最高裁でも当然勝ち抜かないといけませんが、命や健康が第一義だという、ごく当たり前の考え方を社会通念として今度こそ確立していくことが大事だと思っています。
佐藤 水戸地裁の判決は、規制庁の適合性審査だけを問題にするのではなく、原発事故時の住民避難計画策定の困難さ(原発から三〇キロ圏内に九四万人が居住している)を問題にして東海第二原発の運転停止を命じる、画期的なものでした。東海第二原発を運転する日本原電は避難計画策定に携わることはできないため、この判決は原電にとって反論が難しいという意味で、大変巧妙な論理を構築しています。今の馬奈木弁護士のお話で、民事訴訟、刑事訴訟、差し止め訴訟の連帯の必要性を説かれている意味が、よく理解できました。
馬奈木 特に差し止め系と私たちは、今まであまりに没交渉でした。今後は交流を深めながら、共闘していかないといけない。弁護士同士だけでなく、原告や、この問題に取り組んでいる市民団体、NGOの人たちも含めて連携していく必要があります。それが始まりつつあって、良い方向に進んでいると思います。差し止め訴訟の人たちと同じく、私たちも原告団として脱原発を掲げています。単なる主張にとどまらず、関係する自治体の人たちと一緒に汗をかきながら知恵を出し、変えていく。そういった地道な取り組みが必要だと思っています。実際に原告団の人は、語り部のような形で、原発立地自治体で開かれる集会などで話をしたりもしています。私たちも避難計画について言うべきことは言う。自治体が住民の方を向いて仕事をするのか、それとも国や事業者の方を向いて仕事をするのか、それが問われていると思います。自治体の取るべき姿勢、役割を訴えながら、地元の人と一緒に変えていく。これは生業原告団が、ごく普通にやっていることです。この裁判は、福島県を変えようという目的を持った裁判でもあります。国が責任を認めない中では、まずは県が変わらないと話にならない。だから県にはいつも言っているんです。あなたたちはどちらを向いているのか。今までの施策は国の責任を前提にしていないし、賠償一つとっても被害実態に合わない。その時に、なぜ県が国にもっと強く言わないのか。私たちは県と何回も交渉の機会を持って、そのことを繰り返し伝えています。私たちがやっている訴訟は、福島県を変えていくところから始まり、国の政策を変えていこうというものです。同時に、この訴訟は、他の原発の立地自治体にまで影響を及ぼし得る訴訟であり、結果として脱原発につながる訴訟でもあります。立地自治体の人たちと悩みを共有しないで、口だけで脱原発を叫んでいても、なかなか事態は変わらないと思います。私たちはもっと実践的にやっていきたいと思っています。
全体救済と政策形成
佐藤 生業訴訟の理念の一つは全体救済にあると思いますが、それを実現するために、福島県に対しても働きかけをして、被害者救済の政策形成を促していく、ということですね。
馬奈木 結果として、福島県も私たちと同じ方向を向いていただければありがたいと思っています。あるいは、福島県選出の国会議員たちがどういう立ち位置に立つのか。県民世論、地元メディアの評価、一つひとつが、私たちの目指すことの追い風になるのか、向かい風になるのか、どちらに転ぶかで全く変わってくるはずです。原告を増やすことと同一線上の課題ですが、私たちが求めていることが県民の中で理解されないとすると、この取り組みはうまくいかない。逆に言うと、判決を取って終わりではない。そこから先どこまで成果を勝ち取ることができるか。これは県民だけに限定された話ではありません。国内の世論、多くの人々に必要だと思っていただけるかどうか。もちろん立法しようとすれば、国会議員が賛成してくれるかどうか、あるいは省庁が受け入れてくるかどうかに繫がっていきます。だから、私たちの訴訟は、原告団でもあるし、運動体でもあるし、事業体でもあるし、多様な側面を持ったプロジェクトだと思っています。
佐藤 裁判を通じた社会運動という位置付けになりますね。
馬奈木 政策形成訴訟は、大なり小なりそういう側面はあると思います。特に福島の三・一一に関して理念的なことを申し上げると、私たちはそれに第二の戦後という意味合いで捉えています。戦後我が国は、先の戦争に対して誰も責任を取っていない、自ら責任追及しない「無責任の体系」であると言われてきました。その後、今を生きる戦後生まれの人たちにとって、人生で最大の出来事は何かといえば、おそらく三・一一になると思います。その時にまた、誰も原発事故の責任を取らないとすれば、戦後の過ちを繰り返すことになる。そうした点は意識しています。
被害者の方で、「私たちは何も悪いことしていないのに、酷い目にあった」とおっしゃる方がいます。確かに何も悪いことをしていないかもしれません。しかし、私はちょっと引いてみるときがあります。「悪いことはしていないかもしれないけれど、何もしてこなかったんじゃないですか。だから、こんなふうになっているのではないですか。事故があってもそんな認識だとすると、また何か酷いことをやられるかもしれませんよ」と。そもそも原発事故以前に原発の危険性を指摘した人がいたことは、皆さん知っていたわけです。それでも結局、国は原発を続けてきた。それについて、多くの人は自らコミットしてこなかったし、政策を変えさせてこなかった。事故が起こって、酷い目にあって、そのことにようやく気付いた人々がいた。そして、国は原発をやめるのかといえば、いまだに続けようとしている。その人たちの方が力を持っている中で、「私たちは何も悪いことはしていない」と愚痴っているだけでは、主権者の認識としては甘いのではないでしょうか。福島を知っている以上、第三者、傍観者の立場はないはずです。第三者、傍観者の立場というのは、万が一どこかで事故があったとき、その人は国などの原発推進の人たちと「共犯」関係にあり、福島を知っているにもかかわらず反対しなかったという意味で、推進側に加担したことになり加害側に属することになるのではないのか。それが嫌だから、私はこちら側にコミットしているということでもあります。三・一一以降、そのことが一人ひとりに問われているのではないでしょうか。
そのように考えていく中で、生業訴訟を改めて位置付けてみると、問題は主権者としての実践、大人としての責任を果たすということなのだと思います。誰も責任を問わなくていいのか。次の世代に今の状態を引き継がざるを得ないことに対する、大人としての責任のありようといういい方もできるかと思います。裁判の勝ち負け以上に、こういう取り組みを理解し、取り組みに加わってくれる人がどれだけ増えるか。この点が、これからの民主主義にとって重要だと思います。
佐藤 生業訴訟原告団は、二〇二〇年一〇月、国に賠償基準の見直すよう働きかけを求める要請文を、県と福島市をはじめとした県内の市町村に提出されています。最後に、この要請文について具体的にお話しいただけますか。
馬奈木 裁判に勝てば、国の責任が明確になります。しかし、国が自ずと法律を作って、いいことをしてくれるのか。そんなことはありません。最高裁判決で勝ったとして、判決の直接の効果として国が最低限やらなければならないのは、原告との関係で賠償金を支払うことです。私たちはそこから先、何ができるのか。勝訴判決を梃子にして、責任の明確化や原状回復、全体救済まで含めて、原告にとどまらない救済を求めていきたいと思っています。国に法的な責任があることが確定すると、責任と被害は表裏の問題ですから、国は法的な義務として被害者を救済しなければならないことになりますし、それは被害に即した形で、被害に見合った形で救済しなければならないわけです。簡単に言えば、お金だけの話ではなくなる。医療や、生活再建、除染に関わる様々なプログラムが、法制化に向けて課題となってきます。ここまでが原告団の要求項目になります。私たちは、その着地点を見据えて動いています。だから、単に裁判だけ勝てばいいという話ではない。私たちが求めている原状回復は、水俣で語られた「もやい直し」までを射程に入れています。地域づくりや人間関係の再構築も含んだ原状回復です。賠償の有無や多寡、避難したかしていないか、福島県内か県外か、放射性物質の危険性をめぐる認識など、そうしたものをめぐって住民の間で、感情や意見の対立がないわけではありません。そうした分断をどう手当てしていくのか。これはかなり息の長い取り組みになります。それが後の人たちにとって、あるいは福島やその周辺の人たちにとって意味のあることに繫がればいいなと思いますし、原告の人たちはもちろんその思いでやっています。それがこの裁判の特徴です。
最高裁の判決言渡しは、過去の事案を参考にすると、早くても来年でしょう。三事件がほぼ同時期に最高裁に上がっています。最高裁の同じ小法廷に係属すると考えられますので、同じ裁判官が三事件について判断することになります。生業訴訟、千葉訴訟は国の責任を認め、群馬訴訟は国の責任を認めないと高裁判決が分かれていますから、最高裁はこれを統一しなければなりません。最高裁が、住民の命や健康が第一義だと正面から認める判決を出すことを確信し、今後も取り組みを続けていきます。(おわり)