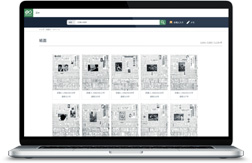お知らせ
【What’s New!】週刊読書人2024年6月7日号
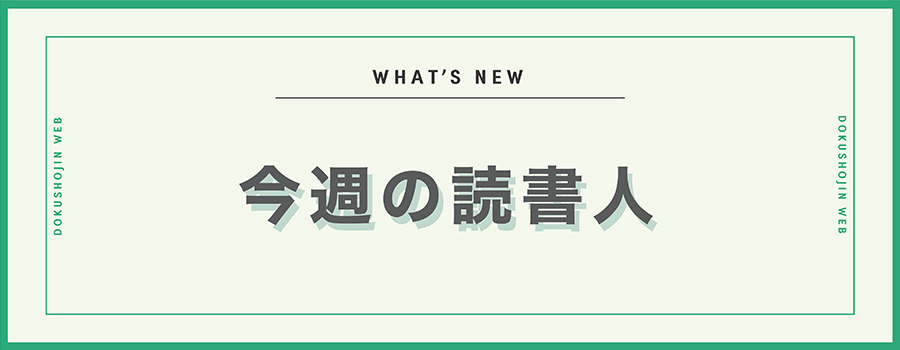

【特集】対談=宮﨑裕助・土田知則
デリダとド・マンの「読むこと」を問う
『読むことのエチカ』(青土社)刊行を機に
【本紙イントロより】
ジャック・デリダとポール・ド・マン。脱構築思想を代表する両者のテクストに真摯に向き合いながら、わたしたちの生と切っても切り離せない、「読むこと」の省察と実践を行った宮﨑裕助著『読むことのエチカ ジャック・デリダとポール・ド・マン』(青土社)がこのたび刊行された。
本書刊行を機に、著者で専修大学教授の宮﨑氏と、『ポール・ド・マン 言語の不可能性、倫理の可能性』(岩波書店)などの著書で知られる千葉大学名誉教授の土田知則氏に、いま何故、脱構築が必要なのか、脱構築から読むことへの問いをめぐって対談いただいた。(編集部)
私事ながら、本紙で脱構築、特にポール・ド・マンに関する企画に携わることがしばしばあり、前回は2018年6月22日号、『ポール・ド・マンの戦争』(彩流社)刊行トークイベント採録(対談=土田知則×巽孝之)を担当しています。なお、本特集の最終パートでもいわゆるポール・ド・マン事件については触れられていますが、事件のディテールを知りたい方はぜひ前述の土田さん巽孝之さんの対談をご参照ください。
では、今回の宮﨑裕助さんと土田知則さんの対談はどういった主旨のものなのか。冒頭宮﨑さんが本書の紹介を兼ねて次のように語っています。
「本書は、思想史的な関心で脱構築の展開を追うこと(中略)以上に重要な目論見としたのは、デリダとド・マン、この二人にとっての「読むこと」はどういうことなのかを問うことです。互いの緊張関係の中から出てきた脱構築はそもそもどういった問題に取り組もうとしていたのか。(中略)少なくとも不可欠な焦点の一つとなるのは「読むこと」への問いだと言えます」
続けて宮﨑さんは次のように発言をします。
「「読むこと」に関してはとりわけド・マンが主題的に展開し、デリダはむしろド・マンに引っ張られるところがありました」
ゆえにド・マンを引き合いに出しての議論が対談のベースになりますが、その思想的な部分、「読むこと」の問いはド・マンとデリダの関係性のなかで共有されているものというのが宮﨑さん、土田さんの共通理解として話が進みます。
本稿の最後に、土田さんによるデリダとド・マンの比較も簡単に紹介します。
「二人の文章を比較してみると、私からするとデリダの書いたものはわからないけどド・マンはわかる、みたいなところがあります」
本書のタイトルにある「エチカ(倫理)」、「読むこと/書くこと」、「アレゴリー」この3つが本対談を読む上でのキーワードとなります。ぜひご一読ください。(編集部峰岸)
【今週の読物】
▽島田潤一郎さんインタビュー(聞き手=北條一浩)『長い読書』(みすず書房)刊行を機に(8)
▽論潮〈6月〉(橋爪大輝)(3)
▽文芸〈6月〉(柿内正午)(5)
▽著者から読者へ=『如何なるや人倫』(清水昭三)
(7)
◇連載=「『ここに幸あり』撮影の頃」(ジャン・ドゥーシェ氏に聞く)(聞き手=久保宏樹)(5)
◇連載=〈書評キャンパス〉九段理江『東京都同情塔』(下澤小春)(5)
◇連載=日常の向こう側 ぼくの内側(横尾忠則)
(7)
◇連載=American Picture Book Review(堂本かおる)(7)
◇連載=百人一瞬 Crossover Moments In mylife⑰・グラハム・パークス(小林康夫)(7)
【今週の書評】
〈3面〉
▽茂牧人著『否定神学と〈形而上学の克服〉』
(秋富克哉)
▽アレックス・シザール著『科学ジャーナルの成立』
(鶴田想人)
〈4面〉
▽エリック・J・シャープ著/久保田浩・江川純一・シュルーター智子監修『比較宗教学』(岩田文昭)
▽吉村竜著『果樹とはぐくむモラル』(辛 承理)
▽エドワード・W・バートン=ライト著『シャーロック・ホームズの護身術 バリツ』(川成 洋)
〈5面〉
▽松浦寿輝・沼野充義・田中純著『徹底討議 二〇世紀の思想・文学・芸術』(川口好美)
▽新井高子著『おしらこさま綺聞』(笠間直穂子)
〈6面〉
▽朱喜哲著『人類の会話のための哲学』(小林雅博)
▽豊田泰久=語り手/林田直樹=聞き手『コンサートホール×オーケストラ 理想の響きを求めて』
(中川克志)
▽岩井秀一郎著『軍務局長 武藤章』(加藤聖文)