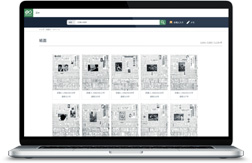お知らせ
【特別コラム】鈴木演劇の「惑星的」力――西洋近代を無化し解体し、断絶を超える――鼎談=本橋哲也×成田龍一×小川公代【本紙続き】

※こちらの記事は週刊読書人2024年11月29日号 1~2面の続きとなります※
鈴木忠志氏のSCOT(Suzuki Company of Toga)が、二〇二五年、富山県利賀村に拠点を移しての活動五〇周年を迎える。それを前に、東京経済大学教授の本橋哲也氏が『鈴木忠志の演劇 騙る身体と利賀の思想』(月曜社)を十二月中旬に上梓する。これを機に本橋氏と、歴史学者で日本女子大学名誉教授の成田龍一氏、上智大学教授で英文学を専門とする小川公代氏に、本書を中心に鈴木忠志氏の演劇について大いに語っていただいた。(編集部)
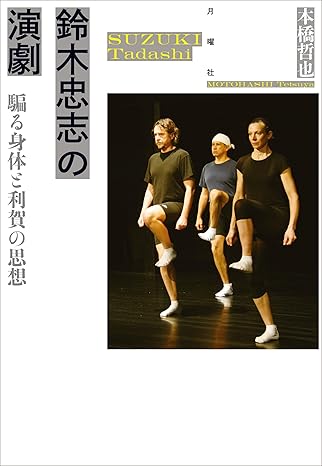
■「自己であることの不可能性を、不断に感じ」ながら
成田 鈴木さんは上演ごとに演出を変えていますが、一貫して日常の身体と言語、同時に時間と空間を揺るがし、観客にメッセージを投げかけています。「近代」が作り出してきた歴史や時間の概念、身体と言語、それが発動する空間の概念を相対化する。いや、それにとどまらず、いったん無化した上で、どのように再構成しうるかを、たえず観客に投げかけていると思います。
こうしたことを考えるとき、本橋さんは重要な指摘をされています。演劇にある「三つの時間」です。出来事が起こった時間(当然にも「時空間」となります)と、それが書き留められた時空間、さらに上演されている現在の時空間――大過去と過去と現在、「三つの時間」が演劇にはあるとの指摘です。演劇が本来持っているそうした時間の重層性を、鈴木さんは混淆し再構成し、一人一人の人間が有する時間と空間――歴史を可視化しようとしていると思います。そのことが、鈴木演劇における「近代」批判に繫がってきているのではないでしょうか。

小川 成田さんの論点に繫げて、シニフィアンとシニフィエの対立についてもう少し話したいのですが、ウォルター・ペイターは、「芸術は常に音楽の状態を希求する」と言っています。今、成田さんがおっしゃった三つの時間は、本来は同時に現前させることは不可能ですよね。でも語りによってそれを束ねることは可能なのではないかと、お話を聞きながら思っていました。つまり、廃車の男とは誰なのかということです。こんなことを言ったら怒られるかもしれませんが、廃車の男は鈴木忠志さんなのではないかと。
『廃車長屋の異人さん』の演出ノートを読んでいたら、書こうとする若き日の鈴木忠志さんが出てきたんです。ソビエト連邦についてのニュースをテレビで見ていた、と同時に美空ひばりの歌謡曲が流行っていたと。ソビエト連邦と美空ひばりを、論理的に関連付ける人はいないと思うのですが、実際に「今になってみれば不思議なことだが、この極端に違う両者を支持する文化人たちには、社会的な弱者に対する思い入れと、反米的な心情が共通に流れていた」「その文化人たちの心情には、いささかの違和感をもっていた私だが、しかし私なりの思い入れもなかったわけではない」と。
戦後まもない日本には、やはりヘカベ的な存在がいたのだと思います。ヘカベとは唯一の女性を示すものではない。渡邊英理さんは『思想』に、「複数の「女たち」の記憶の抗争」と書いていました。そしてヘカベの義理の娘アンドロマケの暴行される場面が出てきますが、当時、性の防波堤となった女性たちは、彼女に体現されている。
古代ギリシアを舞台とする演劇を、戦後日本として見直せば、ヘカベもアンドロマケも、貧困に喘ぎ体を売るしかなかった女性たちと重ねることが可能であり、ではそうした当事者たちがその記憶を語れるかと言えば、ヘカベは「沈黙」するのだ、と本橋さんは書いています。なぜ沈黙するのか。それは、語れないからです。
戦後まもない時代、そこには弱者に心情的に寄り添う鈴木さんがいたのではないか。それが舞台上の、廃車の男なのではないか。

成田 興味深い議論で、小川さんならではの指摘ですが、廃車の男も語らないですね。
小川 語れないんですよね。でも、サミュエル・ベケットの台詞を語る。「歴史にもおさらば…記憶にもおさらば…」と。演出ノートの中の鈴木さんはまだ書いてはおらず、最弱の人を見続けて、何か書かなければいけないのではないか、と思っていたのではないか。
鈴木さんの演劇の中に、同時代の演歌や歌謡曲がなぜ出てくるのか。『エレクトラ』にも『トロイアの女』にも、『世界の果てからこんにちは』にも出てきます。それは先ほどのウォルター・ペイターの「芸術は音楽の状態を希求する」という言葉に重なると思うんです。語れないものは音楽に語らせるのだと。
『サド侯爵夫人』のサド侯爵の不在について、本橋さんが繰り返し言及するのも、そのことに通じるのではないでしょうか。家父長の不在によって女性たちが語るわけですが、そこには刹那的な体験しかないんです。永遠に語り続けるという、語りの状態を固着させることはできない。アルフォンスの不在とは、芸術の音楽性、シニフィアン性を示すための、道具立てなのではないかと。語りはそこに凍結できない。演劇は生きているものだから。
成田 よくわかるのですが、鈴木さんの方法論を、私は異なる方向から考えています。鈴木さんが意図しているのは、文脈の解体でしょう。泉鏡花のもつ文脈を壊す、あるいはベケットがもつ文脈を壊す。壊した上で、鏡花やベケットから切り取った「断片」を再構成することで、新たな文脈を浮上させる作法となっています。
小川 確かにそうですね。たとえば『シラノ・ド・ベルジュラック』で驚いたのは、「ごまたきのブルゴーニュ風」というメニュー。原作は西洋のものですが、登場するのは、着物を着た江戸時代の侍であり、着物を着た女性にブルゴーニュ料理が作れるかと言えば、ごまたきになってしまう。そうしたブリコラージュがあちこちになされているんですよね。
西洋文化でよしとされるのは、理路整然とした一貫性です。でも明らかに、鈴木演劇の『シラノ・ド・ベルジュラック』には一貫性がない。
ブリコラージュを届けられ、私たち観客はいったん、ある種の拒絶反応を示します。そんな料理はないと。でもその不可能なものを、想像世界で共有させられ、おかしみや価値観の解体が起こる。
それが、私にとっては、鈴木演劇に出てくる歌謡曲でもあります。『トロイアの女』に出てくる欧陽菲菲の歌は、ただただセンチメンタルです。
鈴木さんは、ある種の美学的な正解や一般的な基準から離れようとしているのか……。歌が流れる前に、音が鳴りますよね。
成田 はい、ヘカベが空き缶を放り投げますね。
小川 あれを「トロイアの最後の音」だと、国が滅びた音であるとヘカベが言うわけです。その空虚な音には、記憶と歴史をめぐる、この物語が象徴されている、かもしれない。
ブリコラージュ的な手法は、この場面で、ヘカベの風呂敷の中から、箱、笊、缶、七輪を取り出させもします。そして一貫性という、西洋からもたらされた恩恵を、歌謡曲によって打ち壊すわけです。しかし、「I want you to love me tonight」について、その意味を考えたのですが、結局わかりませんでした。文脈にそぐわないこの歌が組み込まれる理由をお聞きしたいです。
成田 「西洋近代」が作り出し「日本」にももちこんだ、時空間の均一性・一貫性・統一性。それを解体する試みは、他ならぬ本家の「西洋」でもされています。ここでは「手術台の上のミシンとこうもり傘」などのシュルレアリスムを念頭に置いているのですが、「西洋自身による西洋の自己批判」がすでになされているのです。このとき、それをそのまま日本にもってきたら、浅薄な解決の仕方になってしまうでしょう。再度の「西洋」模倣に陥ってしまいます。そうではない「西洋近代」の解体の実践として鈴木演劇を考えるとき、そのひとつの方法――実践として、歌謡曲が導入されているのではないかと思うのです。
小川さんは「ブリコラージュ的な手法」と言われましたが、鈴木さん自身は「本歌取り」と言っています。つまりシュルレアリスム的実践は、「西洋」のみが試みたものではなく、他ならぬこの「日本」でも行われていたということです。「本歌取り」によって、一貫性や均質性に亀裂を入れ、「ずれ」を加え、本歌とは異なった文脈に転換する営み。それを応用し、「西洋近代」にどのような議論の展開があったかを熟知した上で、そのやり方に乗らずに物語を解体していく、鈴木さんならではの方法だということです。
その時、取り込む演歌、歌謡曲は、「断片」ではなく、丸ごと一曲でしょう。曲全体のコンセプトをふまえ、それを劇中の文脈にぶつけ、あらたな意味を生じさせていきます。『講談・からたち日記由来』では、島倉千代子の「からたちの花」がその役割をもち、鈴木さんのメッセージへの触媒となっています。それは人々の形にならない「記憶」を、歌謡曲が代表(あるいは領有)しているという認識とも通底しているように思います。
小川 先ほどの、ソビエトの共産党と美空ひばりが、鈴木さんの中では不思議に繫がっているという話ですが、そうした意識というものが、鈴木さんの原点にあるのかもしれない、というのが私の読みです。
私は島倉千代子さんも美空ひばりさんの歌も、母が歌っていたから記憶しています。何十年も昔に人々の中に保存された集合記憶としての音楽を、舞台で流し台詞にも盛り込むというのは、鈴木さんの演劇の特異で面白いところだと感じています。
最後にもう一つだけ、この本では「演劇とは何か」ということを、常に問い続けています。本橋さんは演劇衝動とは、「自己であることの不可能性を、不断に感じるところから発してくる」という鈴木さんの文章を引いています。舞台に対面する私たち、あるいは舞台上で演じる人たち、それを美だと認識する私たち、日々社会に生きる私たち――自己は常に引き裂かれている。「自己であることの不可能性」を大前提として、この本は書かれているんです。それでは私たちにできることは何もないのではないかと思いきや、本書は言葉に表さぬまま、ネガティブケイパビリティを導入しています。
成田 なるほど。そこが小川さんに響いたのですね。
小川 ネガティブケイパビリティとは、対立する二つの価値の間で、どちらも選ばず宙ぶらりんでいられる状態のことですよね。演劇に対して、具体的で微細に分析はしても、決して解釈を断定しないところに、私は本書の価値を感じています。読者に解釈を開いて考え続けさせる、これはエンカレッジングな本です。
成田 現実世界では、専門や立場やイデオロギー、あるいはジェンダーによってさまざまに分断され、それぞれは断絶させられています。しかし鈴木さんの演劇を観るとき、誰かの意見が突出するのではなく、まったく逆に様々な繫がりが生まれ、様々な議論が可能になるように思います。演劇はそもそもそれを可能にする――古い言葉で言うと「サロン的なもの」を生み出す力を持っているのですが、鈴木演劇は緻密に構成され、役者たちのテーマを支える強い演技力があるため、とくにその要素が強いでしょう。利賀という空間も、観劇のあとゆっくりと議論する時間を提供しています。
本橋 お二人からこれだけ様々なお話を聞けて、本当に光栄です。

小川さんが先ほど引用してくださったように、まさに「I want you to love me tonight」なのだと思います。当事者全員がyouです。鈴木さんの演劇を培うのは、まさにこの「I want you to love me tonight」。でもtonightですから、明日にはもうないんです。
小川 なるほど!
今、成田さんがおっしゃった、様々な断絶を超える鈴木演劇の力については、「スズキ・メソッドを前提条件とする共通の集団的身体文法だけが可能とする、真の普遍的で惑星的なことば」と本書に書かれています。断絶を超えるのは「惑星的」な力だと私も思っています。今日はこの本を通して語り合えて良かったです。
しかし本当に鈴木さんの演劇は奥深い。毎年、皆さんが利賀に通う理由がわかります。
本橋 鈴木演劇はパルマコンですから危険ですよ、毒にも薬にもなる。我々はもう沼にはまっています(笑)。
小川 最初にソート・プロボーキングと言いましたが、この本を読んだり、鈴木さんの劇を見ると、考えが止まらなくて大変です。いい演劇とはそういうものなのでしょうね。
本橋 十二月の吉祥寺では、新作『世界の果てからこんにちはⅢ』が公演されます。
小川 楽しみです。
成田 二〇二四年現在、本橋さんの本があらたに加わり、鈴木さんの演劇にこれだけ注目が集まっていることの背景のひとつには、世界が不気味な動きをはじめていることがあると感じています。国籍もジェンダーもあらゆる立場も超えた繫がりが求められる中、みながそれを論ずる対象と、対話を可能とする時間・空間を希求しています。このとき、鈴木さんの演劇がその一つの求心力となっていると、改めて思います。そのことを、今日は多角的に論ずることができました。 実を言えば、演劇批評の話の方法をめぐる議論も準備をし、明治から昭和にかけての演劇批評のアンソロジー集――ぶ厚い本ももってきたのですが(笑)、話題が豊富に提供され、そこまで行き着きませんでした。この続きは、新作の合評も重ね、またお話する機会があればと思います。どうもありがとうございました。とりあえず、幕を下ろすことにいたしましょう。(おわり)
プロフィール
★もとはし・てつや=東京経済大学教授・イギリス文学・カルチュラル・スタディーズ。著書に『ポストコロニアリズム』『思想としてのシェイクスピア』、訳書にレベッカ・ウィーバー= ハイタワー『帝国の島々』など。一九五五年生。
★なりた・りゅういち=日本女子大学名誉教授・近現代日本史。著書に『歴史像を伝える 「歴史叙述」と「歴史実践」』『歴史論集』『増補「戦争経験」の戦後史 語られた体験/証言/記憶』など。一九五一年生。
★おがわ・きみよ=上智大学教授・ロマン主義文学および医学史。著書に、『ゴシックと身体想像力と解放の英文学』『世界文学をケアで読み解く』『ケアの倫理とエンパワメント』など。一九七二年生。