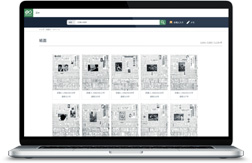お知らせ
【特別コラム】1/17号8面 対談=堀川惠子×松永正訓<医療は誰のためのものなのか>【本紙続き】

※こちらの記事は週刊読書人2025年1月17日号 8面の続きとなります※
ノンフィクション作家の堀川惠子氏が、『透析を止めた日』(講談社)を上梓した。夫の壮絶な最期を悔いとともに反芻しながら、どうすれば透析患者は「安らかな死」を迎えることができるのか、これまで書かれることがなかった難問と向き合う。刊行を機に、小児外科医でノンフィクション作家の松永正訓氏と対談をお願いした。(編集部)
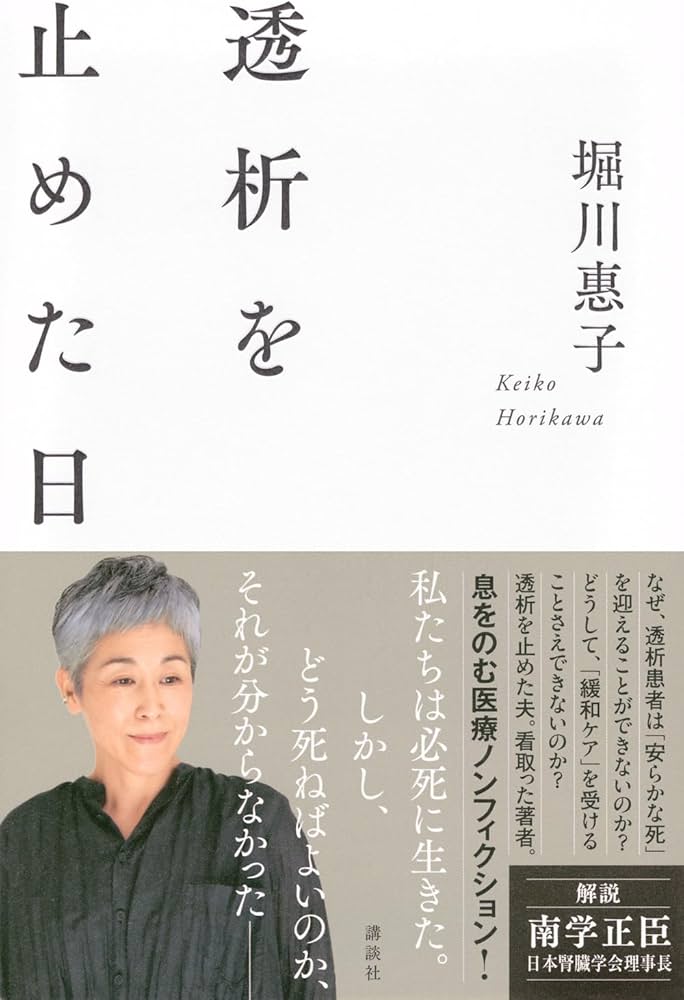
(本紙からつづく)
■透析患者の終末期はケアされずもだえ死ぬ
松永 僕の大学病院での研究や臨床のテーマは小児がんでした。二〇三人、小児がんの患者の治療をして、そのうち六〇人が亡くなっています。医者になったのは一九八七年のことですが、その直前にWHOががんの疼痛治療について発表をしています。千葉大学病院の麻酔科の教授は、がんの疼痛緩和に関心をもっていたため、僕は医者になって一年目から、がんの末期の子にモルヒネを使っていたんです。
堀川 八〇年代にですか。
松永 はい。最初は麻酔科の先生と相談しながら、最後の五年は全部自分でしていました。子どもにモルヒネは強すぎるので、一番多く使ったのはフェンタニルです。それでコントロールできない場合は、第二部にも出てきた、PCAポンプを使いました。林さんにも、なぜPCAポンプを使わないのだろうと思いながら読んでいました。PCAとはPatient Controlled Analgesiaの略ですから、患者さん自身が、自分が痛いと思ったときに自分の手で除痛できるので、安心感を得られるんですよね。そんなものとっくの昔に使われていたのに、日赤医療センターは何をしているんだろうという感じでした。
堀川 この本が出て、品切れ状態が続いていて、日赤の緩和ケア科に問い合わせが入ったのか、慌てて本を送ってほしいと連絡がありました。つまり肝胆膵外科で行われていたことは、緩和ケア科は知らなかったわけです。
松永 日赤ですよ、天下の。
堀川 慶應にしても日赤にしても、たとえば公立福生病院に比べれば、はるかに人手もある恵まれた環境と言われますが、それでもこうなのかと。
今回取材中に多くのドクターに言われたのは、確かに大変だったと思うけれど、堀川さんはまだマシな方だと。少なくとも日赤病院だったし、二四時間付き添うことができた。コロナもあって、ほとんどの患者はカーテンに閉ざされた中、一人でもだえ死ぬ状態なのだと。糖尿病の患者などは、下肢壊疽で両足切断されたまま、透析をまわし続けることもあるしと。
松永 それは何の慰めにもならないですよ。
堀川 言いたいのは、透析患者の終末期は、それほどまでにケアされていないということです。
松永 そうですね。
堀川 しかし松永さんが、緩和ケアを八〇年代から実践しておられたとは驚きました。日本ではまだがんの告知も許されない時代でしょう。
松永 八七年は患者に病名を言っていませんでしたね。小児医療で多いのは固形がんの治療で、患者は一歳から五歳ぐらいの幼少期が多いです。告知する年齢ではないのですが、一方白血病の患者はもう少し年齢が高く小中学生なので、九〇年代ぐらいから小児科医は、白血病の治療時には告知をしていました。子どもを騙すのは無理だからです。
堀川 一つこれまで言っていない告白をします。慶應病院で林が口腔外科にかかるとき、小児科のフロアと同じだったことがあって、よく子どもたちの姿を見ました。大人でもこんなに苦しくて人生に喘いでいるのに、あんな幼い子どもが同じように闘っているのかと。
私は遺言で、お金が遺ったら、小児医療に関わる人たちに全額寄付しようと決めています。
■透析患者への緩和ケアの現状
松永 第二部には大事なことがたくさん書かれていますが、そのうちの一章が「透析患者と緩和ケア」です。いろいろな医者にインタビューしておられて、読むと腎臓内科の先生たち、皮尿器科の先生たちが、それぞれに悩んでいることがわかります。
様々な意見があります。死の直前まで患者を苦しませながら透析をまわし続けて本当にいいのだろうか、という問題提起もあれば、尊厳死を希望して透析を止めた結果、苦しみながら死んでいく姿を見て、その決定を患者に委ねていいのか、医者が導くべきではないかという問題提起もある。安芸市民病院の緩和ケア部長である松浦将浩先生の臨床研究発表によれば、緩和ケアチームと透析チームが話し合い、患者の意思を尊重して透析休止を決定したのに、最後の最後で透析チームの意向が翻ったという。
日本の医療現場は、延命することによって苦しみが伸びるだけの治療はすべきではないという、尊厳死の考え方に向かっていっています。日赤病院の医師が「倫理上」という言葉を持ち出したのも、その流れの上でのことです。透析は進むも地獄、止めるも地獄。まわし続けるのも苦しいし、まわさなければ尿毒症になって、溺死のような悲惨な最期になる。
尊厳死の定義には、治療の差し控えと、治療の縮小、この二つが該当しますが、新しい治療を始めないことはできても、している治療を畳むことは、医者も人の子なのでなかなか難しいんですよね。堀川さんが透析を止めたいと言ったときに、医師が反対したのも、心情的にはわかります。
堀川 そう、先生方も一生懸命透析をまわそうとしてくれたんですよね。透析の場合、止めたら一気にドンッと墜落し、尿毒症もひどくなって、ゆるやかに閉じていくことはできないですから。
松永 それでも、止めようとしなくても透析をまわせなくなるときはやってくる。徳島県の亀井病院の濱尾巧先生が、何科でも、ドクターなら誰でも緩和ケアはできないといけないとおっしゃっていましたが、全く同感です。医者の必要要件の一つは緩和ケアだと思っています。人はいずれ必ず死にますし、医療の原点は痛みを取ることですから。痛みを取れない医者は医者ではないと思います。
ではどうして林さんに痛みのケアができなかったのかというと、一番の理由はやはり主治医がいなかったことです。
小児医療では一人の患者に対して、トータルケアを行います。ほかの専門医に助けを求めることはあっても、主治医はあくまで自分です。僕がこの子を最後まで看るという意思をもって務めます。でも成人医療では泌尿器の先生は泌尿器しか見ないし、消化器内科の先生は肝臓しか見ない。臓器別に分かれているんです。それでも主治医がいれば、自分にその技術がないまでも、緩和ケア医に繫ぐなりできるのですが、林さんは二〇一四年に主治医がいなくなってしまった。
緩和ケアでは、痛み止めが効かなくなってくると最後は、持続的な深い鎮静に移り、ミダゾラムという薬で眠らせることになります。眠っている患者が痛くないかどうかは、また議論が別になりますが。
小児科でも最初はPCAポンプでフェンタニルを投与して痛みを取りますが、それが効かなくなり、子どもがのけぞるように泣いたりすると、親は見ていられない。そうなると保護者に説明をして、ミダゾラムを持続投与する。眠ってしまうともう目覚めないので、それと安楽死のどこが違うのかと問われたら、うまく答えられません。でもなぜその処置ができるかと言えば、保護者と僕との間に一年、二年とつきあってきた関係性があるからです。主治医としてこの子の一生は僕が看ますと約束しているからなんです。
でも林さんと、日赤病院の肝胆膵外科の先生とは信頼関係が築かれていないので、持続的な鎮静をした後で揉めたら困るなど、いろいろ考えてしまったのでしょう。緩和ケアには信頼できる主治医が必須なんです。
堀川 たとえ保険点数に加算されなくても、腎不全や透析患者の緩和ケアをする先生もわずかながらいます。でも医者と患者の間に、人と人との関係性がなければ、その最後に尊厳を守ることができるような、医療は成り立たないということですね。医師は忙しいですし。
■たった二・九%、腹膜透析という希望
松永 堀川さんの取材は、腎不全の患者さんに、如何に緩和ケアをすべきかという議論では終わりません。「腹膜透析という選択肢」という章題を見た瞬間、ああこれだと膝を叩きました。
その腹膜透析(PD)は、日本ではたった二・九%しか行われていない。これにはいろいろ理由があると思いますが、堀川さんはその一つに、医療経済の問題があると分析します。血液透析のベッドを埋める、という病院の動機が働いているということですね。
それもそうだと思うのですが、僕は一番の理由は、ノウハウがないことだと思います。医者は先輩から実地で教わる、大工や職人と似た社会構造なんです。日本ではたぶん透析が未開拓だった時代から、先人が失敗しながら血液透析をまわし始め、だんだんうまくいくようになって、先輩から後輩にそのスキルが伝わり、全国に広がるようになったと思います。
現在多くの医者に腹膜透析PDの経験がないため、そのやり方がわからない。古い知識では、お腹に透析のための管が直接刺さっているので、そこから感染して腹膜炎になると言われていました。
堀川 私たちにとっても、腹膜透析は時代遅れの医療というイメージでした。鹿児島の腹膜透析医療も、実際に見るまでは疑っていました。ところが実際には、一部の地域で驚くような効果をあげている。臨終の場で普通は、先生と遺族が記念写真なんて撮りませんよね。それも皆が笑顔なんです。自分たちの場合と比べて、本当に驚きしかありませんでした。東京は医療の過疎地だと思いました。
松永 3・11でも透析難民が溢れましたよね。電気もですが、一回の透析を回すのに、ドラム缶一個分以上の水が必要です。その水を浄化して透析液と混ぜて、ダイアライザーにかけるという工程がいる。当時、北海道に患者さんが搬送されたとは知りませんでした。
堀川 はい、自衛隊機で。でもその間に、他の地域では、結構な人数が亡くなっています。
松永 そこで東北医科薬科大学病院が地域医療を充実させる目的の下、医学部を新設し、腎臓内分泌内科の森建文先生が腹膜透析PDを広めようと動き出す。この地域の在宅での腹膜透析PDを、大学病院と同じレベルにする、対象は「高齢者」、現場は「家」だと。
世の中には教授になることが人生のゴールという考えの医者が多い中、こんな立派な教授はなかなかいません。
この地域の患者は自分が守る、故郷に恩返しをしたいと。医療って本来はこういうものだと思うんです。腹膜透析PDに取り組む先生たちは、どの先生も本当に立派ですよね。
堀川 患者の生活に踏み込まざるを得ない医療だということもあるのでしょう。患者にとって何が大切かを考える、そういう思考の人なら続けられるのだと思います。
今回たまたまかもしれませんが、取材した医療従事者に、家族に透析患者がいた方が多かった。あのときどうすればよかったのか、反芻しながら私がこの本を書いたのと同じように、医療現場で、患者の終末期を腹膜透析PDで支えようと、模索し続けておられる方々に出会いました。
松永 いわき市かしま病院の中野広文先生は、「PDファースト」――まだ尿が出せているうちから腹膜透析PDを始めると。でも腎機能が廃絶したら血液透析HDに移る。一般にはそこでまわせなくなって透析が終わることが多いけれど、さらに「PDラスト」で、再び腹膜透析PDに戻し、終末期は自宅で過ごす。PDラストなら、緩和ケアがいらなくなるという、これは画期的な発見でしたね。
堀川 緩和ケアの現場にいる方は、正直PDには食いついてこないんです。
松永 なるほど。医者って守備範囲が狭いんです。緩和ケア医は緩和ケアのことしか考えていない。PDで解決しようと思わない。
そして、自由が丘の柴垣医院との再会は皮肉でしたね……。
堀川 そうなんです。再透析のクリニックを探したとき、夫と二人で病院の下まで行ったのに。道路が狭くて車での送迎が難しいから、ここは止めておこうと。彼の死後、学会で柴垣の在宅医療者たちがよく発言をしていて、柴垣って聞いたことがある名前だな、と思っていたんです。取材でお話を聞いたら、腹膜透析PDをやっていますと。この事実に直面したときは、言葉がありませんでした……。PDが適用されたかは分かりませんが、あのときなぜ……たられば、ですね。
松永 そして堀川さんは、現在は川原腎・泌尿器科クリニックにいる松本秀一朗先生の「鹿児島モデル」に辿り着く。医療IoT(医療専門の情報通信システム)で、情報を共有しながら、地域医療をPDで支えるという。
堀川 透析学会で、松本先生も登壇されシンポジウムが行われましたが、その間も先生たちは手元のスマホで患者さんの対応を行っていました。東京でシンポジウムに参加しながら、鹿児島での診察に応答する。東京にいても、議論をしている間も、ケアの質は落ちませんと。
在宅介護の看護師やヘルパーを派遣する施設を運営するあおぞらケアグループの方がおっしゃったことですが、PDとはもともと在宅で患者さん自身や家族がするシンプルな医療だと。医療者が少し寄り添えば実現できるのに、国内外から視察に来ては口を揃えてすごいですねと言うばかりで、手間をかけようとしない、本気で始めようとしていないと。
松永 なるほど。
透析患者の立山かすみさんを看取るシーンは感動的でした。死の前日に五七九㏄を除水して、最後まで尿毒症に苦しむことなくおだやかに逝かれた。
堀川 在宅診療医も、初めてPDが緩和ケアの手段として使える現場を見て驚いたそうです。臨終の場でご遺族に、勉強になりましたと頭を下げられたとか。
■この本から医療制度を変える
松永 本当に、堀川さんが腹膜透析PDに辿り着けてよかった。堀川さんは林さんを失って、医療にズタズタにされ、ものすごく傷ついただろうと思うんです。この本の第二部はある意味で、堀川さん自身のグリーフケアになっている。もちろん医療に対する問題提起でありながら、堀川さんが生き直すための本でもあると読みました。
堀川 林のような終末期を迎える透析患者さんを一人でも少なくしたい。そういう思いで書き始めたのですが、結果としてそうなったかもしれません。
松永 最後に「悲しみが癒えるということと、記憶が薄れていくのは少し違う気がする。そのときは永遠のお別れだと思った。だが亡き人は、記憶の中に生き続けている。独りでは抱えきれぬ苦しみを、ともに背負って生き抜いた日々は、いつかきっと残された人の人生に力を与えてくれる――」とあります。いい言葉ですね。僕も多くの死と、そこから立ち上がっていくご家族を見てきました。僕は亡くなった子どもの親とのお付き合いは、今でも続けているんです。
堀川 あぁそれこそグリーフケアですよね。
松永 日本の医者の数は三四万人です。日本の医者が全員読むべき本だと思う。
堀川 私は医療に絶望したけれど、今を生きて、今透析をしている患者さんのための環境を整えるには、医療現場の皆さんの協力が必要です。私は医学界に抗議するとか、敵対するような気持ちはありません。どうしたらよりよい医療環境を共に作ってもらえるのか、それを考える材料として使ってほしいと、そういう気持ちで、この本を書きました。
松永 ノンフィクションに大事なことは三つあると思っています。まずは面白いことです。面白い本を書くためには文章力がなくてはならない。堀川さんの文章は読み始めたら止まらない面白さです。
それから、ノンフィクションでは、人が知らない世界を提示する必要がある。透析の末期の患者の苦しみは、今まで誰も書いたことがなかったので、この要件も成功しています。
そして三つ目が一番大事で、読んだ人に価値観の変容をもたらしたり、考えや行動を変えさせること。小説とノンフィクションの一番の違いはここだと思うのです。二〇二四年下期に芥川賞を取った「バリ山行」はものすごく面白かったけど、堀川さんのこの本には、面白いだけでなく世の中を変える力がある。
堀川 この本はスタートに過ぎなくて、これから腎不全患者の終末期の緩和ケアを支えるための診療報酬制度を構築しなくてはならないと考えています。この本は、それを実現するためのツールなんです。
医療制度が整ったからといって全てが変わるわけではないけれど、少なくとも現場で終末期の患者さんの対応に困っている泌尿器科医や透析医が、緩和ケア科に相談に行けば応じてもらえて、経営に資する業務として成立する、そういう環境を整えなければならない。属人的な力だけに頼っていてはいけないと思います。まだ詳細は公表できませんが、この本を読んでくださった腎臓病患者の団体や、学会などで、建設的な動きが起こりつつあります。その先を見届けるまでは、書き終えた気分にはなれません。今おっしゃっていただいた三つ目の作業が、これから始まると思っています。医療制度を変えることに全力を尽くします。(おわり)