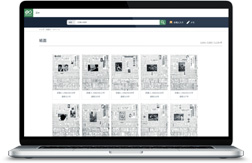お知らせ
【読書人WEB特別編】成田龍一・吉見俊哉対談 ~色川大吉と見田宗介―60年代後半の知的状況をめぐって~
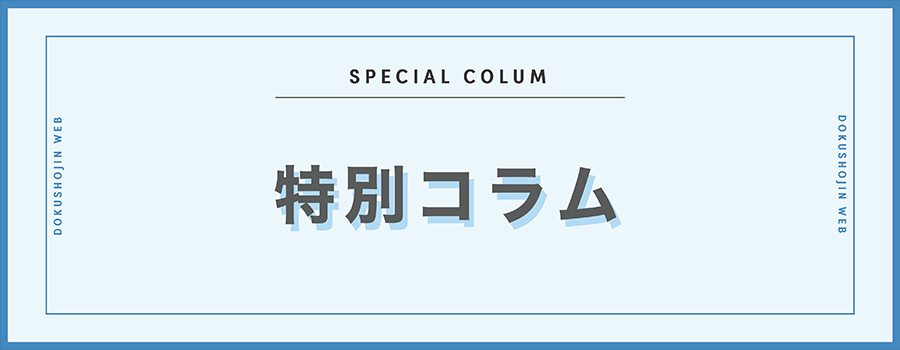
※週刊読書人2025年5月2日〔4月25日合併〕号巻頭特集「昭和100年、戦後80年」対談特別編※
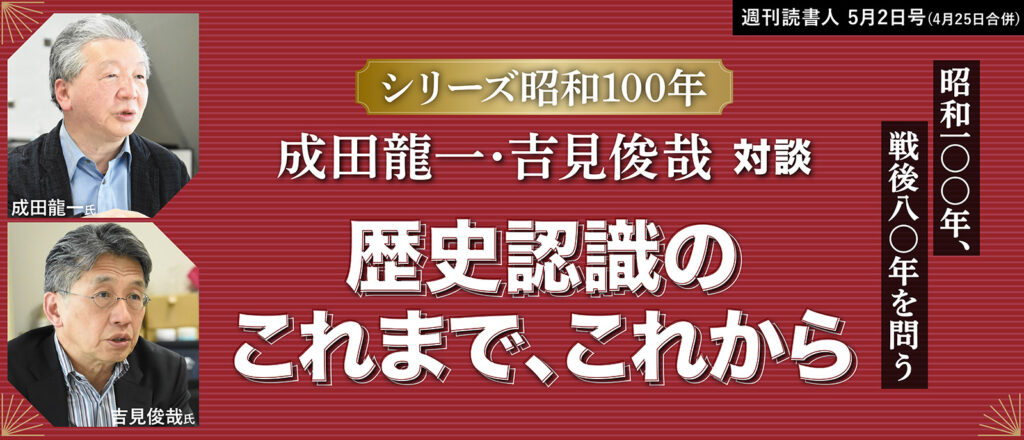
2025年5月2日〔4月25日合併〕号の巻頭特集、成田龍一・吉見俊哉対談「歴史認識の認識のこれまで、これから ―昭和100年、戦後80年を問う―」において、1968年の「明治百年」問題(本紙2面)から、色川大吉と見田宗介の両者を軸に議論が発展した。民衆史から出発した成田氏と見田宗介から薫陶を受けた吉見氏による〈見田宗介論〉でもあり、歴史学と社会学の重なりとズレを確認したうえで、歴史認識のこれからを見据える対話となった対談の一部を、特別編として読書人WEBに掲載する。(編集部)
※本紙と併せてお楽しみください
読書人WEB特別編
■色川大吉と民衆史研究/見田宗介と社会心理学
成田 1968年(昭和43年)、政府が推し進める「明治百年祭」に対して、歴史学界が総力を挙げて反対するという「明治百年」批判の動きがありました。この「明治百年」問題に参加し、歴史学研究の方法や認識を鍛え上げたひとりが色川大吉さんです。色川さんは、60年安保を契機に「民衆史研究」を紡ぎだしますが、「68年」に直面することにより、さらに民衆史研究を鍛え上げていきます。色川さんは政府が作り出した「大きな物語」としての日本の近代化の成功譚に抗して、「民衆」の側からの百年は、決してそのようなものではなかった、と議論します。このときの歴史学の主流は、マルクス主義と実証主義を両輪とする「戦後歴史学」ですが、このころ民衆史研究も多くの人びと――とくに若者たちを惹き付けるようになります。
この色川さんの議論を見たとき、ほぼ同時代に発表された見田宗介さんの議論と重なるところがあるように見えます。「社会心理学」を掲げ、近代日本を対象とした考察群です。

念頭においているのは、「近代化日本の精神構造」「明治維新の社会心理学」(1965年)、「文明開化の社会心理学」、「「立身出世主義」の構造」(67年)、「明治体制の価値体系と信念体系」(72年)、あるいは「解説 恋愛・結婚・家庭の思想史」(☆『近代日本の名著 14』、66年。見田瑛子と共著)、「総論 自由民権運動を支えた人たち」(☆『明治の群像 5』、68年)といった作品です。これらは一冊にまとめられなかったので、なかなか見田さんの大きな柱として考えられていないようですが、『定本 見田宗介著作集』の中に一冊に収められて(☆を除き)、あらためて1960年代半ばからの見田さんの問題意識に接することができるようになりました。歴史学における「明治百年」批判に重なりあうような時期の論稿です。すでに「現代日本」に直接向き合う議論――方法論や資料論を公表していましたが、歴史的な考察も行っていたということです。
二つの軸足によっていた見田さんですが、歴史学をやるか、社会学をやるかという選択肢が自分の中にあったということも言われています。大澤真幸さんとの対談でも「68年くらいまでは、ずっと日本近代の民衆精神史をやろうと思っていたのです」といい、その流れで、柳田国男『明治大正史 世相篇』や石牟礼道子『西南役伝説』に言及しています(対談「連山縦走」『<わたし>と<みんな>の社会学』2017年)。
この点に着目したとき、1960年代の半ばから終わり頃にかけて、歴史学においても社会学においても「民衆」という主題が登場しており、そして政府の主導する「明治百年祭」とは異なる、人々のリアリティを伴う意識や心情、思想や行動からの歴史像を追及する動きが見えてきます。
■戦後の知的状況、社会科学のアメリカナイゼーション
吉見 社会心理学という言葉について言えば、見田先生が社会心理学という言葉を使ったのは、1950年代から60年代の初頭にかけての時期だけのように思います。ある時期から社会心理学という言葉ではなく、「精神構造」とか「心情と論理」とかを使っていき、むしろ60年代以降は「社会意識」という言葉で考えていた。ですから私たち見田宗介に教えを受けた者たちの感覚では、これは社会意識論の問題なのですね。この「社会意識」という概念を社会学に導入したのは城戸浩太郎ですね。彼は50年代半ばに社会意識論を展開していて、見田先生よりも少し早い。というか、見田先生が社会意識という言葉を使うようになるのは城戸を受けていたと思います。
では、なぜ社会心理学を使わなくなったのか。他方で、なぜ初期には社会心理学という言葉を使っていたのかという二つの問いが出てきます。なぜ使わなくなったのかというと、これは戦後日本の社会科学のアメリカナイゼーションの結果だと思います。歴史学ではアメリカの影響は相対的には少なかったかもしれない。でも、歴史学や哲学以外の日本の戦後の主だった社会科学は、基本的にアメリカナイゼーションの圧倒的な影響を受けた。つまり、アメリカ的な概念や視座を受け入れて、それによって標準化されていくプロセスが多くの社会科学の分野で進行した。そうしたときにアメリカナイゼーションの中身をどう受け止めるのかということについて、戦後初期の知識人と60年代半ば以降に知的な形成を遂げた人々の間では構造的、質的な差があったと思います。

つまり、初期にアメリカの社会心理学を受け止めていった知識人として、まず誰よりも清水幾太郎さんがいますね。清水さんの社会心理学は、その後の60~70年代以降の人たちが使っていく社会心理学という言葉と随分違っていて、もともと『流言蜚語』をお書きになられた方ですから、彼の問題意識の中でアメリカの社会科学を受け止めていた。それからもう一人は南博さんで、南さんの社会心理学もこれは思想の科学研究会と深く関わっていて、アメリカのプラグマティズムを学んだ鶴見俊輔さん的なところがあった。清水さんも南さんも、アメリカの主流の社会心理学とは違う意識で社会心理という言葉を当時は使っていたと僕は理解しています。
そうした際、アメリカの何人かの社会心理学者の仕事がとてもインフルエンシャルだった。最も有名なのは、エーリッヒ・フロムです。フロムが『自由からの逃走』で書いたこと、その向こうにはフランクルト学派がいたわけで、フランクフルト学派がやっていたようなことが社会学であり、社会心理学であるという感覚が戦後日本の社会学者たちの中にあった気がする。
その際、なぜ社会心理学という言葉を使ったのかというと、もう一方にはマルクス主義の影響がありました。マルクス主義的な文脈で言えば、これはイデオロギーの話なんです。ですから戸坂潤ならば、同じ問題をイデオロギーと呼んだでしょう。しかし、清水さんにも南さんにも、それでは掬いきれない次元があると思われた。それで、イデオロギーとは呼ばずに、社会心理という問いを立てる。つまり、構造的に規定されながらも、そこにいる人々の心の蠢きとか、感情の発露とか、イデオロギーという概念では捉えられない次元を考えようとした。だから、これはむしろアナール派なりカルチュラル・スタディーズが考えていくような心性とか感情とか心情とか、そういうレベルで人々の集合的な心の動きを捉えようという問題意識が、清水さんにも南さんにも、見田先生にもあったのではないかと思います。ですからある時期までは、そのような領域を捉える言葉として、社会心理という言葉は適切なように思われたのです。
つまり、そこで考えられていた「社会心理」は、その後に一般化していくいわゆる社会心理、「社会的な心理(ソーシャル・サイコロジー)」ではないのです。そうではなくて、目指されていたのは、「社会の心理(サイコロジー・オブ・ソサエティ)」なんですね。
ところが60年代半ば以降、社会心理学という言葉は使われなくなっていく。なぜなら、大きな制度的な流れとして、アメリカのオーソドックスな社会心理学が入ってきて、これは要するに社会化された個人の心理学です。社会心理という言葉の理解としてそちらが主流になっていった。そのことがはっきりわかってくると、社会心理という言葉の魅力は一気に薄れていき、そうではない言葉、社会意識とか精神構造といった言葉が重視されるようになったのだと思います。
■民衆意識と社会心理/データに還元されないものの価値
成田 見田さんの学問的枠づけ――学問的自己規定が、学的広がり、戦後の同時代の知的状況からよく分かりました。周知のことですが、「近代日本」を考察対象とする総まとめのような『近代日本の心情の歴史』(講談社、1967年)も、副題を「流行歌の社会心理史」としています。「社会心理学」の立場を維持しているのですね。もっとも、同書が文庫化されるときに付された「学術文庫版のためのあとがき」(1978年)では「今のぼくならば(このような副題には―註)しないだろう」としています。加えて、この本では1960年代半ばまでの流行歌が分析されており「現代日本」にまで踏み込んでいます。見田さんの出発にあたり、「社会心理学」という学問的規定、「近代日本」という対象設定は、微妙なゆれを含んでいたように見えます。
そのうえで、「明治百年」問題を間に挟むとき、1960年代後半の時期の知的状況――学問的状況は、「歴史」に向かうとともに「民衆」に視点を寄せていたということです。今回の「昭和100年」と対比したとき、一つの接点が見えてくるように思うのです。
吉見 見田先生は、かなり初期に「現代における不幸の諸類型」を書かれたように、近代社会を生きる集合体としての人々の幸福とは何か、不幸とは何か、欲望とは何か、そして夢はどのように破れていくのかということに非常に関心があって、それこそが心情の問題であったりするわけです。そうした問題系列で、見田先生は代表的な論文「新しい望郷の歌」や「まなざしの地獄」においていわば社会心理の構造分析をしていくわけです。だから見田先生的に言えば、初期に考えていたような社会心理学的なアプローチをずっとしていて、まったくぶれていないのです。
成田 この時期からしばらく、見田さんは「幸福」「不幸」あるいは「孤独」などと「民衆の心情」を範疇化し、それを「価値意識」という方法的座標、また「流行歌」や「身の上相談」といった資料と結びつけ、緻密な分析を行っています。現状に軸足を置きながら、近代日本の出発時にも目を配り、ひろく歴史的な射程での考察を提供しており、(公表時期からは、やや遅れながらでしたが)夢中になって読みました。この営みが、歴史学の領域における「民衆思想」――民衆意識を軸とした歴史像と接点を有していることを、強く感じていました。これは私にとっては、「民衆史研究」の分析方法と対象資料の選択・抽出にかかわる議論となりました。

いまさら言うまでもないことですが、「民衆史研究」も色川さんは北村透谷と自由民権運動との問題意識から出発し、民衆運動史を色濃く投影しています。民衆運動の敗北に伴う心情のありようが探求されました。資料もしたがって、自由民権運動に参加した「豪農」の残したものを、子孫の維持していた土蔵を一つひとつ開けて探し出すという手法となります。その資料を読み解くのですから、どうしても政治思想、社会思想に傾きます。見田さんが分析される社会心理との差異が目につきました。
吉見 ただ、社会心理学という言葉の理解が、アメリカの主流の社会心理学とは根本的に違ったわけで、ここにはアメリカ的な社会科学のパラダイムと戦後日本の知のパラダイムの違いが伏在していると思います。
成田 そうした学知の背景は、いまのいままで知りませんでした。不明を恥じますが、(さきに述べたように)民衆の心情の解析にあたり、問題意識に伴う方法と資料の検討、その明晰さに魅せられました。歴史学においては、ひたすら歩いて資料を探索するという、言ってみれば素朴なやり方でした。ただ、それは歴史学研究なりの蓄積と知見に基づくもので、色川さんも決して偶然に資料を見出したわけではありません。豪農という地域の有力者の土蔵を開けるという手法は、江戸時代(=近世史)研究のやり方を踏襲したものです。
このように、初発の問題意識を同じくしながら、その展開の過程で学知の方法的差異をみせるという点に関心を有しました。そのときに見田さんの方法をめぐって、思ったことが二つあります。一つは、方法から資料を導き出すこと。そのときに二つめとして、見田さんは新聞を選択した、ということです。数量的データ、質的データというデータの論点をいい、近代日本の場合、前者のデータが歴史的に整備されておらず、新聞記事を使うとして、新聞を分析していきます。
吉見 新聞は質的データです。基本的にアメリカの社会学や心理学は圧倒的に量的データ主義で、数量分析主義です。今も社会科学はほとんどそれで占領されている。だからその社会科学における量的分析、統計処理という大きな流れがある中で、それを完全に拒否するわけではないけれども、文書やオーラルヒストリーのような語りがある。科学主義的なデータ分析がどんどん広がっていく20世紀あるいは21世紀の学問世界で、そういう量に還元されない、というか還元してはいけないものの中に見えてくる世界、価値を語る、分析するということの学問的価値をどういうふうに守るか。それが、社会学をどう作るかということでもあったと思います。
■両者のズレと重なりを出発点に

成田 歴史学において、「戦後歴史学」の中心であった経済史では量的分析が重視されますが、大づかみに言えば質的分析がなされます。ここでも二つのことを述べてみます。第一は、質的な分析を大切にする民衆史研究においても、新聞は資料としてこなかったことです。今でこそ、新聞資料は重視されていますが、60年代においては「二次資料」という言い方で、「論説」は取りあげられるものの、民衆の心性に関しては補助的に利用される程度でした。
第二には、「戦後歴史学」は「科学的」たらんと社会科学を志向し、法則性を追求していたことです。歴史学の方法といえば、もっぱらマルクス主義で、「方法」と「資料」はこの時点においては別個に議論されていました。そのため「戦後歴史学」に距離を取る「民衆史研究」も資料に工夫を凝らし、地域の資料を博捜することによって、質的な関心を追及したのです。
吉見さんが強調されるように、見田さんはアメリカの社会学や心理学に目を配っていたでしょう。私の関心は、見田さんの「問題意識」―「方法」―「資料」が一体となり、歴史的分析にもそのことが貫かれていたことです。方法とデータの結びつきを見田さんは別途遂行していますが、マルクス主義に一元化している歴史学との差異をいつも思っていました。
吉見 見田先生が質的データにこだわったのは1950年代から60年代にかけてで、量的データだけでは見えてこないものに興味があったのだと思います。
成田 見田さんには軸足が二つあって、現在の問題を考えると同時に、(60年代においては)明治維新期――近代日本の出発を問題にするというスタンスですね。歴史学も当然ことながら現在の課題から出発しているのですが、それを記すのは、限られた歴史家がエッセイとして書くのがほとんどです。それに対し、見田さんは双方を公表しているということです。先に述べた、方法と資料の必然性も、こうした姿勢に結びついているでしょう。
吉見 そこは少し成田さんと理解が違うかもしれません。見田先生は明治期のものもやって、それはある時期いろいろな成果を出しましたけれども、根本的には、近代の出発点として見田先生が考えていたのは、かなり初期からユダヤ・キリスト教です。たぶん2000年ぐらいの単位で近代を考えていたから、その一局面に1860年代からのこともあるけれども、しかし問題の根本は、総体としての近代にあった。
例えば、『現代日本の精神構造』(1963年)に、「死者との対話─日本文化の前提とその可能性」という論文を書いていて、この中に「シツォイド文化とチクロイド文化」という議論があります。ヘレニズム系の文化とヘブライズム系の文化というものは時間意識が違うということを言っていて、要するに直線的なユダヤ・キリスト教的な世界像を問題にしていた。こういう問題意識は文化人類学的な問題意識で、70年代に近づけば近づくほど見田先生の中でそこが拡大していく。ですから、『時間の比較社会学』の前に『気流の鳴る音』があるのです。
■歴史学と社会学/その入り口と出口
成田 なるほど、そのこと自体はよく分かります。たしかに日本近代の考察のときにも、「近代」を参照系としています。ただ、この吉見さんとの「対話」では、見田さんが、60年代に「日本近代」を主要な分析対象としていることの意味を考えたいのですね。
少し「問い」の立て方を変えてみましょう。見田さんは論稿を公表したあと、単行本に入れ、論文集としてのまとまりをつくります。そうした営みは、後に著作集においては、「現代社会」/「現代化日本」と「近代化日本」/「近代日本」として再整理され、まとめられていきます。ふたつの対象――「近代」「現代」をみすえ、「近代日本化日本の精神構造」(著作集Ⅲのタイトル)の研究をされたことの意味はどこにあると、吉見さんは考えられますか。
先ほどの二つの時間の流れの考察でも、「死者との対話」はアジア・太平洋戦争での死者に対する意識を問題としており、見田さんは絶えず目の前の出来事を取り上げ、比較の軸として別種の参照系を吟味しているのではないでしょうか。
吉見 入り口はそうなんです。でも出口は違う。見田先生の場合は入り口が目の前の現実なんだけど、そこから出ていく向こうにあるのは多分2000年から3000年ぐらいの単位で、地球に起こってきた文明史を見ていた気がします。
成田 たしかに「日本近代」の考察に際し、本来的なという言葉こそ使わないけども、「近代」を想念して、日本の近代を相対化しています。さらに『時間の比較社会学』や『現代社会の理論』など、ある時期以降の作品には、その大きな射程での「出口」の時期が明示されています。ただ対象としている60年代の認識はどうであったか、ということです。繰り返しになりますが、60年代後半の「明治百年」問題の状況を、見田さんも共有していたであろうということです。
吉見 入り口は民衆史の色川さんとも重なる。ところが社会学者が行く出口と、歴史家が行く出口は必ずしも同じではないかもしれません。
成田 その問題なのですね。結果として歴史学者と社会学者というかたちで振り分けることができますが、なぜ出口が異なるのか。このことを、その時点での歴史学の方法との比較で考えたいということになります。
■柳田國男の読みの違い
成田 具体的に、一つの例を述べてみます。高度経済成長のなかで、歴史学を含む学知は大きな試練を受けます。このとき、色川さんは可能性を模索して、柳田國男に向き合います。見田さんも、柳田を論じますね。ただ、見田さんと色川さんでは、柳田の読み方が全然違っています。
同じように民衆の心性、見田さんでは民衆の不幸や幸福にまで立ち入らなければ民衆史のリアリティはないと考え、柳田に接近します。しかし、二人とも『明治大正史 世相篇』に着目しながら、読みが違うのです。
吉見 色川さんの読みというのは、どういうものなのでしょうか。
成田 色川さんは、柳田國男の『明治大正史 世相篇』に二つの点から接近します。一つは『明治大正史 世相篇』が、柳田國男の著作中でどのような時期に、どのようなかたちで生み出されたのかという点。二つ目は、1920年代から30年代初頭の激変期に生み出されてきていることの意味の確認です。同じように、民衆のリアリティを探究し柳田に赴きながら、見田さんが叙述の作法に着目するのに対し、色川さんは現象の広がりを言い、ふたりの意味合いはかなり異なります。
色川さんは、柳田に倣い、その名も『昭和史 世相篇』と銘打った著作を1994年に刊行します。「儀礼」に着目し、衣食住の変化をたどり、「ふるさと」観の推移をたどります。「都市空間のフォークロア」とあわせ、「犯罪」を「群衆の欲望」とし、さらに「民衆運動」「天皇」のフォークロアなども探ります。色川さんならではの工夫がみられるのですが、残念なことに現象の並列にとどまっています。加えて歴史家らしく、「軍事大国の時代」「転換期」「経済大国の時代」と時期区分を行い、「民衆意識の深層」を探ろうとしています。色川さんの柳田を介しての踏みだしは、未発に終わったといわざるを得ないと思います。
■見田宗介と真木悠介/パラダイムチェンジ
吉見 見田先生について言えば、60年代前半までと60年代末以降である種のパラダイムチェンジが起こっていると思います。それはどういうことかというと、直接的には東大紛争との直面が契機として大きいと思います。その瞬間に、真木悠介の名前が生まれ、それ以前の社会学者・見田宗介とそれ以降の思想家・真木悠介の間である種のパラダイム転換が起きている。
そして、真木悠介としての本格的な仕事は『気流の鳴る音』で、そこで大きかったのは文化人類学の影響です。つまり、歴史学的なパラダイムから、むしろ構造主義、ポスト構造主義的な人類学的なパラダイムに大きく移行していったのだと思います。60年代末あたりから見田先生はレヴィ=ストロース、カルロス・カスタネダ、エドマンド・リーチらの文化人類学的著作を本格的に読んでいます。そして60年代から70年代にかけて文化人類学が切り拓いてくれた地平の中で、日本の近代史の問題も、それから日本そのものの問題も捉え返している。
そこから先の仕事は、かなり連続的で、私たちはこの時期の見田先生に圧倒的な影響を受けてきました。ただ、見田先生にとって、それ以前からの社会学的な理論の地平で何が大きかったかというと、やはりマルクス主義だと思います。あの当時は、一方の廣松渉さんの仕事と他方の見田宗介先生の仕事が、東大駒場のマルクス主義理解の双璧でした。廣松さんの議論はちょっと私には抽象的すぎたので、見田先生の存立構造論のほうに影響を受けていた。ですから、先ほど話した社会心理学的な部分と、マルクス主義の存立構造論的なパラダイムと、さらに『気流の鳴る音』以降の人類学的な地平が、1960年代から70年代にかけての見田先生の仕事には統合されていた。
真木悠介の『気流の鳴る音』から『時間の比較社会学』へ、そして『自我の起源』へと行く流れの中で、見田先生の仕事は近代を徹底的に相対化していく。これは、フランスの構造主義やポスト構造主義的なパラダイムとどう関係していたのか。近代日本の現実、あるいは社会意識の中で、構造主義と同じような問題を考えるとしたら、どういう社会学的アプローチがあり得たのかを見田先生は極限まで考えられ、われわれはそれに追随してきたのだと思います。
成田 見田さんのパラダイムチェンジは、私も同意するところです。見田さんによる柳田論の執筆も、パラダイムチェンジ後の仕事です。
このとき、なぜ見田さんをめぐる議論を持ち出すかというと、六〇年代後半の課題として、高度経済成長の考察があったとの認識からです。別言すると、高度経済成長の「戦後歴史学」の一番大きな失敗は、高度経済成長が説明できなかったということにあると考えるからです。
「戦後歴史学」は高度経済成長に批判的に向き合いました。高度経済成長を寿ぎ、ここに行きついた「近代日本」百年の歴史をまるごと評価する、政府の物語への批判と重なりあっています。ただ、それでは民衆の心性にみあう歴史意識とはならないでしょう。そこに踏み込もうとした色川さんの試みも不発であるとき、どのような高度経済成長の解析が可能か。そのひとつの解を、見田さんが提供しているように思うためです。
そのような流れでいったとき、「理想の時代」/「夢の時代」/「虚構の時代」という、見田さんの戦後史の時期区分は、どのように位置づくでしょうか。
吉見 決定的なターニングポイントがどこかというと、夢の時代から虚構の時代への転換ですね。つまり、理想の時代から夢の時代への転換というのは、理想がもう実現不可能となって、それでも夢を追い続けるという流れだったのが、虚構でいいじゃないかという、そういうフェーズになっていく。消費社会的なリアリティがわれわれの身体に深く入り込んでしまう状況です。だから、夢の時代から虚構の時代への転換は、構造的には大きい。それは日本において消費社会が完成したことを示すのです。それが起こるのが、1970年代から80年代にかけてです。
現状認識はその通りなのですが、でも問いはそこにはない。この図式は分かりやすいから、人口に膾炙するのだけれども、見田先生の問いとしてより重要なのは、その虚構化した世界の中でどのように、虚構を超える意識が生まれてくるのかが重要で、時代の三区分という図式自体は分かりやすいけれども、見田先生の本領ではないと思っています。
■戦後歴史学の失墜/高度経済成長との向き合い方
成田 高度経済成長を軸とした、狭い意味での戦後史の時期区分だということですね。しかし、私からすると「戦後歴史学」の失速が始まり、色川さんでさえ踏みこめなかった高度経済成長の民衆の心性の解析において、見田さんの3つのフェーズの説明はシャープに見えます。高度経済成長を折り込んだ歴史認識の考察という意味合いです。
吉見 見田先生のお仕事で、高度経済成長期の問題を真正面から捉えたのは、今、話に出た三区分ではないと思います。そうではなくて、論文で言えば「新しい望郷の歌」、それからその先の状況を捉えたのが「まなざしの地獄」です。「まなざしの地獄」は高度成長社会論です。見田先生がそこで何を語ったかというと、それは東京に出てきた若者たちの欲望の問題で、つまり欲望の社会学です。その欲望は、単に物質的な欲望ではなく、他者から見られる対他的な存在として人間があって、どう見られたいかとどう社会は見るかという、そこのズレですね。ですから、永山則夫を見田さんは一つの典型的な質的データとして扱っています。その事例を分析しながら、高度成長期に無数の若者たちに起こった欲望の問題を社会とのズレの中で捉えた見事な仕事です。
成田 そのこと自体は、吉見さんのいう通りでしょう。近代化の人間類型に着目し、その中での「不幸」や「幸福」の心情を分析する見田さんが、高度経済成長という事態のなかで、新しい人間類型に向き合って描きだす具体的なモノグラフィーの提供の時期がありました。歌謡曲の分析として心情の歴史をたどったあと(この解析は、高度経済成長による心性の変化が見越されていました)、その後の高度経済成長の時代を考察する論稿は、たしかに「まなざしの地獄」でしょう。
しかし、この論稿を含みこみ、高度経済成長の時期を大観し分節する3つの時代区分を出された。このことは、高度経済成長期における変化の歴史的意味を探っており、その試論であったということです。
吉見 私の理解では三区分よりも重要なのは、見田先生の『現代社会はどこに向かうか』(岩波新書、2018年)で、地球は有限で、有限な環境下ではすべての成長は必ず飽和点に達するロジスティック曲線を描く。人口も生産もすべてこの構造の中で限界点に達するわけだから近代化も必ず終わるということを示された。その終わりが、どういうかたちで見え始めるかというマクロな分析をしておられる。これはとても重要なお仕事で、見田先生は、マクロに近代あるいは現代を捉えたときに、高度成長期以降という以上に近代以降を見据えていたのだと思います。
■プロセスから読み解く歴史家と到達点から思考する社会学者
成田 繰り返すことになりますが、そのこと自体はその通りでしょう。しかし、見田さんにもプロセス――家庭的な進行があると思うのです。見田さんの60年代、見田さんの70年代、見田さんの80年代、それぞれの時期に、その都度の現在に向き合い、議論を提供していき、最後にはロジスティックス曲線を使って「人類社会」の説明をするに至りました。

このとき、なぜ見田さんをめぐる議論を持ち出すかというと、六〇年代後半の課題として、高度経済成長の考察があったとの認識からです。別言すると、高度経済成長の「戦後歴史学」の一番大きな失敗は、高度経済成長が説明できなかったということにあると考えるからです。
その差異を検討し、腑分けすることによって「見田宗介という営み」に接近していくというのが歴史家の作法ですね。そのことによって、色川さんとの比較も可能になると思っています
吉見 そうか、歴史家の説明なんですね。僕はやはり社会学者なのかな。
成田 歴史家はプロセスから考えますが、社会学者は行き着いた地点から思考の構造を考えるということですね。別言すると、私から見たときには、見田さんの仕事も歴史と格闘した痕跡であり、歴史的な位相を有しているということになります。色川さんも見田さんも、歴史的な拘束性があり、その点を見ていく必要があるということです。
吉見 歴史はここにあるわけで、しかも考えようとしている方向性も一致している。でも、歴史家がアプローチしようとするところと、社会学者がアプローチするところが違うわけですね。ですから、重なりとズレがある。
成田 やっぱり違いましたね。これだけ差があると思いませんでした。
吉見 見田先生の一番面白いと思うところが違うのです。
成田 あるいはその説明の仕方、そもそも接近の方法が違うということですね。「明治百年」をイデオロギーにかかわる論点から受け止めて、そのイデオロギーに対抗するためには、どのような学問的実践が有効であるかを考えたときに、見田さんと色川さんとの重なりとズレは戦争経験=世代以上に、学知の差異にありました。見田さんに薫陶を受けた吉見さんと、民衆史研究から出発した私が「戦後80年」の今ここで向き合っているのですが、私たちもまた、その差異を共有していることが明らかになりました。
(おわり)
★なりた・りゅういち=日本女子大学名誉教授。日本近現代史・都市社会史。著書に『近現代日本史との対話』(全2巻)『近現代日本史と歴史学』『シリーズ日本近現代史 大正デモクラシー』『歴史論集』(全3巻)、編著に『シリーズ歴史総合を学ぶ 世界史の考え方』『〈世界史〉をいかに語るか グローバル時代の歴史像』ほか多数。1951年生。
★よしみ・しゅんや=東京大学名誉教授、國學院大學教授。社会学・文化研究・メディア研究。著書に、『都市のドラマトゥルギー』『空爆論』『平成時代』『ポスト戦後社会』『アメリカ・イン・ジャパン』『東京裏返し』、近著に『このとき、夜のはずれで、サイレンが鳴った』(原広司共著)ほか多数。1957年生。