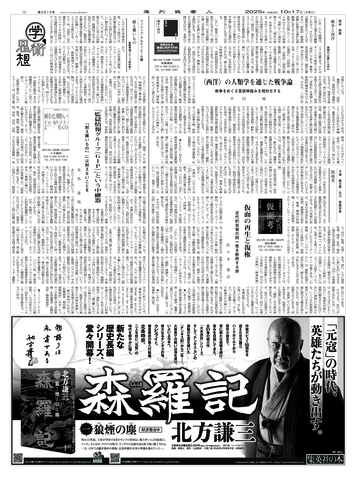- ジャンル:哲学・思想・宗教
- 著者/編者: フィリップ・アルティエール
- 評者: 美馬達哉
耐え難いもの
フィリップ・アルティエール編
美馬 達哉
一九六八年五月革命の後、フランス国内では、毛沢東主義を掲げるプロレタリア左派に対する厳しい弾圧が続いた。そして、一九七〇年には、投獄されていた多くの活動家が、普通囚ではなく政治囚としての待遇を要求するとともに、監獄内の劣悪な環境や蔓延する暴力に抗議し、ハンガーストライキを敢行する。一九七一年、当局が一定の譲歩を示したことで、このストライキは終結し、その過程は当時のマスメディアでも大きく報じられた。
この出来事の直後、ミシェル・フーコーと、そのパートナーであったダニエル・ドゥフェールを中心に、歴史家ピエール・ヴィダル=ナケや『エスプリ』元編集長ジャン=マリー・ドムナックらが加わり、「囚人自身が監獄の状況を語ることを可能にする」組織として、監獄情報グループ(GIP)が設立される。GIPの活動は、一九七二年末、囚人当事者やその周囲の人びとを中心とした「囚人行動委員会(CAP)」へと引き継がれ、短期間で幕を閉じた。その中心的成果とされるのは、囚人へのアンケートや調査結果をまとめたパンフレット『耐え難いもの』の刊行(全四号)である。
本書は、これらのパンフレットを中心に、いくつかの関連資料を集成したものである(続いての邦訳出版も予定されている)。このような一見マイナーな資料集が、あえて邦訳されたのには理由がある。GIPという経験は、フーコーの思想形成、とりわけ権力のミクロ物理学の構想と、一九七五年の『監獄の誕生』に至る理論的深化に大きな影響を与えたとされるからである。同じくGIPに参画していたジル・ドゥルーズは、「GIPは『監獄の誕生』までの実験室だった」と述べている(「フーコーと監獄」)。
『監獄の誕生』においてフーコーは、合法と違法を分割する裁判という法の言説的システムとは異なり、囚人の身体という物質性を直接扱う監獄において、個々人を監視・評価・分類して従わせる多様な制度がいかに歴史的に構築されてきたかを論じた。法哲学の発展とは区別される、具体的な処罰の実践の細部を注視する歴史的関心は、GIPの活動に関連するといえるだろう。そして、「耐え難きものは、裁判所、警官、病院、精神病院、学校、兵役、出版、テレビ、国家、そして何よりも監獄」というGIPのスローガンが示すように、フーコーの批判は、監獄から現代社会の総体へと広がっていく。
さらにGIPでの経験を通じてフーコーが明確化したのは、党中心の左翼的な社会運動の限界を超える地平、すなわち当事者性の尊重と知識人としての自己の否定、であった。そのために、GIPの刊行物は、囚人自身の言葉を「中継器」のようにそのまま掲載し、知識人は無署名で寄稿するという仕組みだった。後に、フーコーはこの態度を歴史研究にも適用し、一九七三年には、一九世紀フランス農村で母・妹・弟を殺害した青年の手記と資料を、そのままの形で出版する(『ピエール・リヴィエール』)。
またGIPにおいてフーコーは、知識人として被抑圧者を代弁するのではなく、個別的な闘争のために自らの専門知を用いる人びと――精神科医、ソーシャルワーカー、弁護士など――の存在を見出す。これは後に、彼が「特定領域の知識人」と名付ける役割である(「真理と権力」)。その延長線上で、『監獄の誕生』もまた、フーコー自身にとって、歴史家の立場での特定領域の知識人としての貢献であったかもしれない。
さて、本書に収められているのは、当時の状況に直接介入しようとした政治的文書だ。ただし、フーコーにとってのGIPは、政治的アンガジュマンである以上に、悲惨な事実の耐え難さとは相反するような、強烈な審美的経験でもあったと思われる。彼にとって囚人の言葉は驚嘆の対象としての「実生活の詞華集」(「汚辱にまみれた人々の生」)だったとも言えるし、特定領域の知識人は危険を恐れず真理を語ること(パレーシア)を可能にする自己陶冶の称揚へと後につながっていくからだ。
だが、本書は、フーコーの哲学的遍歴の一エピソードとしてのみ重要なわけではないし、読者はフーコーと同じ目線で読む必要はない。ここで、GIPという中継器に関わったもう一人の存在――ジャン・ジュネ――に注目することで、本書のもつ現代的意義に新たな補助線を引いておきたい。
生後三〇週で捨て子となったジュネは、放浪と窃盗と男娼としての生活のなかで、メトレ感化院(「子どもの監獄」)をはじめとして各地の監獄で服役した。その経験をもとにした小説で高い文学的評価を得た彼は、やがて一九四九年には大統領恩赦を受ける。この元囚人は、GIPには関与していたが、「監獄を皆まるで地獄のように語った。私はそれを天国にしたのだ」とアイロニカルに語って、直接的にフランスの監獄に関わる内容を寄稿はしなかったという(エドマンド・ホワイト『ジュネ伝』)。
ジュネがGIPに寄せた唯一の文章は、黒人解放を唱えて米国で弾圧を受けていたブラックパンサー党を擁護するものであった。一九七一年に獄中で射殺された党の指導者の一人ジョージ・ジャクソンに捧げられた『耐え難いもの』第3号では、ジュネ署名による序文とともに、米国の黒人たちのインタビューや資料が紹介された。戦闘的な言葉や挑発的なレトリックが用いられているものの、そこで、地域での具体的な実践の例として挙げられるのは、いたって日常的な活動、「子ども朝食プログラム」や衣服配給プログラムやクリニックの設立についてである。そして、米国の白人支配層が暴力的な弾圧を加えるほどに恐れたのは、銃による武装ではなく、草の根の活動から生まれ得る連帯だった。
二〇二〇年、黒人男性ジョージ・フロイドの警察官による殺害事件をきっかけに、人種差別と暴力に反対するブラック・ライヴズ・マター運動が全米に拡大したとき、「警察予算を打ち切れ(Defund the police)」、「警察と監獄を廃絶しろ(Abolish the police and prisons)」というスローガンがしばしば叫ばれた光景は、こうした歴史を反復している。
本書でのGIPの記録は、フーコーをめぐる思想史の一資料にはとどまらない。「耐え難いもの」には耐えないことを選び、改良された監獄ではなく、監獄そのものの廃絶された世界を想像し、それを実現するための第一級の道具でもある。(佐藤嘉幸・箱田徹・上尾真道訳)(みま・たつや=立命館大学大学院教授・生命倫理学・医療社会学・臨床神経学)
★フィリップ・アルティエール=フランスの歴史家。一九九五年から二〇一四年までフーコーセンター所長を務める。一九六八年生。
書籍
| 書籍名 | 耐え難いもの |
| ISBN13 | 9784409031384 |
| ISBN10 | 4409031384 |