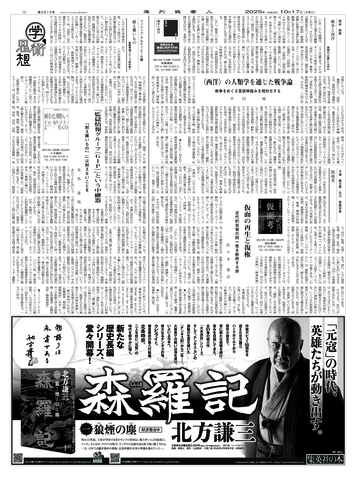- ジャンル:民俗学・人類学・考古学
- 著者/編者: 今福龍太、石川直樹
- 評者: 佐々木重洋
仮面考
今福 龍太著/石川 直樹写真
佐々木 重洋
「〈わたし〉が私ならざる仮面をかぶって変身したり自らを隠蔽したりするのではない。仮面こそが〈わたし〉という不分明な枠組みに形を与え、ダイナミックな表現を生み出す生命原理なのだ。その意味で〈わたし〉とは仮面なのである」。(11頁)
近代的自我の同一性を前提とする社会では、〈わたし〉は他者ではあり得ない。「ほんとうの」〈わたし〉は常にひとつであり、その素顔もまたひとつのはずである。仮面をかぶったとしても、その変身や隠蔽はあくまで一時的で限定的なものにすぎず、仮面をとればまた元の〈わたし〉に戻るはずだ。他者も同様だ。仮面をかぶっているとしても、玉葱の皮を剝くように暴いていけば、いつかは素顔が現われるはずだ……。
本書は、このような「はず」を根底から問い直す。本書が対象とするのは、これらの「はず」が常識となった近代社会以降に生きる仮面ではない。人間が古よりその深部において保存してきた、他の認識領域や〈わたし〉(=〈他者〉)の拡張に向かうような、より根源的な活力をもたらす文化的装置としての仮面である。その思索の旅は、日本の古寺巡礼と和辻哲郎、坂部恵から始まり、能楽、韓国の仮面劇、メキシコの仮面祭、クロード・レヴィ=ストロースの『仮面の道』の舞台、ヴァンクーヴァー島へと舞台を変えながら続く。そして、ポー、ボルヘス、アンソール、プルチネッラ、ファノン、セゼール、ボールドウィン、安部公房、セリエント、吉岡実、ベンヤミン、イェイツ、寺山修司など、古今東西のさまざまな事例を題材に、仮面が持つ潜在的な力が再召喚される。
その力は、近代的自我の同一性の解体へと向かう。自己/他者、生者/死者、現世/来世、現在/過去などを明確に区分する思考も解体の対象となる。そして、1966 年の映画『ペルソナ』を、生成AIを使ってリメイクしたスウェーデン映画、『もう一つのペルソナ』を経由して、思索の旅は再び和辻哲郎、坂部恵、そしてヴィレム・フルッサーらと合流する。そこで確認されるのは、ペルソナが唯一絶対で不変のものではなく、常に可変的でありつつもどこかで連続性を保っていること、仮面とは、他者との間―主観的な関係性のなかで、ペルソナの可変性と連続性を可能にするということである。
「〈わたし〉とは仮面である」とは、近現代的な「はず」の世界に生きる仮面とは異質の、人類の偉大な発明たる仮面の再生と復権に向けた宣言である。逆に、人々に息苦しい思いをおしかぶせるような、「はず」を強制する仮面は「槌を以てコッパミジンに粉砕」(戸井田通三)し、あるいは「ひっくり返す」(フルッサー)対象である。〈わたし〉は、無数の仮面と自在に遊び、戯れることで私になることができるのである。
ジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリは、近代の精神分析学がこうした仮面的実践や試みを理解することができず、それらを病状診断したことを批判した。自らも「分裂病」、「精神疾患」診断に悩まされたアビ・ヴァールブルグは、人間は実際に非人間にもなり得るのであり、その理解のためには古代より受け継がれた「残存」を探求する必要があることに気づいていた。「残存」のアイデアは、エドワード・タイラーに由来する。これらと同様に、リュシアン・レヴィ=ブリュルの「融即」理論も、どこかで本書の内容と共鳴しあうことだろう。それは進化主義とは別の思考回路においてである。
そのうえで、近代人が仮面とみなしたが、じつは「そうではないかもしれない」事例を対象に、思索の幅をさらに広げてみたい誘惑にも駆られる。いくつかの民族誌が報告しているように、仮面に相当する概念を持たないものの、近代人には仮面のようにみえる「何か」を使用している社会も存在する。仮面がなくても他者になることができ、「融即」が可能な事例もある。そうした人々が、近代人には仮面のようにみえる「何か」を使うということは、いったいどのように理解されるべきなのだろうか。
本書は装丁にもなかなか凝っており、手に取ったときの手触り、そしてカバーの裏面(!)にまで配慮が行き届いている。石川直樹によって随所に配された印象的な写真の数々もまた、それぞれに仮面をめぐる思索の旅に読者を誘うことだろう。(ささき・しげひろ=名古屋大学大学院教授・文化人類学・民族芸術)
★いまふく・りゅうた=東京外国語大学名誉教授・文化人類学。著書に『霧のコミューン』『クレオール主義』など。一九五五年生。
★いしかわ・なおき=写真家・登山家。
書籍
| 書籍名 | 仮面考 |
| ISBN13 | 9784750518800 |
| ISBN10 | 4750518808 |