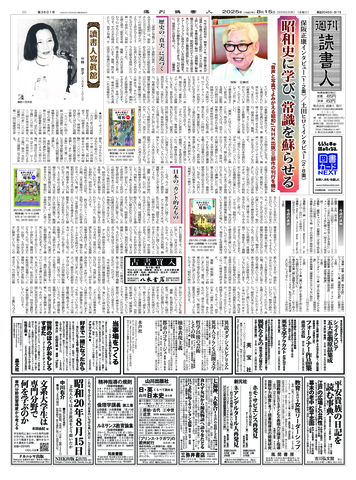保阪正康インタビュー
<昭和史に学び、常識を蘇らせる>
『音声と写真でよみがえる昭和』(NHK出版)三部作の刊行を機に
今年は昭和百年・戦後八十年。保阪正康氏が『音声と写真でよみがえる昭和』(NHK出版)を上梓した。本書は戦前編/戦中・占領期編/戦後編からなる三部作。昭和時代のすべてを振り返る本シリーズでは、活字と豊富な図版に加え、NHKアーカイブスに保存されている当時の録音を、QRコードから聴取することができる。刊行を機に、保阪氏にお話を伺った。(編集部)
――『音声と写真でよみがえる昭和』は、保阪さんと元NHKアナウンサーの村島章惠さんが、2014年から2017年にかけてNHKラジオ第一で放送した、『保阪正康と語る「昭和史を味わう」』をもとにしたものです。その大きな特長として、活字と写真、そして実際の音声、この三つの媒体から昭和史を眺める仕組みになっていることが挙げられます。どんな思いを込めてこのような仕組みを採用したのでしょうか。
保阪 この本はある意味で革命的な本だと思っています。通常、単行本は活字と写真だけで出来ています。しかし本書はそれに音も加えている。つまり三つの要素が作品の中に入っています。このようにして〝三位一体〟で歴史を見るという試みは、ある意味、出版物の次の時代の前段階なのです。というのも、次の時代では、ヴァーチャル・リアリティ(VR)が活用されるようになると考えているからです。
本書はそのVRの一歩前、現在では一番進んだメディアになったと認識しています。音を加えることで、本に含まれる各項目が生き、立体化してくるのです。活字は想像力、写真は視覚によって現実の歴史を確かめるだけだけれども、音声が入ることで解釈の幅がぐっと狭まる。それによって、事実を超え、真実により近接感を持つことができるようになります。
「近接感」を持つことは、事実の先にある真実、これを見極める一つの重要な要素なのです。活字と写真だけでは、事実こそ確認できるものの、読者の努力、推測、想像力、そうしたものすべてを駆使してもなかなか真実を見抜くことは難しい。
「真実」とはどういうことか。例えば二・二六事件というのは、活字と写真で説明される場合、〝青年将校が立ち上がって云々〟という記述で表現されます。この時はしかし、筆者の想像力によって過去の出来事が活字に表され、それに写真が付されるのみです。
ですが、ここに音声が加わることで、事実が現実のものとして、読者の目の前に再現されることになる。青年将校たちはこんな風に立ち上がったのか、それに対して当時こういう見解が出されたのか、といった、活字と写真だけではわからないことが明らかになる。本書はそのようにして、真実へとアプローチする第一歩となるメディアなのです。
人が歴史の本を読むのは、「過去にこんなことがあったんだ」「こういうやつがいたんだ」と興味をひかれ、関心を抱くからでしょう。音声は、その関心を補佐してくれます。文学や歴史において、それまで読者と著者を繫ぐのは想像力だけだった。そこに、音声が現実を差し挟んでくるのです。本書の試みによって、それまで歴史に対して鈍感で、本を読まなかったり、興味を持たなかったりする人たちが、新しい読者になっていくのではないか。こういう期待もしています。
――この本はVRの前段階のメディアとして位置づけられるのですね。
保阪 この考えには立花隆さんからの影響があります。彼の晩年に、二人だけでいろんな話をしました。立花さんは余命も限られた状況だったんですが、「やっぱり昭和史とか歴史を語ること、これを最後の仕事にしたいんだよ」と語っていました。それまでは宇宙飛行士に会ったり、脳死について議論したり、武満徹とか音楽のことをやったりしたけれど、最後は歴史の語り伝えをやりたい。なぜか。今の若い人たちはあの戦争と今とが「地続き」で繫がっているということを知らないからだと。ではそれをどうやって伝えていくのか。そこからが立花さんの凄いところです。他の人が活字で歴史を語るところ、「僕は違うやり方をやるんだ、VRでやるんだ」と言った。
VRでは、独特のゴーグルをかけて、例えば広島の原爆が現実に爆発しているまさにその場に、著者や読者が入っていくわけです。そうすると、推測や想像力を超えた、原爆の惨状のさなかに立つことになる。戦争というもの、あるいは人類のいろんな問題が、皮膚感覚で一体感をもって理解できるようになります。立花さんは、それによって歴史を語り継いでいきたいんだと言ったのです。現在でも技術開発は進んでいますが、商品化はまだ先のこと。だから、VRが普及するまでの間、本書のように音と活字と写真という三位一体で史実を伝えていくこと、これが意味を持つんじゃないかと思います。
――二・二六事件で兵士たちに投降を呼びかける音声や吉田茂の肉声を聞くと、歴史が非常に近くなった感覚を抱きます。
保阪 「戦後編」の掉尾「刊行を終えて」で紹介しましたが、最近、電車の中で見ず知らずの大学生が私に話しかけてきたんです。「昭和の時代について僕は何も知らないけれど、戦争の時代ってこうだったのかと、音を聞くことによってすごくリアルにわかりました。歴史の本はこんなふうにして書いてもらえると本当に助かります」と。もちろん、例えば平安時代の貴族の生活は録音がありません。ですが、ドラマ仕立てにして再現することは可能でしょう。そうやって、活字の本に「現実」を挟み込むことができる。本そのものが、過去と現在の「地続き」な、歴史の実証性を示すメディアになりうるのです。
――なぜ、今と「地続き」のものとして歴史を理解することが大事なのでしょうか。
保阪 日本は江戸時代265年間、ただの一度も対外戦争をしませんでした。内戦も、天草四郎のキリスト教による乱を除けば一回もない。そして近世が終わって近代が始まる明治元年、そこから昭和20年までが77年。このうち最初の27年間も、明治6年の台湾出兵を除き、基本的に戦争をしていないのです。しかし対照的に、明治27年から昭和20年までの50年。この間、日本は戦争ばっかりやっている。翻って昭和20年から今まで80年間、再び戦争をしない時代になっています。つまり、400年以上の歴史幅から見ると、日本は近代中盤の50年間以外は戦争をやらない、歴史的に極めて珍しい国でした。
そこで考えるべきは、私たちの国、国民や文化・伝統の中に、戦争をしない知恵が何か残っているはずだということです。人間は、同種同族を殺さないということを遺伝子に組み込むことはできなかった。同族殺しは不可避的に起こる。しかしこれは逆に言うと、その回避は自分たちの知性や理性で考えなさいよ、ということに他なりません。これが人類に与えられたテーマだと、私は思うのです。
例えばカント。この18世紀プロイセンの哲学者は、『永遠平和のために』という本を書きました。戦争をしないために人類はどんな社会をつくればいいか考えた本です。あるいは中国の墨子。戦国時代にあって「戦争なんか意味がない」と言って歩いた思想家です。これに対して、日本はただの一人のカントも墨子も作れなかった。ところが、300年ほどの期間、戦争をしない国でいることができていたのです。この歴史の中に、何か知恵がある。ここに日本はカント的なものを抱え込んでいる。それが何なのかということを、日本人は整理し、独自の平和論を展開していく必要がある。そのためには歴史をきちんと学ばなくてはならないのです。
そして明治後半から昭和前期までの50年間。ここで日本は、世界のどの国もやらないような馬鹿な戦争を続けてきた。近代というのは、戦争にもルールがある時代です。それにもかかわらず、日本は「ルールなど知ったことか」とでも言うような戦争をやってきた。特攻作戦、玉砕がありました。また兵士は、死者の七割が戦闘死ではなく餓死したとされます。そして1945年5月にヒトラーが倒れた後、情勢はどうなったか。日本はただ一か国で、5月から8月まで世界数十か国を相手に戦争している。この国が突如やった戦争は、驚くほど非人間的で残酷なものだったのです。
今年は戦後80年です。私たちの国の極端な歴史の中から何かを汲み取らなければ、先達に申し訳ないでしょう。「何かを汲み取る」手段として、書籍に写真だけではなく音をつけました。それによって、歴史から教訓を学んでほしいのです。
――その50年間の特異な時期、日本では、リベラルな都市エリートがモダンな文化を享受する一方で、農村は貧困に喘いでいたと本書にあります。あるいはラジオの登場があった。社会の分断や新技術の登場といった情勢は、現代に非常に似ていると思います。そう考えると、今の時代は戦争に向かっているとも感じられないでしょうか。
保阪 私は海外取材に赴き、日本と戦った国の人たちに話を聞いたことがあります。あるいは、日本を訪れた外国のメディアから取材を受けるので、彼らとよく話をします。このとき議論の前提となっていたのは、20世紀の戦争は〝原価計算〟をする戦争だったということです。これだけの金額を投じて戦争すると、これだけ人命を失う。そしてこれだけのものを得る。果たして得か損か、という計算です。
イギリスの軍事学者は言うのです。「日本の軍人は愚かだと思います」と。原価計算をこれっぽっちもやっていなかったからです。イギリスは帝国主義の親玉ですが、300年歴史を積み重ねていくうちに、帝国主義を変質させてきました。初めは、弱小国の資源を収奪し、人権を無視してきた。それが、イギリス本国に市民社会が生まれるのに伴い、自由主義的で人権も容認する形に変化していったのです。
〈1面よりつづく〉
――具体的にはどのような変化でしょうか。
保坂 例えば対中国の戦略において、イギリスは全土を支配しようなんて全然考えていませんでした。そんなことなどやっている暇がないからです。代わりに、北京や天津、広東や上海に租界地を作った。それは帝国主義が狡猾になっているということでもあるのですが、とにかく中国全土を占領しない。一方日本は、鉄砲を担いだ兵士が中国へ入っていって制圧しようとする。それを彼らは「愚かだ」と言います。中国を制圧できるわけがない。日本はまともな戦略を持っておらず、20世紀の戦争をするだけの知恵がなかったのです。
20世紀にはどの国でも既に、シビリアンコントロールが効いていて、軍事は政治の下にありました。しかし日本は逆に、軍事が政治の上にあった。政治家ではなく軍人が戦争遂行を担っていたので、勝つまでやろうとしたのです。だから外国から、「おたくの軍人は馬鹿ですね」と言われる。その通りだと思います。自国の兵士たちを平気で殺す特攻や、現地住民の虐殺。軍人としてあるまじきお粗末な戦争を続けてきた。このことを徹底的に解剖しないと、私たちの国は一歩も前に進みません。
これは決して、政治や思想の問題などではありません。常識の問題なのです。常識でものを考えたら、20世紀の文明における戦争の位置づけというものがあるはずです。しかし、日本の戦争は「そんなの知ったこっちゃない」という愚かな考えで行われてきた。日本人には、近代への理解に遅れと間違いがあったのだと、強調しなければなりません。
――近代への理解は、現在の日本も足りていないと思いますか。
保阪 日本の50年の戦争を総括する、またその戦争から学ぶという姿勢の欠落している人が社会に一定数いると思いますね。国家主義的政党などはまったくそのケースでしょう。どういうところを反省すべきなのか分かっていないから、「あの時代がいい」なんて言うのです。威勢の良かった50年の戦争時代を美化し、誤れるノスタルジーに浸っている。
帝国主義は、三つの言葉に集約して表せます。「国威」「国権」「国益」です。この三つが帝国主義の軸であり、それらを発展させること。これが一等国への道だという時代があったのです。その当時の日本にノスタルジーを抱いているような人たちは、先達の知恵を学ぼうとしない傲慢さを持っています。それを思想や政治の問題にすり替えるから政治的対立になる。そんな問題ではない。常識でものを考えなさい、ということなのです。史実を知り、真実を知るということは、常識を復権させることに他なりません。
私は日本の近代の歴史教育にすごく不満を持っています。戦前の歴史教育は皇国史観、天皇を軸とする歴史です。戦後は唯物史観ですね。歴史は科学である、科学だから一定の法則をもって進んでいく、と。しかしどちらも、思想を演繹してそこに史実を接ぎ合わせていくものとして同類です。解釈を先行させて、史実を都合のいいように当てはめている。そうではない。歴史は帰納的に下から積み上げていって、史実を検証していくものであるべきです。実証主義的にやるのが歴史なのです。
本書は、解釈を先行させていません。史実を一つ一つ提示するのみです。読者には一旦それを受け止めてもらって、それから「こんな時代は嫌だな」などと自分で解釈をすればいいわけです。
――本書「戦後編」の冒頭、「昭和史の要点は「戦争」と「天皇」と「国民」の三つの語に集約される」とあります。やはり日本の戦争では天皇の役割が大きかった。
保阪 かつて江戸時代の庶民は、天皇のことなど知りませんでした。天皇は存在しますが、政治は徳川が握っていた。朝廷はこの国の権威として幕府との関係を保っていましたが、それを庶民はあまり知る必要がなかったのです。
それに対し、近代では天皇が主権者となり、統治権も統帥権も天皇が持つようになりました。しかしだからといって、天皇がすべてを差配していたわけではない。その権力を代置させていたのです。行政は総理大臣がやる、というように。
これは憲法上不自然です。その淵源はプロイセンにあります。かの国は途中から皇帝が倒れて、まったく新しい国になってしまっている。日本はそれとは異なるのに、当時のプロイセン憲法をそのまま輸入し、皇帝を天皇と置き換えてしまった。
なぜか。幕末、薩摩・長州の下級武士が、自身の力を権威づけるために天皇を担ぎ出したからです。朝廷の権威を利用して、明治政府は作られました。逆に言うと、近代において天皇はある意味利用されてきたのです。
皇国史観は、天皇制を国家の基盤として見ます。反対に唯物史観はそれを、諸悪の根源たる資本の手先だと見る。実際には支配階級の道具として利用されていたわけですが。しかし私のたどり着いた結論は、私たちは天皇制についてもう一度、認識を改めねばならない。ここにあります。
つまり、明治天皇と睦仁、大正天皇と嘉仁、昭和天皇と裕仁、平成の天皇と明仁、令和の天皇と徳仁。彼らには、時代を画す天皇としての面と、人間としての面の二つの顔がある。すなわち、天皇は、自己の中に対立を常に抱えている。このことに他なりません。
――対立とは?
保阪 例えば明治天皇は、御前会議において日清戦争開戦を決定しました。睦仁は戦争をやりたくないが、明治天皇としてはそれをやらねばならない。伊藤博文に、「あなたがやらないと困るのだから」と説得されて、いやいやながら開戦する。日露戦争もまた、御前会議で開戦の詔を出さねばならなくなります。ですが睦仁としては、その決断を厭い、会議の場で泣いていたんですよ。
それでは、彼は戦争が嫌だから、ヒューマニストで平和主義者で非戦主義者なのか。違います。戦争に負けたら自分の代で天皇制が崩壊するから、それを恐怖しているのです。だから戦争に反対する。文人と名高い大正天皇は尚更でした。
天皇は個人としては戦争を嫌うのです。こうした齟齬を問題視した明治天皇は、東宮御学問所を設置し、のちの昭和天皇・裕仁に徹底的に帝王学を教え込むよう遺言します。担当する天皇としての時代と裕仁個人との間に齟齬を来さないよう、人格を天皇の側に一体化させる教育と言えるでしょう。しかして、昭和20年までの裕仁は、戦争への反対・賛成を超えて軍と一体化していました。そこに矛盾はない。昭和天皇はある意味で、明治天皇によって人工的に作られた天皇なのです。
そのため、彼にはかわいそうなところがあります。昭和20年になると、次のように言われることになった。「役割は変わりました。あなたは象徴天皇、人間天皇ですよ」と。裕仁は昭和64年1月に亡くなりますが、それまで彼は自分自身との葛藤のうちにありました。大日本帝国の時の天皇と裕仁は一体でしたが、それを切り離さなければならなかったからです。
その意味で、彼の戦後はずっと戦いでした。昭和63年に、生前最後の記者会見がありました。宮内記者会の記者たちが、この在位期間の中で一番記憶しているのは何かと聞くと、しばらく黙って、「何といっても、あの戦争です」と小さく呟いた。それからまた長い沈黙。会見中の姿を捉えた写真には涙が写っていました。彼はそこにきてやっと、戦前の天皇から離れ、民主主義国家の天皇というものになりつつあったのです。
平成の天皇はそれを見ていました。彼は一貫して父親を反面教師とした。「戦争はいやだ」という明仁としての思いと、平成という天皇の時代とを一体化させています。だから彼は、生前退位の際に、「平成が戦争のない時代として終わろうとしていることに、心から安堵しています」と言い、涙するのです。
そのため私たちは、明治天皇ではなく睦仁を見る、大正天皇ではなく嘉仁を見る。そういう天皇論を展開しなければいけないと思います。ちなみに、その意味で本書には〝裕仁〟の顔はほとんど入っていません。全部昭和天皇の顔なのです。
――保阪さんは『昭和史 七つの謎 part2』(講談社)などで、大略、昭和天皇は戦争に対して〝政治上・法律上の責任はないが、道徳的・精神的責任がある〟と考えていたと指摘しています。このとき、前者の責任は昭和天皇の天皇としての側面に、後者の責任は裕仁としての側面に相当すると見ていいでしょうか。
保阪 まず、昭和天皇に戦争責任があるかどうかという論争自体には、意味がないと思います。なぜなら、あるに決まっているからです。ないと言ったら、天皇を侮辱していることになる。近代社会で、その人がサインしたものについて責任を認めないなら、あらゆる契約が全部意味をなさなくなります。開戦の詔書を昭和天皇が出していながら、それには責任がないなどというのは、まったくおかしなことです。だから、これは政治や思想の問題ではありません。先ほども言ったように、常識の問題なのです。
問題はその「戦争責任」とは何か、それを天皇がどのように理解しているか、ということにあります。私は『昭和史のかたち』(岩波書店)で、昭和天皇が政治的/法律的/歴史的に責任があるかどうかと、その責任への自覚とを、図表にしてみせました。天皇は、臣下に任せたから開戦の政治的責任はないと思っている。東京裁判もそれは問わなかったと。
このことを分析するにはいくつかの尺度が必要です。①開戦・終戦の政治責任、法律的責任、経営責任、国民への説明責任といった種々の責任。②それらを天皇はどう思うのか、③また自分個人はどう思うのか。この三つの尺度を作って初めて、「私は天皇をこのように考える」ということを主張できるのです。
――本書「戦前編」冒頭には、元号というのは人々の主観的な歴史だということが書かれています。昭和は、人々の主観としてはどのような時代だったのでしょうか。
保阪 日本人の一番悪いところが、昭和10年代に露出したと言えるでしょう。たとえて言うなら、水に夾雑物が入っているとして、それを絞っていくとぽろぽろと垢のようなものが落ちていく。それが、昭和の前期に露呈した日本人の欠点だと思います。敗戦までに経験した日中戦争、太平洋戦争、それらへの突入の仕方、戦争の仕方、軍人のあり方。そういうところにおいて、最悪な部分が露出したのです。
昭和18年の8月ごろ、『皇軍史』という本が出版されます。軍人教育の本です。そこには、太平洋戦争は〝日本の原点に還った戦争である〟という主張と解される記述があります。神武天皇を戴いて神の国を作った日本という史観、その原点に賭けて戦っていると。問題はその次です。読者に〝我々はなんと幸せなんだろうか〟と伝える論理が、『皇軍史』では展開されているのです。江戸・室町・鎌倉・平安、そうした時代の政治指導者は、自分たちの使命を忘れて大名や主君に忠誠を誓っている。これは日本の誤れる歴史なのであって、我々は今、原点に還った。だから幸せなのだ、というわけです。
それを読んだとき、とても大きな衝撃を受けました。お前は何を考えているんだ、と。ここからわかるのは、私たちは昭和の全部を未だ知らないということです。昭和を知れば知るほど、私たちの国の弱さが露出していることがわかります。反対に、敗戦後、ずっと戦争をやっていない今というのは、無意識のうちに、昭和的な歴史を否定して生きているのです。そこに、我々の国のカント的なものがあると私は考えます。昭和というのは、カント的なものの現れと、最も悪いものの現れ、その両面が露呈している時期なんですね。
「天皇」「国民」「戦争」、三つを目の前に並べるとします。戦前、天皇は神で、戦後は人間となりました。国民はかつて臣民であり、今は市民です。そして戦争は、片や醜く酷い仕方で行われ、今は全然やっていない。この三つの言葉を選んでも、戦前と戦後の対照のように、極端な二つの解釈が昭和において現れるのです。
日本人は、戦前のような世界にひとたび入ってしまうと怖い。錯誤の世界に入ると、とんでもないところへと一生懸命になって進んでいく。だから、そこに入ってはいけないと、強く言いたいと思います。(おわり)
★ほさか・まさやす=ノンフィクション作家・昭和史家。「昭和史を語り継ぐ会」主宰。個人誌「昭和史講座」で菊池寛賞、『ナショナリズムの昭和』で和辻哲郎文化賞など受賞。一九三九年生。
書籍
| 書籍名 | 音声と写真でよみがえる昭和 |
| ISBN13 | 9784140819890 |
| ISBN10 | 4140819898 |