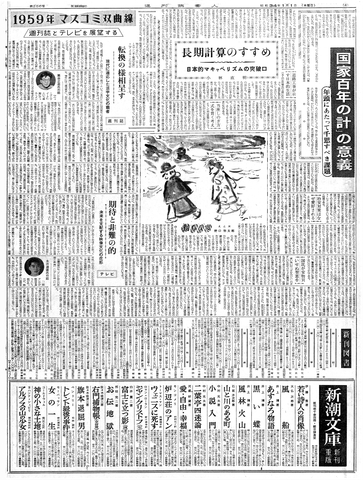大衆社会といわれる現代に生きるわれわれの特徴は何か。それは心の中にレーダーを備えて常に他人の行動に向調子ることだ、という『孤独な群衆』の著者によれば、人類のコミュニケーション史は、口頭コミュニケーションだけで組織された時代、文字および古文化の時代、電波と映像の時代という三つに大別されるという。(D・リースマン「本—精神の火薬」・『アメリカーナ』五八年七月号)
このように、大胆な説を借りていうならば、週刊誌とテレビこそ、まさに質文化と映像文化を代表するチャンピオンということになろう。しかも新たなタイプの週刊誌の誕生が予告され、民間テレビの大きな開局が決定している本年は、この両者がその主導権をかけて競いあう年だとも見られている。そこで、これから二人のチャンピオンの過去、現在、そして年頭に当たっての姿を、ひとわたり占ってみることにした。
<【週刊誌】転換の様相呈す 現代に適応した活字文化の覇者>
もはや「週刊誌ブーム」の時代は去って、「選刊誌時代」であるとさえいわれるようになった。たしかに、毎週、趣向をこらしてわれわれの前にお目見えする三十数誌の総発行部数が七〇〇万をこえ、全国の各世帯にミシンやコールド・クリームなみに普及しているという勘定になれば、そういうことになる。
しかも、週刊誌合戦の最中にある週刊誌が社会時評「今日の焦点」で「週刊誌ブームを分析する」ということが象徴しているように、現代人にとって週刊誌は一つの社会問題になって来たかの如くである。こうした問題意識に立つ週刊誌研究会編『週刊誌――その新しい知識形態』(三一新書)がようやく最近になって刊行されたので、それを手がかりに、この「現代のゴースト」に立ち向かおう。
まず生いたちの記だが、戦前、新聞の陰にかくれて「週刊朝日」「サンデー毎日」(一九二二年三・四月創刊)という二本のレールの上に乗って静かに歩みつづけてきた日本の週刊誌は、戦後もその情勢を保ちつづけていたが、ほぼ一九五〇年から大きな転換の兆候を見せはじめ、二本のレールも巾広くがっしりしたものになった。
五二年には「週刊サンケイ」「週刊読売」を加えて四本となり、翌年には「週刊東京」、五六年には出版社による初の週刊誌=「週刊新潮」を加えて大本、さらに五八年には出版社系の「週刊大衆」「週刊明星」「週刊女性自身」などを次々と加えて三十数本にまで発達したというのが、そのあらましである。
次にその表情と性格の問題に移ろう。形式面からいえば、見事な総合性(多様性か?雑多性か?)と、しかも驚くべき画一性とが誰しも感じとる第一印象である。それは内容面からいえば、解説性と娯楽性ということになるが、細かくいえば、ヒューマン・インタレスト(人間的興味)による処理、オピニオン・リーダー(意見指導者)の意見を加える、生活の案内・手引をする、生活を楽しくする説得者、という特徴とも言いかえることができる。
そしてこれらを貫くものは、セックス、犯罪、争いの三主題であり、ゴシップ精神と美談づくり、常識主義の視角であって、全体としては「消費性」をかたちづくっている。
週刊誌の機能は何か。まず、常識をふまえた上での知識提供であり、人びとの生活への道具化であろう。娯楽文化と関連した遊びと金と夢が相対的にも絶対的にも増えつつあるだけに、他の側面をなすサラリーマンも、第三次産業(サービス業)への労働力の大量流入という世界の趨勢と歩みをともにしている日本の産業構造からいって、やはり頼もしい週刊誌の読者層を形成している。
そのほか、家庭主婦、潜在失業者という読者予備軍まで控えているだけに、三十円という手頃な値段が、四十円になる傾向が見えはじめたが、ここ当分は「週刊誌時代」ということになろう。
しかも大宅壮一氏によると、「週刊誌は出版社同士の泥試合の結果、グレシャムの法則どおり、駄菓子的な質の低下競争をやっている。そこにまた、よりよき形の選刊誌が割り込む余地が出てきた。これからの週刊誌は、量より質の決戦となるだろう」(「週刊誌ブームを分析する」・『週刊朝日』五八年十月五日号)といわれているほどだ。
そこで、「週刊朝日」の今日を築きあげ、いままた新しいタイプの週刊誌を出そうと努力している朝日新聞出版局次長の扇谷正造氏に、別項のような構想の一端を語っていただいた。
ともあれ、中央公論社でも下半期に出すとみられているだけに、今年の週刊誌界は新たな転回の様相を示し始めたといえよう。
<扇谷正造氏の話>
『ニューズウィーク』という雑誌に、「ウェル・インフォームされた(よく吟味された情報を受けた)国民は平和の基礎である」という意味の言葉があるが、今度の週刊誌では、この“ウェル・インフォームド・オピニオン”(吟味された情報に基づいて作られた世論)をつくることを標榜している。
具体的に一例をあげれば、戦後アメリカの対外援助資金を各国はどう使ったか、というのに、こんな話がある。
「イタリアは教会を直した。フランスは香水と着物を買った。西ドイツは工場を作った。イギリスは労働者アパートを建てた。そして日本は? みんな食ってしまった。」
――という話がある。こういう日本人に対する評価は、日本にいては思いつかないし、わからない。というのは、裏返せば、われわれは“ウェル・インフォームド”されていないということだ。
また、警職法の問題を取り上げる場合でも、まずロンドンのお巡りさんはなぜ民衆に支持されているか、パリでは? ワシントンでは? モスクワでは?――といった具合に進め、頭ごなしに「警察は悪い」とはいわない。警察というものを社会的に必要な存在と認めた上で、その機能や制度上の問題を批判・検討するという行き方をとる。
つまり、一定の立場にとらわれずに、つねに「世界の中の日本」という角度から眺めて、掘り下げたデータと解説を提供する。そういう意味で、啓蒙的な色彩がある。
だから、部数も三十万から四十万といった線で押えていく。部数が伸びると、それに拘束されて内容を甘くする――そんなことのないようにするつもりだ。
読者対象も、大学卒でサラリーマン経歴一~十年を中心に、進歩的な経営者、中年の労働組合員、中小企業の担当者、地方の農村技術員、PTA会員などを予定しており、年齢層も、どちらかといえば中年層ということになるだろう。
遅くも春にはスタートしたい、としている。
<【テレビ】期待と非難の的 未来を支配する映像文化の花形>
「一億総白痴化」の道具だといわれながらも、テレビの普及率は目ざましく、一九五三年、その前途を危ぶまれながら発足したにもかかわらず、わずか五年にして一四〇万台に達するほどの発展をとげた。六〇年八月には三五〇万台に達すると予測されているほどである。あっという間に、電波・映像文化の王座にのしあがってしまい、既成のマス・メディアたるラジオ、映画は、その打撃を恢復する方向を探し求めているところである、といってよいだろう。
この“怪物”の異常な成長スピードに、正直なところ研究者は追いつけなかったようだ。やっと「特集:マス・メディアとしてのテレビジョン」(『思想』五八年十一月号)が、わが国の研究者のほとんど全部を動員して報告され、加藤秀俊『テレビ時代』(中央公論文庫)がまとめられたところである。だから加藤氏もいっているように、「一般化しはじめて十年ほどしか経っていないテレビについての議論は、およそすべて、いまのところアヤフヤな段階にあるので、インチキくさくならざるをえないのである」(あとがき)ということになる。
この現状をふまえて、いくつかの問題点を探ってみよう。
清水幾太郎氏は「テレビジョン時代」(特集所収)のなかでいう。
「テレビジョンは……現在を過去との関係においてとらえることは出来ても、現在を未来との関係においてとらえることは出来ない。……それは、映像化され得るものを映像化することによって、われわれを無意味な努力から解放するであろう。そして、活字を使うメディアをその本来の領域において存分に活動させるであろう。」
吉村融氏も「テレビ・コミュニケーションと人間の思考」(特集所収)のなかで、次のように述べている。
「われわれの思考活動は、言語シンボルと映像シンボルを相補的に使うことにより、一層円滑に展開していくだろう。テレビジョンと他のマス・メディアは、その各々の機能の特色を生かした分業を行うことにより、共存を続けうるはずである。」
加藤秀俊氏も「テレビ時代の思想と教育」(『テレビ時代』所収)のなかで述べる。
「……活字世代・ラジオ世代は、ややもすれば……事実的世界に足をつけることを忘れていました。テレビ世代になってやっと、事実の世界と密着したところで人生観・世界観をくみ立てる足がかりが出来上ったのです。」
いずれも文明論的な発想を根に持っていて、日本の実態調査報告とは、まだまだいえない。
ところで、現実の日本のテレビについては、「要するに子供のためのもの」「見るにたえるのは『日本の素顔』などとスポーツ中継だけである」という声があがっている。しかし、資本額の差異にもよろうが、アメリカのテレビはなかなかよいものが多く、特にエドワード・マローの番組などは、世界中の事件の現場に急行し、生の映像を撮って流すので、大変有意義だともいわれている。
また、映画的手法を使えば、かなり高級な内容を伝えることができるという意見もあり、政党の集会なども国民に見せてもよいのではないか、という声もある。
教育テレビに期待する波多野完治氏らの意見もあるが、現在の設備・機構では、早急に完全なものは望めないというのが大勢のようだ。
それにしても、「私は貝になりたい」という芸術祭参加テレビドラマのタイトルが流行語になったことの意味は大きく、現実に他のメディアへの影響は大きい。
そこで、週刊誌研究会のリーダーとして前に紹介した『週刊誌』を書きあげた東京工業大学助教授、教育社会学専攻の永井道雄氏に、テレビと週刊誌の将来の関係について、別項のような見通しを語ってもらった。
<永井道雄氏>
「一時、テレビが映画を食うという説があったが、映画は活路を発見して新しい展開を示した。テレビと週刊誌の将来も、内容的にいって、両方ともよくなるか、両方ともダメになるかのいずれかだと思う。
現在のところ、大衆芸能の側面が強すぎるが、週刊誌のほうに新しい動きがあるので、テレビもそれに応じた動きを見せるのではないだろうか。
とにかく、テレビの攻勢は週刊誌のトップ記事に新しいタイプを要求したが、逆に週刊誌はそれを逆手にとって、己れの特色を発揮して生存していくだろうと思う。」