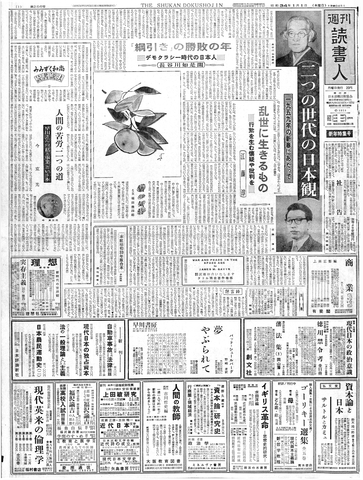日本人の性格としても、また日本文明の性格としても、多様性という特徴があって、異った時代においてはもちろんのこと、同じ時代や同じ人間にも同方の極端な性格の現われることがあるのを特徴とするが、またある場合には一方の極端が現われ、他の場合には他方の極端が現われるというようなことがある。従って「その時々の新聞などを見ただけで日本文明や日本人の性格を判断すると間違う」とよくいったものだ。そこで一九五八年という年も、その一方の極端が現われた年のように思われる。警職法とか勤務評定というのも上の方にその一方が現われたので、これに対して、労働者や日教組のような反対運動の型は下の方に他方の極端が現われたわけで、同じ時代の同じ日本人そのような両極の強く現われたのが五八年の特徴であった。がその一年の魔史によって、日本人を判断するわけにはいかない。嘔吐や下痢も胃腸そのものの病気のためのこともあり、そうでなく悪いものを食べたためのこともある。五八年の歴史のでこぼこはその前者でなく後者のように思われる。子供達に馴染まれている先生速が日教組のような運動に巻き込まれていたのも、おそらく胃腸の銀族の方でなく食あたりの方らしい。イギリス人気買のように、保守と自由の性格が正しく調合されてすこやかに育った胃腸なら、そのような嘔吐的また下痢的新状はあり得ない筈だが、そこが元来多様性をもつ上に、その関合を時に誤ることのある日本人なので、上の方の後戻りに対して下の方の行過ぎもある。長い歴史の眼でみれば心配する程でもないが、短い歴史に生きている個人としては、後戻りも行過ぎも、その直接の利害に脅かされないわけにはゆかないのである。こういう変戻りや行過ぎは、明治の中頃から、殊に大正時代からのことで、明治末からのたびたびの対外戦争も、その後戻りや行通きが今のように上下の反対に分れないで、国民全体の動きになったわけで、そうなると日本そのものが没落するほかはなく、昭和のナイヤガラに日木を落しこんだわけである。そこを思うと、両極に分れて網引をしている間は安心であるともいえる。、しかし、網引が双方互角では歴史は遊まない。どちらか一方の力が強くなってはじめて歴史は進むか退くかの動きをみせるのである。一九五八年はその網引の一年だったようで、五九年はそのどちらかの力が勝って勝敗を決する年でなければならない。・さてしからば、どちらの力が勝敗を決するか、それが五九年の課題である。そこで面白いのは、戦前の日本ではその網引の当事者だけで事が決ったので、そこでは網引の連中以外の日本人は、はじめは高見の見物をし、どちらか一方が強そうに見えてくるとその側に加勢するという、すこぶる自主性のない国民だった。ところが戦後のデモクラシー時代になると、国民そのものが綱引の双方に分れて高見の見物ではなく、個人個人が綱引の馬力のもとということになった。戦前の日本にくらべると、まるで取って付けたようなデモクラシーだと人はいうが、前述のように、元来が多様性をもった日本人なので、封建制もデモクラシーもいわゆる神武以来で、今日はじまったことではない。文学・芸術でも日本は古代からデモクラシーで、朝廷に三十一文字の歌が出来ると、東国の蝦夷までがその歌を詠んだ。上は天皇から皇族・貴族をはじめ、下は農村・漁村の男女までがその三十一文字を詠み、それが『萬葉集』という尨大な歌集となっている。そういうことは世界のどこの文明国にも例のないことである。その『萬葉集』をみても皇太子と美智子嬢の婚約などは、古代からいわゆる日常茶飯事で少しも珍らしい話ではなかった。一方では、二千年も前にあったことが現代にも行われているというのが、日本の政治・経済・文学・芸術・技術・その他文化一般にわたっても特徴だが、他の一方では昨年流行したことが今年は消えてなくなってしまうこともある。三千年の持続性を持つといえるかと思うと、一年・半年の持続性もないというのが、日本の文明の諸相である。そこを思うと、一九五八年度の、我々をむしゃくしゃさせたような話現象も、五九年、今年には姿を消すことになるかも知れない。元旦の願いといえば、そんなものである。(はせがわ・にょぜかん氏=評論家)