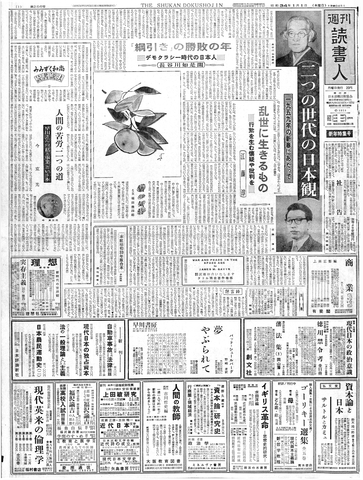実業家の著述というと大半は専門の著述業者に書かせたものが多く、その著述業者という奴が、老いぼれた文学青年上りときているから、まったく読めたものじゃない。僕はいろいろな実業家から本をもらったが、大抵は閉口頓首するのだ。ところが大阪では容易ならざる文筆家が財界にいるので驚いた。大原総一郎氏、あるいは清水雅さん、あるいは武藤糸治さん、あるいは稲畑太郎さん、あるいは辻本敬三さん等と数えると、一寸、専門の文筆業者に遜色がない人材群だ。そういう中で早川電機工業株式会社というよりシャープテレビで知られている早川徳次さんの『私と事業』(衣食住社)という著述は、最近の僕に最も大きな感動を与えたという点で、多くの人に読んでもらいたい書物だった。これはよくある成功物語でもなく、また努力型の立身譚でもない。平凡な一人の人間のまことに血の出るような苦難と、底の知れない善意と、目さましい叡智に輝いた記録に過ぎない。けれども若しこれを菊田一夫級の上手な劇作家が脚色したら、きっと多くの観衆に、というのはそれ等の観客というものは本を読まない種族だが、彼等にも感動を与えるに相違ないと思われるのだ。これを菊田一夫級の上手な劇作家が脚色したら、きっと多くの観衆に、というのはそれ等の観客というものは本を読まない種族だが、彼等にも感動を与えるに相違ないと思われるのだ。ることだ。僕の読書はおおむねこれだった。つまり本を読む覚悟をきめていて、人にも邪魔されずに読むのでなければ楽しみがないのだ。一冊の本を一週間もかかって読むなどという人は気がしれない。その僕がこんなに忙しくなると殆んど読書の時間というものが持てないのだ。仕方がないから暇にまかせて一冊づつ読むことにしている。早川住次社長の本を読んだら僕が涙が流れて仕方がなかった。こんなに泣くのは恥しいと思いながら、どうしても涙が出るのだ。人間にとって苦労というものは二つの路をとって襲いかかってくる。ひとつは苦労の方から人間に襲いかかり、もう一つは自分から苦労をこしらえて飛び込んで行くのだ。早川さんの方は苦労が襲いかかったのであり僕などは手前勝手に苦労をこしらえてそれに飛び込んで行ったのだからお話にならない。襲いかかる苦労は自分の努力によって克服することが出来るが、自分でこしらえた苦労はトートロジイというやつで次から次へ派生して来て始末が悪い。関東大震災で奥さんと二人のお子さんと財産とを一挙に失って、無一物になって大阪に転住され、今日、十億の資本の早川電気に仕立てあげた生涯は矢張り痛快な男子の一生だ。僕も、まるで都落ちといわれながら河内の貧乏寺の和尚になったが、また文学生活をはじめているのは食えない寺のせいだが、何か早川さんの半生に似ているような気がさせられた。僕はまだ成功者にはなっていないが、今後十年ぐらいは書けそうだから、それまでに少しは成功者らしい作品の一端ぐらいは残して死にたいと思う。今日のように教育が低下し、教員が堕落し、馬鹿な所行をしている限り、学校教育などに僕は期待できなくなった。そこへいくと卓川さんの『私と事業』という本は人生の案内書であり、事業の教科書だ。大阪の人は早川さんのことを、口がしまらない位に儲けてはる人だと言う表現をする。あんまり儲かるのがおもしろくて、口を開きっ放しにするという意味だろう。笑いが止まらないくらい儲けるのも人間の本懐だろうと思う。一読をすすめたい本だ。(こん・とうこう氏=作家)