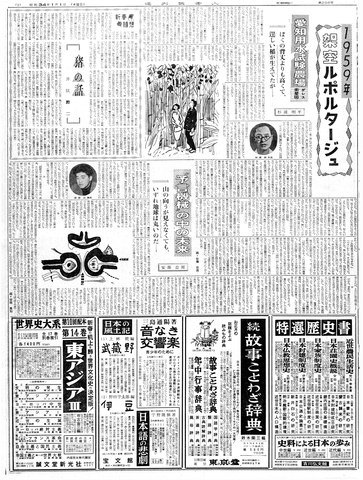巌谷大四君が来て、いきなり僕のことを亥年の生れだろうといった。だから猪について雑文を書いてくれといった。年賀葉書に猪の絵を描けというようなものである。ところが僕は亥年でなくて成年の生れである。巌谷君はしまったというように頭をかいて、いや成年生れでも何年生れでもかまわない、ともかく僕が以前よく谷川へ釣に出かけたから、猪や熊を見たことがあるだろうといった。
しかし釣をしていて猪や熊を見た人は滅多にないそうだ。僕も見たことはない。主に見るのは野鳥ぐらいなものである。たった一度、山野川で猿の群れを見かけたが、そのときでも猿の方で僕に無関心でいたのに僕の方は身のすくむ思いがした。猿の群れが人間を襲う場合には、寄ってたかって人の腕の下を擽ると聞いている。あの毛の生えた手で擦られるとしたら、想像するだけでも擦ったいような気持がする。
僕は野放しの健康な猪はまだ見たことがないが、御坂峠へ行ったとき、そこの茶店の主人の撃ちとめた猪を見た。重さ四十貫の大きな猪であった。茶店の主人はハチという優秀な猟犬を飼っている。猟も上手である。茶店の裏の尾根で猪を待ち受けて、ハチに飛びつかせて乱闘に及んだとこを覗い撃ちにしたそうであった。
ところが弾丸が急所を外れて背中に当って手負いの猪にした。普通なら猟師に向って突進するところが、どういうものか後脚が利かなくなって、前脚だけで暴れているうちに、脚をすべらして崖から転がり落ちた。その屋の下ば茶店の裏の広場である。不断、峠を越える観光バスや自動車はここに駐車して、お客がその辺をぶらついて来るのを待っている。
猪はその広場に転がり落ちた。後脚はお坐りした恰好で、前脚だけ立ててぱりばり牙を噛み合わせる音をさせた。しかし後脚が利かないから一歩も動けない。そこを茶店の主人がカメラで着色写真に写し撮って、弾丸を倹約する意味から大きな丸太ん棒で打ち殺した。僕はちょうど猪が息の根を止めたところへ行き遭わせてバスから降り後で茶店の主人がその写真を送ってくれた。雪で覆われた坂道の向うに真白な富士山が見え、それを背景にして手負いのな猪に向ってハチが吠えている写真である。猪は赤い口をあけて牙をむき出している。
この写真を読書新聞の人が貸してくれといった。それで僕は茶店の主人に手紙で許可を得てから提供したが、新聞に転載された写真では青白い雪が灰色に見え、猪の赤い口が黒くなっていた。茶店の主人の話では、猪は犬が正面から向って来ると、長い鼻先で犬を抑え伏せて牙で掬いあげる。鋭い牙だから犬は二つに割けてしまう。猪が外敵に向ってばりぱりと牙を噛み合せるのは、敵を威嚇するためばかりでなく、上顎の牙で下顎の大きな牙を緊急に研ぎすませるためでもあるそうだ。上顎の牙は小さいが、下顎の牙を研ぐのに都合よく噛み合わさるように横に突き出している。
猪の下顎の牙は、ぐっと歯齦に深く根差して生えている。だから猪突して行って、木の枝に突きあててもびくともしない。腕ぐらいの太さの木は蛇で切ったようにすぽりと切れている。その鋭い牙も手に取って見ると大して鋭いとも思われないが、鋭くする効果を出す要領を猪は心得ているらしい。牛の角なども大して先が鋭くないが、ちょっとでも人間に触ると肌が赤く剝げている。
猪を獲る方法は各地でいろいろ変っているようだ。天城の猟師の話では、ワナや仕掛鉄砲は別として、十人ぐらいで出かけて行くアテガケという方法と、勢子に追い出させる大規模な方法と、犬に追い出させる小規模のものと三種あるそうだ。御坂峠の茶店の主人の猟法は、一人で山へ出かけて犬に猪の後脚をかみつかせ、猪が怒って犬をキバにかけようとどうどうめぐりをしているところを撃つのである。眉間をねらって撃つのだそうだ。天城の猟師は、耳の付根のすぐ下を撃つのが理想的だどいっていた。柳田さんの『後狩詞記』に九州の椎葉村の猟法が書いてある。御坂峠のはちょっとこれに似通っている。
どういうものか伝承の十二支には虎とか猪とか猛獣が入れてある。だから正月だというのにこんな荒っぽい話を思い出す。先日、福山新聞という郷里の新聞に、僕の村には猪を駆遂する電気仕掛の設備が出来たという記事があった。人間には危害の心配ない新しい設備だそうである。村内の誰かが発明したらしい。とにかく珍重すべき設備だから、猪の被害を受けている遠近の人たちが、引きもきらず見物に来るといってあった。今度、郷里へ帰ったら見て来ようと思っている。(いぶせ・ますじ氏-作家)