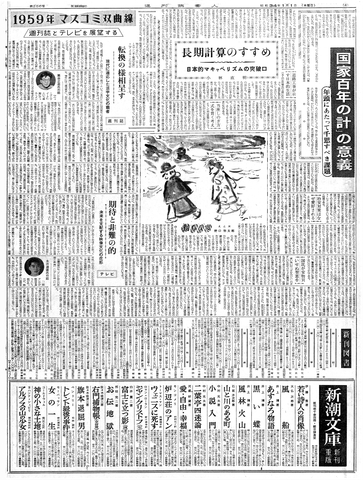「一年の計は元旦にあり」といわれる。正月元旦を起点とする一年の期間は、封建時代の昔から近頃まで、実用に即した生活のサイクルにおける最長の計算単位であったのだろう。裏から言えば、過去のふつうの日本人の生活感覚では、「一年の計」を立てることが、長期的な展望の限界だったと思われる。だから「来年のことを言えば、鬼が笑う」のである。
もちろん邦家百年の計という言葉もむかしからある。しかしそれは、白髪三千丈や八百万神のたぐいと同時に、「百」という数字によって象徴的・観念的な意味をもって語られてきたのであって、ふつうの感覚における見通しとしてのプランニングの長期は、だいたい一年で事足りたし、また可測性という点でも、それ以上の期間にわたることは、とくに封建社会では困難だったにちがいない。
これにくらべると、職後の経済再建にともなって、私経済の領域に長期計画の可能性がいちぢるしく増大したことは、たしかに注目に値する。卑近なところでは、新聞紙の広告欄をにぎわしている銀行や証券会社の「投資のすすめ」をみるがいい。そこでは、「六年半で百万円」という有名な(?)キャッチ・フレーズを始めとして、十五年から三十年というロング・タームに、市民の貯蓄計画をひきいれようとする甚だ親切な広告が――ボーナス期ともなるとほとんど毎日のように――人々に呼びかけている。
こうした長期計算による貯蓄や家計が、国民の何パーセントによって行われているかは不明だが、千億を単位として報告される貯金や投資の膨大な額をみても、また上述のような広告方式の盛んな状態をみても、どうやら「何ヵ年計画」という長期の計算を家計のなかに盛りこむ人がかなり多くなった、といってよさそうだ。
ところが、そういう長期的な計画がもっとも必要な領域、すなわち政治や国家的政策をのぞいてみれば、だれでも今更ながらにアキレかえらざるをえないだろう。日本の政治・経済・社会の全生活を見事につらぬいている特徴は、ほかならぬ長期計算の欠如だからである。
この事実を改めて見直したうえで、それがどこから生じたのか、それをどうしたらいいのかを正月の一日ぐらいついやして考えてみるのも、無意味ではあるまい。これは新年そうそう余りオメデタイ話ではないが、とくに政治家の諸氏などに年頭に深思してもらいたい問題である。
<道路工事が示す日本的生活>
日本人の生活様式の全面にわたって、長期計算がおそろしく欠けていることは、われわれ自身とその身のまわりをみても明らかだが、ここでは個人の生活態度は問題外としよう。
ここで問題とするのはだから、もっぱら政治社会の公的生活や政策に限られる。それにしても、われわれ日本人の計画性の欠如は、いったいどうしたものだろう。身近なところから、道路・住宅・都市・公園などを眺めてみればまさに一目瞭然である。大方の市民がその被害をうけている東京都の道路工事などは、眼に見ることのできる典型的な事例だろう。
市民達にとってみれば、まるで無計画としか思えないような掘っては埋め埋めては掘るの千日工事。うすっぺらでいい加減な舗装のために、都心でさえもたえず修理ばかりくりかえしているデコポコ道。その修理工事がまた非能率このうえなしの失対事業で、右から左にドロを運んで叩いているだけといった有様だから、雨でも降ったらたちまちもとの木阿弥。要するに、修理のための修理という無意味な費用が流されてゆくだけで、道路じたいは一向によくならないのである。
首都圏整備法などという甚だケッコウな「計画」がたてられている大東京の真中で、こういう情けない有様である。まして地方の住民の大部分は、雨がふればドロンコ、風が吹けばホコリだらけという「日本の道路」の被害者なのだが、この世界第一流(?)の悪路によくも辛抱づよくガマンしてきたものである。
<当座しのぎ方式を貫く考え>
こうした例は道路だけでなく、野にも山にも村にも町にも至るところに見出される。そして忘れるひまもなくやってくる地水火風すべての災害のたびごとに、自らの無計画やその場しのぎのヤッツケ仕事の愚かさを、ひとびとはいつもながら手痛い仕方で教えられているのである。にもかかわらずいい加減な堤防工事がちょっとした雨で破壊され、木と紙のバラックがたえず火災にみまわれているのに、性こりもなく中途半端な土盛りや一時的なバラック建で当座をしのいでいるのが、日本的生活様式だったといえよう。
この当座しのぎの方式の特質は、ガッチリとした基礎工事に投資しないで、その場かぎり形がつくろえば足りる、という考え方にある。さい当たり何とかなれば「明日は明日の風が吹く」だろうというわけだ。この短時間的思考様式は、今年の薪のために来年の洪水を考えないで濫伐する農夫や、今日の食事のために明日にも必要な家財を質におかねばならぬ日傭労務者だけでなく、国家の最高政策にたずさわる政治家たちにも共通した性格のようだ。
見てくれだけの仕事には熱心でも、地味な基本投資にはぜんぜん無関心だという例には、学術――とくに基礎的な学問をガッチリと育てようとする実質的な努力が歴代内閣を通じて皆無にひとしかった点にも鮮かに示される。自力で独創的な発明をなしうる基礎研究をするよりも、手っとり早く外国のパテントを買えばいいという多くの大企業の考え方も、ショート・レインジの計算という点で全く同様である。
<治安対策はなぜ愛好される>
ところで政治の短期計算は、さらに、権力者にとっては面倒くさい民主主義方式をすてて、権力による直接的な統制を呼びおこしやすい。反対者や批判者に対して、その意見を尊重しながら時間をかけてゆっくり説得するというデモクラシーの方式は、長期的には被治者の信望のうえに安定した政治の基礎をきずく最も確実な途であるが、何かの理由でそういう長期の周到方式がとれなくなると、権力はとかくその実力装置に頼りたがる傾向がある。
ここでも当座に便宜な「手っとり早い」方式として、警察権などを強化してゆく「治安対策」が愛好されるのである。それは、政治体制や政策への批判や反対の生ずる根源の理由はそっちのけにして、反対者を物理的に抑圧することによって、さしあたり治安を保つことはできても、被治者の心服や安定したデモクラシーの育成には逆効果しか持ちえないにも拘らず、短期計算的な為政家には楽でがたい魅力があるのだろう。こうした対策が、アスピリンでチフスの熱を下げようとするのと同じだということを知るには、多少とも賢明な長い眼が必要である。
そこで、よき道路やよき都市とともによき政治をわれわれがのぞむならば、何よりも先ず政治家たちに、長期計算をなしうる能力を求めなければならない。戦後の政治の経験の教えるところによると、汚職や乱闘や派閥抗争で国民にあいそをつかされた多くの為政家諸氏は、マキァベリズムの過剰によってではなくて、その欠乏によって批判さるべきであるらしい。賢明なマキァベリストならば、ぬけぬけと公約を裏切ったり、数の暴力だけで相手方をねじ伏そうとしたり、警察権の強化に狂奔したりはしないだろうからである。
<国民が安物買いせぬ智恵を>
長いあいだ「手から口へ」のまずしい生活やバラック的環境に馴らされてきた日本の国民も、近頃はようやく短期計算の損に気がつき出してきた。道路や治水や住宅などの場合には、がっちりした基礎のための投資が得だということは、今日では誰の眼にも明らかだろう。それに何よりも、太平洋戦争という恐しく膨大な犠牲を払った体験が、そもそも旧支配層の極端な短見から始まっただけに、その教訓は多くの人々の眼を開いたことも事実だ。
にも拘らず、日本の内治・外交・文教の諸政策には、未だ長期計算がひどく欠けているといわねばならぬ。むろん外交や軍事などには、予見不可能な不確定要素が多いけれども、ロング・タームの政策体系をとれば、旧来のやり方を根本的に変えるような視野がえられるにちがいない。たとえば、二千億の巨大な国費を投ずるという戦闘機の生産問題をとってみても、今の恐ろしい科学の進歩のもとでは、せいぜい十年ほどのタームをおいて利害得失を考えれば、今日のような論議は問題にならないのではないか。
国家百年の大計とまでゆかなくても、ここらで皆がイマジネーションを働かせ、せめて一世代ぐらいのタームを視野において、政治=社会問題を考えてはどうだろうか。
もっとも、政治家に向ってそんなことをいっても無駄だ、といわれるかも知れない。さし当っての利害や派閥闘争を離れては、政策はおろか地位の確保もおぼつかないような代議士たちには、選挙での得票と利権を超えた視野なぞ持てそうもないというわけだ。そうなると結局、短見で矮小な日本的マキァベリズムに、政治の知恵を強要しうる方法を国民が考えださなければならない。
それには国民じしんが、場当りな安物買いをしないだけの知恵をもたねばならないし、従来の短期的思惟方式がどこから生じてきたかをつきとめて、政治に長期計算を入れる努力をつみ重ねなければならないだろう。
(こばやし・なおき氏=東京大学助教授・法哲学専攻)