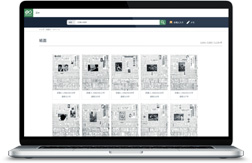お知らせ
【特別記事】西成彦×沼野充義=対談 西成彦著『移動文学論Ⅲ 多言語的なアメリカ』(作品社)刊行記念 新しい世界文学へ、「アメリカ大陸文学史」の試み

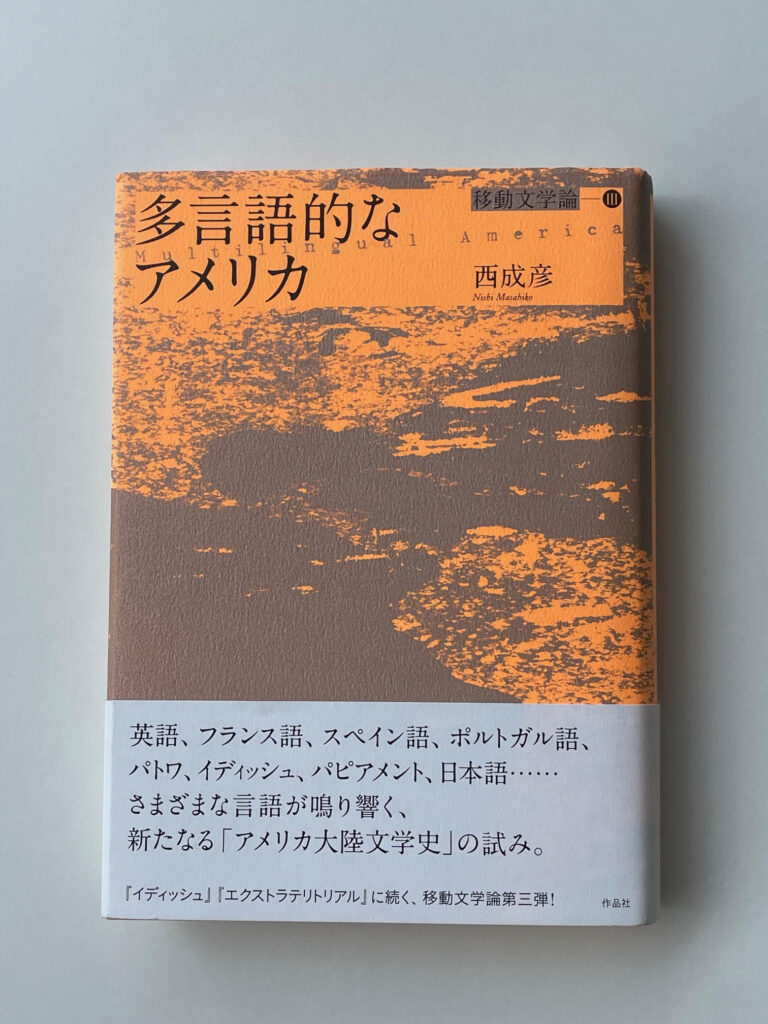
比較文学者・西成彦氏の『移動文学論Ⅲ 多言語的なアメリカ』が作品社から刊行された。本書は西成彦氏の移動文学論シリーズ『イディッシュ』『エクストラテリトリアル』に続く第三弾で、本書をもって移動文学論三部作が完結した。本書の刊行・三部作完結を機に、『亡命文学論』『ユートピア文学論』『世界文学論』で二〇二二年に「徹夜の塊」三部作を完結された沼野充義さんと対談していただいた。お二人は東欧、ロシア/ポーランドから出発しながら、西さんは「移動」、沼野さんは「亡命」というキーワードから、それぞれ国境を越えた世界文学的な視野をもって研究してこられた。同世代のお二人がお互いの仕事をどう見てきたか、密度の濃い対話が交わされた。本稿では前半部分を紙面掲載。対談全文とさらにイントロダクションとして対談動画の一部を読書人WEBにて公開する。(編集部)
沼野充義さんから西成彦さんへ
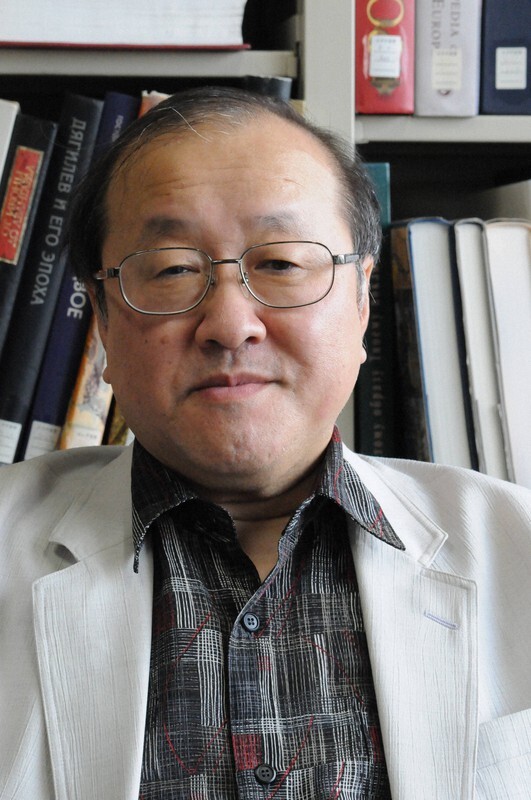
「移動文学論」三部作完結
沼野 対談の切り口として、私から感想を述べさせていただきます。西さんのこの「移動文学論」三部作はこれで本当に完結なのか、この先も続くかもしれないなとは思いつつ読んでいたのですが、とりあえず三冊目の刊行でひと区切りだと思いますので、おめでとうございます。我々は同じ世代でお互い今くらいの歳になってきますと、今までやってきたことを振り返りながら仕事を収束させていくような方向に行こうと考える人は多いと思うのですが、西さんの仕事を見ていると、年齢を重ねるに従って収束するどころかますます拡張していく、素晴らしい勢いの良さを感じさせる研究を続けられていることが、まずとても感銘を受けた点です。
西さんの「移動文学論」三部作ですが、最初に『イディッシュ』が出たのが一九九五年。この頃は移動文学という言葉自体、私もあまり耳に慣れていなくて、亡命文学や移民文学などいろいろな言い方があると思うのですが「移動文学論」という言い方をしたのは、日本で西さんが初めてじゃないかと思うんです。当時は「移動文学論」という言い方自体ちょっと奇妙な言い方だと感じたのを覚えています。『イディッシュ』、つまり東欧ユダヤ人のイディッシュ語による文学は世界中に移動していったわけで確かに「移動文学」ですが、その後こんなふうに「移動文学論」が広がり、発展していくとは想像がつきませんでした。
本書の最後の方に書かれていたように、イディッシュの次はクレオールを「移動文学論」の第二部にしてペアにしようという計画がもともとあったそうですが、そう簡単にはまとまらなかった。実際には第二部は『エクストラテリトリアル』(二〇〇八)――これはG・スタイナーのナボコフ論で使われる言葉で、由良君美さんが「脱領域の知性」と訳したのですが――いうタイトルで出されました。本書の中心はクレオールではなくて、多言語的なポーランド、多言語的東欧の内と外、それからカフカ論で、カフカ論も普通のカフカ論とは違う西流のカフカの読み、多言語的な東欧を背景にしたカフカ論と言っていいと思いますが、そういうふうに視野が広がっていった。
新たな「アメリカ大陸文学史」の試み
沼野 そして今回刊行された第三部『多言語的なアメリカ』(二〇二四)で、西さんの「移動文学論」が完結したわけですが、これは第Ⅰ章「密林の東欧ユダヤ人」に宣言されているように「アメリカ大陸文学史の試み」になっています。本書の最初の方で西さんは《今日のアメリカ大陸文学を一望に収めるには、この五つの言語に万遍なく目配りする必要がある》と書かれていて、一瞬びっくりするような書き方なのですが、五つの言語とはスペイン語、ポルトガル語、オランダ語、フランス語、英語だというわけです。そういう野心を持ってアメリカ大陸の文学というものを読み解こうとする。そして、《わが「アメリカ大陸文学史」の試みは始まったばかりだ》と書かれている。本当はもう仕事を収束させていかなければいけないような年齢に差し掛かっているはずが、ものすごく大きな企てをして、しかもそれがまだ始まったばかりだと最初に宣言されているわけで、この心意気というか壮大な意欲というのには、やはり打たれるところがありました。
三兎を追う比較文学者として
沼野 そして、言語を超えた南北アメリカ大陸全体を含めた文学史の可能性というところに、多言語的なブラジル、多言語的なカリブ海、日系移民の文学も入ってくる。それに加えて、西さんの出発点でもあるポーランドや東欧ユダヤ人の影も見えてきて、西さんはそれを南北アメリカに追っていく。多言語的な南北アメリカ大陸に対して、その多言語性を増幅させるというか、支えていくような一つの鍵として、東欧ユダヤ人というものが常に見え隠れしている。東欧ユダヤ人というのは、第一作目の『イディッシュ』から、西さんが一貫して追い求めているテーマですが、それをも取り込む形で『多言語的なアメリカ』という今回の本に結実された。
それともう一つだけ最初に申し上げておくと、やはり西さんの言葉でハッと打たれたのは、最後の「イディッシュ語を追いかけて(あとがきにかえて)」で、南米にポーランド人とユダヤ人の影を追うようになり、さらに日系人の後も追い、ポーランドとユダヤそれから日系人と“三兎を追う比較文学者になった”と、ご自分を規定されていることです。もともとポーランド、ユダヤは出発点にあったにしても、そこから外地文学という形で本来の日本の枠を広げていって日系人も視野に入れてというこのスケール。こういう形でアメリカ文学史を記述する企てに着手していることを示す、これは大変印象的な言葉でした。
西成彦さんから沼野充義さんへ
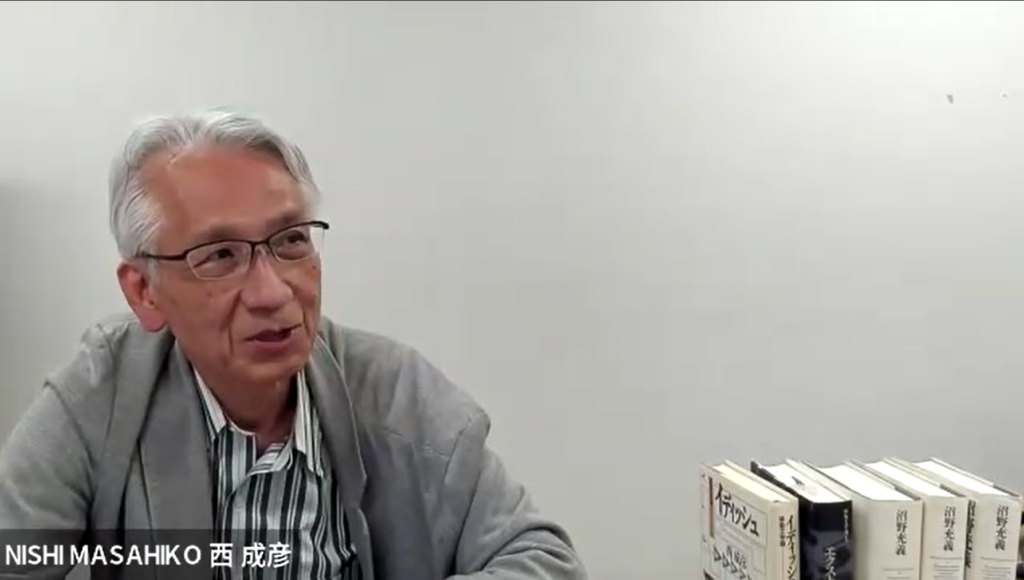
一九六〇年代、東欧世界との出会い
西 ありがとうございました。僕と沼野さんは大学に入った年も同じで、僕は関西出身で沼野さんは関東という違いはありますが、同じ日本の、同じ時代の空気を吸って生きてきたと思います。六〇年代は日本で旧チェコスロバキアの体操選手・チャスラフスカなどが牽引するかたちで東欧に関する関心が高まって、その後の「プラハの春」、そしてその鎮圧と、東欧の話題が絶えなくなっていました。『現代東欧文学全集』(全一三巻/恒文社、一九六六~六九)が出たのが、その六〇年代後半でしたし、そういう時代の空気を吸って思春期を生きてきた。
沼野さんが亡命という現象にこだわりを持たれるようになったのも、ソルジェニーツィンノーベル賞受賞(七〇年)と、その後の亡命(七四年)が大きかったと思うし、その時期には「亡命」をとりあげた本が日本でも次々に出版されました。なかでも僕の将来を左右したと今にして思うのが、河出書房新社から出た「エトランジェの文学」(全八冊、一九七四~七五)でした。そこには、ナボコフにゴンブローヴィチ、そしてコンラッドやアイザック・バシェヴィス・シンガーなどが入っていて、僕はそれを横並びに日本語で読んだわけですが、もともとは英語、ポーランド語、ロシア語、イディッシュ語と、さまざまな言語で書かれていて、しかもそれを「エトランジェ」の名でひと括りにしてある。僕が特定文学志向でなく、世界文学志向になったのは、そのあたりからです。沼野さんは研究対象としてロシア文学を選ばれましたけども、そもそもは、何でも食べちゃうような、雑食系だったのではないでしょうか。
比較文学というディシプリン
西 ただ、僕は大学院で比較文学・比較文化を専攻し、そのつながりで最初の就職先も熊本大学の比較文学講座ということになりました。つまり、そこに身を置いていさえすれば特定の文学や言語に縛られずにやれた、というか、裏を返せば特定の文学にしがみついているわけにはいかなくなった。いま指摘してくださったように日系移民やラフカディオ・ハーンに関心を持つようになったのも、熊本で、森鷗外や小泉八雲、夏目漱石など、熊本に縁のある作家に等距離で接しているうちにいつしか守備範囲が広がって、沼野さんはこの歳になってからも拡散しているとおっしゃいましたが、僕からすれば、過去に見境なく手を広げてしまったものをどうにかコンパクトにまとめるのに必死。つながりがなかったはずのものを一つの星座にまとめるために一つ一つやっているのが現状だと自分では思っています。
「移動文学」というキーワード
西 沼野さんは、移動という言葉の選択を特徴的だと言ってくださいましたけれども、その頃のはやりは越境でした。河出書房新社の『文藝』別冊で「越境する世界文学」が特集されたのが九二年。コロンブス五〇〇年の年で、ポストコロニアルに人びとの目が向き、今福龍太さんの『クレオール主義』(九一年)が出るなどして、まさに越境ブームでした。他方、川村湊さんたちが牽引されるかたちで、「外地の日本語文学」に皆の目が向くようになっていたし、ベルリンの壁の崩壊を経て、人の移動は活性化して、しかもそれは「亡命文学」の名では呼べなくなるだろう。そうした安心感もあった。
その時に、そもそもは黒川紀章さんが作られた言葉なんだそうですが、ホモ・モーヴェンス(homo-movens)という言葉が思い浮かんで、移動をキーワードにするのはどうだろうかと思いついたんです。作家たちが政治的な理由、文化的な力関係の中で移動する、あるいは植民地主義などで移動するということがあって、そこから越境的な文学が生まれてくるのですが、だったらそれを研究する研究者もまたモビリティを高めないことには取り残される。
サバルタン的なバイリンガル
西 沼野さんの初期のお仕事に『屋根の上のバイリンガル』(筑摩書房、一九八八/その後白水Uブックス、一九九六)がありますね。あの本には、ナボコフやベケットやブロツキーのようなポリグロットとも言えるようなインテリばかりでなく、むしろサバルタン的なバイリンガルたちにも目が向けられています。「君はすごいねえ、バイリンガルだねえ」と褒めてはみたものの「バイリンガルなど褒め言葉にもならない」ことに気づかされるというご自身の経験が語られるのですが、これは「からゆきさん」に向かって「旅がお好きなんですね」といって冷やかしているのに等しいんですよね。移動にも裕福な世界漫遊家のそれから、底辺の肉体労働者のそれまで大きな開きがある。バイリンガルだって同じだってことですよね。
今回の本に話を戻すと、まさに移民として、あるいは奴隷としてアメリカに渡ったような人たちは、自ずから多言語使用者にならざるを得ず、また自分たちの大切な言語の継承ができず、クレオール的な言葉を発明するしかなくなってしまった。そういった異文化接触と言語変容の実験場だったのがアメリカ大陸ではなかったか。
多言語的実験場としてのアメリカ大陸
西 東欧の亡命文学をラフカディオ・ハーンとつなげながら考えるようになったこともいまから思えば大きかったですね。いつしか、そこにはコンラッドもまた違和感なくとけこんできて。
今度の本では文化人類学の話も取り上げましたけれども、先住民たちが持っている多様な言語もさることながら、コロンブスが発見したことにされている新大陸はいろんな言語を持った人たちがぶつかり合って、共通語がない中で何とかコミュニケーションして出来上がっている世界だった。そんなアメリカ文学の実験に目を向けようということで、「僕がこれから一人で頑張りますよ」という意味ではなくて、とりあえず僕は口火を切ったから、語圏の枠を飛び越えて、みなさん集まりましょうと、そういう思いをぶつけた本なんです。
言語探偵/多言語の海を探索する
【沼野】 西さんの文学へのアプローチというのは言語探偵的な読みと言ってもいいかもしれません。作品を読む際はまず、作家が育った家庭内部の言語環境の記述に目が行くということを書かれていますね。そういう言語への関心が基本にあって、例えばコンラッドの『ノストローモ』においても、マリオ・バルガス=リョサの『密林の語り部』にしても、言語状況を一つのキーワードにして多言語の海へ探索を深めていく。これこそ西さんならではの読みで、そういった意味での言語探偵的な読みを実践しているということを、今回の本でも全体を通して強く感じました。
西 それはもうほとんど習い性になっていてそうせざるを得ない。特に日本の外地文学をやったりすると、日本人が朝鮮半島で押しつけた日本語だけで済ませていたかというと、そうでもなくてグレーゾーンがたくさんあることは本当によくわかる。アジアの大日本帝国の文学というものを見ると、そういう読み方がどうしても必要になってきたというのが現実なんです。もう一つ、宮沢賢治を論じた時に(『森のゲリラ 宮沢賢治』岩波書店、一九九七)、イーハトーブの中で動物と人間は、必ずしも同じ言葉を喋っていなかったということに気づいたのも、大きな収穫の一つでした。
沼野 西さんの読みで特徴的なのは、まずは言語への着目ですが、もう一つは多言語的、多民族的な環境の中での異なったもの同士の接触/交差、常にそこに着目するということだと思います。そこが西さんの着眼の仕方の面白いところで、普通の比較文学では比較できないようなことを大胆につなげていくわけです。今回の本の中でもラフカディオ・ハーンとコンラッドとジーン・リース、この三人はどこかで相互につながっていないかというようなことを夢想として述べていますよね。こういうふうなつながりで作家たちを読んでいくというのは、ひょっとしたら、新しい文学史的な手法になるんじゃないかなと印象づけられました。
私が西さんとちょっと違うなというところは、私は最初の専門はロシアだったわけです。ロシア語というのは日本ではマイナー言語と思われがちですが、ポーランド語とかイディッシュ語と比べたらはるかに教育・学習環境が整った言語で、明治以来のロシア文学のプレステージも非常に高いので、ロシア語の文化資本の蓄積は日本でも相当なものがある。だから、結局ロシア語一言語主義みたいな方向に優秀な専門家たちが行ってしまうわけですよね。そういう流れに抗して、西さんは一つの言語ディシプリンに閉じないように、常に自分を開いてきた。それは確かに、禁欲的に一つの専門言語に閉じこもらないで、いわば自分の興味を全部ぶっちゃけてしまうというようなやり方かもしれません。その結果、多民族的な状況の中で様々な出自の人々の交差、つながりを見て来られたわけですが、これは志向性として、そして方法として非常に重要なことだと思いました。
比較文学という講座にいたことを西さんは良かったと強調されていましたが、私から見ると、西さんは従来の比較文学という枠組みでは対応できないような世界の文学の多様性を探索してきたわけで、比較文学を超えてきたということではないでしょうか。
イディッシュとクレオール
沼野 私たちは同世代同学年で、ポーランド語も一緒に勉強しました。バイリンガルの話が出ましたから少し外国語の話をすると、チェコ語をやっている阿部賢一 さんが最近『翻訳とパラテクスト』(人文書院、二〇二四)を出されましたが、その本でも小言語の言葉は文化資本の蓄積が少なくて、教科書も学校をはじめとして言語を習得するための色んな手立てが少ない。そういう言語を日本で勉強するのは、英語などに比べるとものすごく大変だと。阿部さんは自分がチェコ語をやった例に基づいて言っているんですけれど、我々にとってのポーランド語もそうだった。
西さんは日本でどうやって勉強したらいいのかわからないようなそれ以外の言語にも、言語の探索者のように果敢に入っていったわけですよね。西さんがイディッシュ語への興味とほぼ並行していたのか前後になるのか、クレオール語に興味を持たれる。クレオールに関しては『翻訳の世界』という雑誌で「クレオール・パンチを飲み干せ」という連載をしてましたよね。
私はその一年くらい前に同じ雑誌で「言語街道交差点」という連載をしていて、後でそれが『屋根の上のバイリンガル』になったんですけど、西さんはそのほぼ同じ頃、イディッシュだけじゃなくてクレオールの方にも足を踏み入れて、連載には文法の解説も含めて楽しい実例もたくさん入っていて、私にとっては毎回読むのが楽しみな連載でした。それを後に西さんは『クレオール事始』(紀伊國屋書店、一九九九)というタイトルの本にまとめる仕事をして、今回の本でも「多言語的なカリブ」というような主題も一つの柱として入ってきています。
カリブの研究も我々より少し後の世代、マリーズ・コンデやグリッサンを研究して本を出すような大辻都さんや中村隆之さんのような研究者、もっと若い世代で中村達さんのように『私が諸島である カリブ海思想入門』(書肆侃侃房、二〇二三)という切り口で研究するような人たちが出てきましたけれど、やはりあの頃の西さんの仕事というのは際立って先駆的で新鮮でした。
イディッシュとかクレオールの両方に興味を持つとは言っても、本格的に取り組むのは普通はそのどちらか一つじゃないかと思うんですけれど、西さんはあの頃から両方並行してやっていた。日本では教科書になっていない、地図もコンパスもないような二つの言語の世界に並行して足を踏み入れていって、それらの言語の音を自分の舌で確かめながらその言語の官能性を味わっていくような、そういう言語への向かいあい方をしていく。日本で世界のマイナー言語をやるというのは環境が整っていないから大変なことではありますが、西さんにとってはやっぱりそれが面白かったわけですよね。
西 やりがいがあることでした。僕は大学の学部時代は東大教養学部教養学科のフランス科でしたから、デリダだのドゥルーズだの、いわゆるフランス現代思想というものにかぶれた時代を経験しています。七五年にドゥルーズ/ガタリの『カフカ マイナー文学のために』という本が出て、『日記』のカフカは「小文学」と言ってるだけなのですが、それをドゥルーズはマイナー文学と読みかえて、それは決してマイノリティの文学ではないと釘を刺しています。それこそ、文学自体がいろんな網の目をすり抜けていくようなそういう微粒子的な動きを示し始める、それが「マイナー文学」だというんですね。「マイノリティの文学」と「マイナー文学」、それがどう似て非なるものなのか、そこを見究めてやろうという気持ちになったというのが、一九七〇年代。
それから、沼野さんが八七年から八八年に一年間ワルシャワ大学に日本語を教えに行かれて、その翌年に僕がバトンを受け継いで、その一年、僕はまさに「動く比較文学者」でした。何度も入国出国をくりかえせるビザをもらえたことが大きかったのですが、まずゴンブローヴィチをやる以上はアルゼンチンに行っておかなくちゃと、フランクフルト経由でブエノスアイレスに出かけて行ったのが一月。その頃すでにイディッシュ文学にも興味をいだき始めていましたから、そこではイディッシュ語の本もごっそり買いこんで船便で日本に送りました。そして次は夏、ラフカディオ・ハーンが日本に来る前に滞在していたマルチニークを見ておきたくて、今度はパリを経由して飛びました。その時にクレオール語の入門書や関連書籍をいろいろ仕込んできて、片手にイディッシュ、もう一方の手にクレオールという二刀流に入ったわけです。
ポーランド体験/さまざまなマイノリティを内に秘めた国としてのポーランド
沼野 私は専門的にはロシアをやっていましたが、並行してポーランドにも常に携わっていたので、戦前まで東欧・ポーランドの置かれていた多民族的な状況の中でユダヤ人も非常に大きな存在だということはよくわかっていた。そして多民族的な共生の問題、ユダヤ人が国境を越えて越境していくという問題に触れて、ロシア文学のカノンの中に留まっていてはできないような多民族世界の探求ができないかと思うようになったわけです。私が学生の頃は、例えばナボコフみたいな作家にはロシア文学の専門家や翻訳家たちはあまり手を出していなかった。ナボコフはロシア出身のアメリカの作家だといった定義で片付けちゃってたわけです。私はこれはすごくおかしいなと思って、「亡命文学」という視点からナボコフのような作家たちもちゃんと捉えなければいけないんじゃないかと思ったわけです。西さんの場合、多言語性に着目した根っこのところには、やはりポーランド体験が大きかったんでしょうか。
西 それはそうですね。僕の場合は最初に行った外国がポーランドで、ポーランドにはポーランド文学の伝統があってという、そういうオーソドックスなモデルでポーランド文学を見るところから始めたのですが、まず僕が心を奪われたゴンブローヴィチ周辺のポーランドの作家の中にユダヤ系が非常に多かった。その多くは戦争の時に殺されたり、あるいは散り散りバラバラになったりしたんですけれども、ともかくポーランド文学と言っても、それは一筋縄ではいかない。日本も日本人だけで出来上がっている国ではないということは今では周知のことになってますけども、ポーランドもいろんなマイノリティをかかえこんだ国であり、しかもユダヤ人の場合にはイディッシュ語という言語と、それによって書かれた膨大な文献をよりどころにしている。それこそユダヤ研究所の地下室に行くとカビ臭い古いショレム・アレイヘム全集の端本が転がっていたりして、お前にやるよ、持っていっていいよみたいなことを言われたりして。ポーランドの過去をちょっと覗いたら、そこを見ないわけにはいかなくなってしまったというのが現実でした。
しかも、ポーランドは国がなかった時代が長くて、ミツキェーヴィチがコレージュ・ド・フランスでスラヴ文学を講義したり、コンラッドのように長い船乗り生活を終えてから英語で小説を書くようになった作家がいたり、ポーランドの知識人は世界を股にかけたんです。それも、彼らはただ西ヨーロッパの言語に堪能だったというだけではなく、その言語で表現する中で、やっぱりポーランド人でなきゃ言えない、アウトサイダーならではの批評精神みたいなものをぶつけていった。ポーランドの国内にもマイノリティがいるし、ポーランドの外の大国でもポーランド人がマイノリティとして悪戦苦闘している。それをまるごと見るのでないとポーランド文学史は語れないなと思ったのが八〇年代でした。そして、ひるがえり、そのモデルで日本文学史を見たらどうなるかと考えたのが『外地巡礼』(みすず書房、二〇一八)だったというわけです。
日本語が絶えず他言語と接触しながら運用された場所としての「外地」
沼野 『外地巡礼』について、西さんの外地の考え方についても伺っておきたかったんです。外地という場合、日本の旧植民地であり、日本の国内に対して外ということで、朝鮮半島とか台湾とか満州とかその辺を指すのが普通だと思うんですよね。ただ西さんはそこでアメリカ大陸の日系移民、あるいは沖縄とか北海道とかそういうところも含めて外地をかなり拡張して考えていますよね。今回の『多言語的なアメリカ』でも、「ブラジル日本人文学とカボクロ問題」の章で、ブラジルにおける日系人、日本語文学に焦点を当てていて、これも西流外地文学の探索の一つの成果かと思いました。西さんは「外地の日本文学」というものにアプローチする場合、どういう姿勢で臨まれているのでしょうか。
西 さっきの移動の話と重なるんですけども、確かに九〇年代に川村湊さんや黒川創さんたちが「異郷の日本文学」や「外地の日本語文学」というようなタームを用いて、「日本文学」という既成概念を崩していかれたのですが、その場合の「外地」は手あかのついた歴史的なタームであって戦後の日本で使うべきではないのではないか、それははっきり植民地と言い改めるべきではないかといったような議論がありました。
ただその時に僕は、だったら「外地」という言葉を、新しい操作概念として使えないか、外地という場所は日本語が唯一の言語であるような、そういう内地ではない空間で、しかしそこに日本語を継承した人間が散らばっていった場所を指すのに使えないか、そう考えたんです。ある時は日本人が奢り散らかした植民地が外地なら、逆に日本人同士が身を寄せ合うようにして日本語を話していて、片言のポルトガル語、英語しか話せない中でも何とか生き延びていった、そういう移民たちが住んでいた移住地もまた外地、そういった意味での「外地」の定義を試せないかというのが、僕がブラジルの日系文学を日本語文学のなかに位置づけようとしたときの思いでした。
それは言い換えれば、日本語が絶えず他言語との接触にさらされていた場所。それが仮に日本語で書かれていたとしても、必ずしもその日本語だけで物語が完結するはずがなく、片言のコロニア語(ブラジル移民のポルトガル語交じりの日本語)にもたれかかったり、日本人が朝鮮語を喋ったり、片言のピジン中国語で買い物に行ったりですね。そういう多言語空間を生きていた日本人の痕跡みたいなものを留めた文学を全て外地の日本語文学というふうに呼んでみたらどうなるだろうか、そんなふうに着想したんです。これは先程のポーランド型、つまり国内にもマイノリティがいるし、国外に行けば自分もまたたくまにマイノリティになってしまう、そういうポーランド人が生きてきたこの二百年間を、それを強引に明治以降の日本語使用者の文学創造に重ね合わせたのだといえなくもない。ポーランド研究から始めた人間だからやれたことだったと。
沼野 なるほど、そこはすごくよくわかります。やっぱり西さんならではの発想で、外地の日系文学に新しい光を当てることができたと思います。ブラジル研究自体は、細川周平さんの大きなお仕事もあるし、それ以外にもいろんな形でアプローチされている方がいると思いますけど、西流世界文学の三兎を追う世界文学の一つの柱として南米の日系人文学に光を当てる、これは新鮮な新たなアプローチというふうに思いました。
西 あらためて思いますが、南米に行って比較文学者としての腰が据わったと言える気がします。僕がブエノスアイレスまで足を運んだのは、ゴンブローヴィチを追っかけたただの文学散歩が目的でしたが、そこで数多くの東欧系ユダヤ人のみならず、日系人に出会っちゃったわけです。日本人の顔をした人間からスペイン語で話しかけられた。そして二〇〇二年、サンパウロ大学に招聘されて、今度こそ日系人の社会の存在感をたっぷり味わわされた。しかも、向こうに行くと、ポーランド系の人も少なくなくて、そこに行ったらポーランド語が通じるみたいな世界、あるいはイディッシュ語を話す世界もあって、自分の中でもまだバラバラだった世界が一つに収束したような感覚がありました。そこまでいくと文学散歩では済まなくて、もはや参与観察でした。日本とカリブということでいえば、ラフカディオ・ハーンという仲介者の存在が決定的な役割を果たしたのですが、アルゼンチン、ブラジルとの出会いは予想もしない結果をもたらしました。
越境文学派という流れ
沼野 私なりに世代的なことも含めて感想をもう一つ述べさせていただくと、これは自分勝手でおこがましいような話なんですが、私たちの世代の中で「越境文学派」と言ってもいいような流れが出来てきたんじゃないかと思いました。今では越境という言い方が最善かどうか分からないので、「移動文学派」と言ってもいいんですが、具体的に言えば同じ世代である西さんとか私とか今福龍太さん。それから細川周平さんは音楽学者で文学の専門家ではありませんけども、ブラジル研究で非常に大きな仕事をしていて仲間だと思っています。ほんの少し後の世代では管啓次郎さんがいて、そこからどんどん次世代につながっていくという面があります。
日本では外国文学に関わるというのは伝統的に、例えばフランス文学だったら、もうフランス語一本槍でフランス人のようにフランス語をしゃべることを究極の目標にするようなディシプリンになっていたと思うんですよ。そこを随分崩してきたのは我々の世代なのではないか、まずそういう世代的なものがあると思います。私ももともとロシア文学畑の人間ですから、従来の伝統的ディシプリンを全否定するつもりはないのですが、従来のやりかただけではどうも現代の世界の文学の多様性には対応できないんじゃないか、そういうことが分かってきた。もっといろんなやり方があるんじゃないかというのが見え始めて、我々の世代に、私の言う「越境文学派」というふうなものが出てきたという気がします。
変わりゆく世界、新しい世界文学の可能性は?
沼野 やっぱり一国一文学の城を守りながら、ディシプリンを固めていくような、旧帝大的な文学部のありかた、つまり独文学科とか仏文学科とか国文学科とかそういう縦割りのディシプリンの複合による文学への取り組みというのでは、圧倒的に多様で膨大な現代の世界文学の状況には対応できないというふうに思うんです。
これはハーバード大学のデイヴィッド・ダムロッシュという世界文学論をやっている人も書いているんですが、世界文学に携わるのは新たな正典目録を作ろうとすることではなくて、それぞれが自分の読みのモードを展開して切り拓いていけばいいんじゃないかと。何といっても世界文学って圧倒的に膨大で多様で、全体を一人で把握などできるものではない。世界の多様さに対しては、我々は謙虚であるべきだろうというふうに思います。
二〇世紀の半ばくらいまでだったら、世界ってほとんど西欧世界であって、例えばエーリヒ・アウエルバッハだとかクルツィウスだとかレオ・シュピッツァーとかルネ・ウェレックとかそういった世界文学、比較文学の大御所がいて、一人の大学者が世界そのものを全部把握できるみたいな幻想があった気がします。ただその頃の世界というのは実質的に西欧世界であって、それ以外の世界は入っていなかった。しかし、現代では一人の碩学が全部を把握するということではなくて、一人一人がそれぞれにまだ地図もできてないような未踏の沃野に踏み出していって、自分なりの道筋をつけていくしか、新たな世界文学を論ずることはできないんじゃないかな、というふうな気がしています。
西 奇しくも今回の本の巻頭には、沼野さんたちが東大の本郷に立ち上げられた現代文芸論教室が出している機関紙『れにくさ』の野谷文昭先生の退職退官記念号(第四号、二〇一三)に書かせていただいたバルガス・リョサの『密林の語り部』論(本書所収「密林の東欧ユダヤ人」)を収めまさせていただきました。先ほど僕は最初の職場が比較文学講座だったことが大きかったという話をしました。それがもしも英文学とか仏文学とかだったら、ここまで好き勝手なことはできなかっただろうと思うんです。
これは沼野さんもハーバード大学で痛感されたことなんではないかと思いますが、例えばアメリカの英文学科はシェイクスピアやミルトン、ディケンズやオースティンなど、十九世紀くらいまでを研究するセクションで、二〇世紀に入ってからは比較文学の方でカバーすることが多い。それこそジェイムズ・ジョイス研究の大家であるハリー・レヴィンは比較文学者ですよね。ジェイムズ・ジョイスを英文学者がかかえこむなんて、ありえないことのはずなんです。そういう意味で英文学研究と比較文学研究が上手に棲み分けながら、互いに支え合っている。そして日本もそうなるかなと、若い頃の僕はそんな希望をいだいていました。どこの大学でも文学部文学科には比較文学の講座があるというような環境がしだいに整っていくだろうと。
ところが、意に反して、その後は語圏の壁がさらに強化されたようにも見え、ポストコロニアル研究でさえまだまだ語圏の壁から自由ではない。そして、まさにそこに殴り込みをかけられたのが東大の現代文芸論研究室だったんだと、僕はそう理解しています。一国文学研究者が文学研究者の主流で、隙間を埋めるような文学に手を出すような人間はどこまでいっても規格外の、補佐的な存在だという構図をこわしていかないと、世界文学を幅広く論じることは難しいでしょう。これからは、外国語の研究もAIとか、頭のいい翻訳機器とかが出てくるから、人間の出る幕ではなくなるかもしれませんが、文学研究そのものの間口がどんどん狭くなっている中で、その時に一国文学の牙城を守りたい人ばかりが先頭に立って大きな声をあげている場合じゃないと思うので、現代文芸論教室みたいな場があちこちにあって、現代的な文学を研究しているような人たちがどんどんそこで教員として研究者として採用されるような仕組みが出来上がればいいなと思っています。
沼野 今おっしゃったことは、一つはもちろんアカデミックな組織の問題としてディシプリンがどう構築されるべきかという問題、それから若い研究者たちにとっては就職先がどこにあるのかという、そういう切実な問題にもつながってきます。読者の立場から見ると、これから世界の文学をどんなふうに読んだらいいのか途方に暮れてしまって、新たな指針とか、地図みたいなものが必要なのに、そういうものを得ることがそもそも難しい、という問題でもあります。
そこで西さんがどう思うかお聞きしたいのですが、もう今さら世界文学全集の時代じゃないとはいえ、例えば西さんとか私とか今福龍太さん、あるいはもっと若い人たちが入るべきかもしれませんが、そういう人たちが中心になって新しい世界文学の読み方を示すような世界文学のアンソロジーは可能だと思いますか? そんなものは今更必要ないでしょうか。
西 若い世代の人たちがそういうこともやっていたりするから、もう任せちゃっていいかなと思っていすけれど(笑)。僕はむしろキャノン(正典)として読まれているようなものが、まさにキャノンであるがゆえに、専門家に囲い込まれているという事態を打破することの方が自分の仕事だと思ってるんですね。だから柄にもなく『嵐が丘』について書いてみたり、カミュの『異邦人』を論じてみたりするんですけど、自分で新しいキャノンを作り上げるっていうよりも、その敷居やら檻やらから文学を解放していくのが自分の役まわりと思っています。いずれにせよ世界的にみて女性作家が文学の主流になってきつつあって、それに対応するのにおじさんだけの編集体制では立ち行かないだろうなと思いますが(笑)。
沼野 そういう企画を考えるときに、どうしても男性の編者に偏りがちですね(笑)。そういう男たちをヨソに女性たちが勝手に何かを作っていく時代かもしれません。(おわり)
プロフィール
★にし・まさひこ=比較文学者、立命館大学名誉教授。主な著書に『ラフカディオ・ハーンの耳』『森のゲリラ 宮沢賢治』『イディッシュ 移動文学論 I』『エクストラテリトリアル 移動文学論 II』『外地巡礼 「越境的」日本語文学論』など。近著に『カフカ、なまもの』。一九五五年生。
★ぬまの・みつよし=スラヴ文学者、名古屋外国語大学教授、東京大学名誉教授。主な著書に『屋根の上のバイリンガル』『亡命文学論 徹夜の塊』『ユートピア文学論 徹夜の塊2』『世界文学論 徹夜の塊3』など。近著に『徹底討議 二〇世紀の思想・文学・芸術』(松浦寿輝、田中純共著)。一九五四年生。