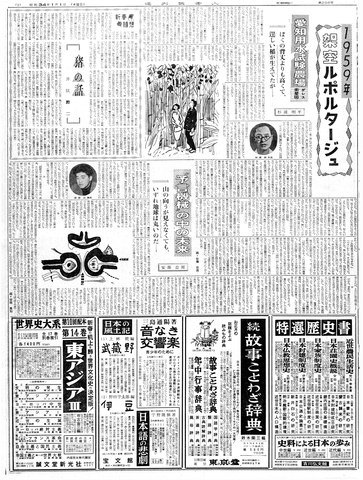誰かが言った。「百年後のことは疲れないでもないが、数年後を語るのはむつかしい時代だ」と。
なるほど、そのとおりだと私も思った。自然のリズムで時をはかっていた時代なら、近い将来の予言は、そう困難ではなかったかもしれない。社会のリズムは、はるかに緩慢で、連続的に見えたはずだから。
しかし、社会がずっと組織化されてきて、そのリズムが自然のリズムを追いこしてしまい、時の推移を、むしろ新聞のニュースではからなければならなくなった現代では、日常的な連感は、もはや未来を予測するよりどころではなくなってしまったのだ。
今日と明日は断絶し、深い湾によってへだてられている。地球が丸いことは分かっていても、山の向うに何があるのかは分からないようなものだ。戦略をたてるよりも、戦術をたてることのほうが、いっそう困難になった時代なのである。
「貴族をすべきか、乞食をすべきか、ああ、それ以外に第三の道はないか」というプロローグではじまる『乏居』を花田清輝が書き、それはむろん、革命の道を暗示するものだったが、なぜかかなりの人がこれを誤解して、平和と暴力との闘いを回避しようとする第三勢力的中立に対する風刺だと受けとったらしいのである。
作者の考えでは、おそらく「革命を平和か暴力かという二者択一でしか考えられない機械的な傾向」に対し、その新説法的な統一のうえに立った独自な——というよりも、「平和か暴力か」の選択の前に、まず革命の思想がなければならないのだという、しごく当然な革命論を主張したつもりだったのだろうが、それをまるであべこべに、しかも好意的に解釈した者がいたというのだから、なんとも不思議な話である。
作者の説明不足というよりは、やはり日々の断絶から戦術を見失った人々がいかに多いかの証拠でもあろう。さらにいえば、断絶の中にいながらそれを断絶だとは自覚せず、なおも日常的な連続感でむりに押しきろうとする焦燥感に、いかに多くの人々がしばられているかのしるしでもある。
「明日は見えるべきだ」という固定観念から、見えない明日を水に描く無駄な努力が、人を迷路に閉じこめている。
こうした未来に対する混迷は、一つには、大衆が未来に対して果たす役割が決定的なものになったにもかかわらず、というよりも、そうなったという事実のために、ありのままの大衆の姿を直視せざるをえなくなり、しかし見る目はいぜんとして「度民」か「人民」かという古い見方から脱しきれず、しぜん過大評価と過少評価のあいだをふらつく以外にない、というところからも来ているように思うのだ。
大衆が一つの観念でないことは、もう語りきったはなしである。庶民であると同時に人民でもあり、農民であると同時にプロレタリアートでもある、そうした矛盾をうちにはらんだものが大衆なのである。
時には右手の刀で、おのれの左手を切りおとし、自ら舌を噛みきったりすることもある。混乱と苦悩をうちにかくしたものなのだ。
正しく大衆を見感じようと思えば、おのれの中にも、同様な矛盾と混乱の痛みを感じとる必要があるだろう。そして、その矛盾を、そのまま実在として感じられたときに、はじめて混乱からつむぎ出される未来も予感することができるというものだ。
暗くなれば、その中にある明るさを、明るくなれば、その中にある暗さを——
だから、予感の、具体的な一つ一つにこだわる必要はない。むしろ、不定形な明日を不可視的だなどとあせったりはせずに、具体的な想像図以上に具体的なものとして感じとる精神こそ必要なのだと思う。
なおじ見えたりすることのほうが、かえって見えていないことかもしれないのである。
しかし、その不定形の明日を、ある瞬間だけとらえて釘づけにしてみることは、かならずしも不可能ではない。論議のあとには、どうしても見世物が必要だ。
さいわい私はいま、雑誌「世界」に予言機械の出てくる小説を連載中なので(その機械の使用は、なかなか手続きが面倒らしいのだが)、とくに作者の特権で、しばらく使用させてもらうことにする。
さて、何から予言してみようか。事件らしいものはさけて、むしろ日常生活の断片をとらえてみることにしよう。
ある街の、ある時刻——スイッチを入れて、ダイヤルをまわすと、ブラウン管の上にその未来像があらわれた。
それはまだ条件の不足から、混沌としてなにやら見分けがたい。そこで、未来方程式のうちの重要な変数である「大衆」の項に、ある過当な数値をはめこんでみた。
と、私はその街を歩いている。歩きなれた、平凡な道——ところがそのうち、所々に、妙な建物があることに気づく。はじめは、倒産して閉めた商店かとも思ったが、どうも様子がおかしいのである。
やがてその一軒のガラス戸が開いて、黒い服を着て黒いゲートルをはいた、三分刈り頭の男が顔をのぞけた。はて、見おぼえがある……これは警防団の服装ではないか。ダイヤルをまわしちがえて、未来ではなく過去を出してしまったのだろうか?
男が手をふって、笑いかけてきた。いや、やはり過去ではなくて、未来だったのだ。それは私のよく知っている人物で、しかもごく最近になって知り合った相手なのである。(たしか、一緒の会で仕事をしていた評論家だ。)
私は逃げ出そうとしながら、なぜか逆にそちらの方に足が向いてしまうのだ。男の笑顔は、奇妙にこわばり、私は自分がゲートルをはいていないことが、むやみに気になりだした。
私はすべて楽しんでいるような平静さをよそおい……誰もがこうした偽りのよそおいで、自らしばられていくのだと、自分の態度をいまいましく思いながらも……さそわれるまま中に入って、並んで火鉢に手をかざした。
男が便所に立った隙に、ロッカーの中をのぞくと、案の定、彼の昨日までの脱け殻がくしゃくしゃになったまま、おしこまれてあった。まったく思っていたとおりである。
だが、人間はいったい、何枚皮をもっているというのだろう? 化物の中で一番おそろしいのは、誰か自分に身近なものにそっくりで、ほとんど見分けがつかないような奴だという。
化物なのか、本物なのか、見きわめもつかないまま、その相手とつき合わなければならないとしたら、たしかにそれほど恐ろしいことはあるまい。
しかし多分これが現実なのだ。それはまた、私自身の「皮」の問題でもあるだろう。(転向の問題について、あらためて考えなおしてみる必要がある。)
男がしきりと話しかけてくる。気がついてみると、私はさっきから一言もしゃべっていないのだった。ものを言うのが恐ろしかった。何か言っても、黙っていても、厭な目にあうのは明らかだった。
追いつめられて、大衆項を元の変数に戻してやると、街の風景はふたたび混沌とした不定形にもどっている。
むろんこれが本当の未来であり、あれは架空のお伽話にしかすぎないのだ。しかし、現実にはこれと正反対の未来が現れるにしても、その中に以上のような風景が内在していることは、同様に動かせない事実なのである。
個々の未来像にこだわる必要はない。山の向うが見えなくても、いずれ地球は丸いのだ。
(あべ・こうぼう氏=作家 画・安部 真知)