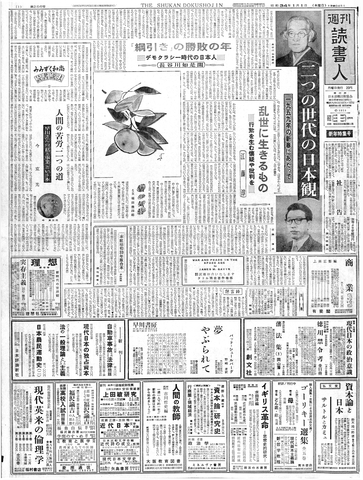われわれは、現にひとつの乱世に生きている。乱世とはなにか。出来合いの尺度や規範がすべて間尺に合わなくなりだした時代のことである。逆にいえば、出来合いの尺度や規範にすがりついて、間尺にあわない部分を無視したり圧迫しようとする連中が、必死になって時間を停滞させようとしている時代である。無理に合わせようとする力と、合わない間尺とのぶつかりあいが、われわれひとりひとりの内部でも、日常の生活でも、「政治のなかでも間断なく繰り返されているというのが実状である。この澱んだ時間のなかで、われわれは、多少の間尺の悪さはがまんしても、出来合いの秩序や規範に調子を合わせて生きることを強いられている。そして、そうするうちに、少々面白くなくとも、とにかく「秩序」の方が「乱世」よ」り安全だと考えるようになる。さらに最後には、現在の社会が永久不変の動かしがたい岩のようなものだと信じるようになり、「乱世」に生きているという自覚を失ってしまう。しかし、それでも居「心地の悪さがのこるのは当然であって、この焦立ちは、ある朝目が覚めてみたら一切が変って良くなっているのではないか、という莫然とした期待となってわれわれの心にひそんでいる。皇太子妃決定の時のあの気狂いじみたお祭りさわぎは、この期待の爆発以外のなんだといえるか。こうした英雄到来を待ちのぞむわれわれの女性的な憧れは、あの戦争が天皇の鶴の一声でおしまいになったという記憶とわかちがた"く結びついているであろう。身は波まかせ、風まかせ、自分の力ではなにもできないという諦めが最高の美徳とされ知恵とされる。そして出来合いの秩序や規範にしたがうことが良識とされる。このような時代は偽善の欧眉する時代である。まず乱世の現実から眼をそむけて安逸にのがれようとするのが第一の偽善である。自らの不満や焦立ちを現実に行動にうつすことなく、合わない間尺にあわせて便々たる卑屈さは第二の偽善である。またこのような時代には科学的な意匠で装飾された安易な道徳主義が流行する。ほどほどの改良主義や庶民崇拝の人道主義的口吻をもらすてあいが横行する。しかし、「乱世」にきれいごとのヴェールをかぶせても秩序は回復されない。「乱世」を「乱世」と見、すべてが流動しつつあること、出来合いの規範が一切可変なものだということを認識することから、新しい秩序をつくりあげよ。うとする行動が開始される。あの強力な岸内閣といえども磐石だはない、人間の意志によってよろめきもすれば、弱体化もするということをわれわれは昨年の秋識ったばかりである。現在は恒に停滞した時間ではない。そのなかに現在そのものを否定する契機がかくされているということを、「乱世」ほど明瞭に露呈する時代はない。間尺にあわない秩序は、あう秩序に変えていけばよい。自分の行動を一々出来合いの権威や尺度にあわせて、正しいだろうか間違っているだろうかなどと右顧左べんす。るのは馬鹿げている。議論に価値があるのはそれが行動の前提になるときだけである。そうでなければ、それはガマの油売りの口上と変りがないことになる。しかも行動のエネルギーは道徳的な、紳士的なお説教からは生れはしない。間尺にあわない秩序をあう秩序に変えることは、到底数人の英雄のよくするところでもなければ、火エンびんやジグザグデモのよくするところでもない。われわれはまず出来るかぎり広く連帯し、間尺にあわないものの存在を恐怖しそれを抹殺しようと狂奔している既成秩序の固守者たちに、彼らの行動がいかに非実際的で馬鹿げているかを知らせる説得の論理をつくっていかなければならないであわれわれは権力の前にかしこまって善政を願う「庶民」などではない。万事に受身で瞳れてばかりいる感傷的な二た昔ほど前の女学生でもない。われわれが共有するのは自分でやらなければ誰もやってはくれないという積極的な姿勢である。乱世のなかから生い立って来た民主主義の論理が、当然実現されるべきだという要求である。盆とか正月とかいうものはほっておいてもまわって来る。しかし停滞した時間はわれわれが動きろう。出さなければ前に進まない。確なものがあるから行動するのでない。確実にするために行動すのである。この世のどこに確実ものがあるかなどと思い入れてるのは乱世に生きるものの態度はなかろう。ホップスやマキャェルリはそのように返巡することによって『レヴァイアサン』や『君主論』を書いたわけではない。製疑や批評は必然的に行動を生む。そうでない懐疑や批評は死をもたらすにすぎない、と私は考える。(えとう・じゅん氏=評論家)