記事 1959-01-01
1–15 / 15 件
-
 お正月のあそびといえば、かるたに双六、羽根つきにタコあげ──と、相場がきまっている。そのそれぞれのゲームは、民俗学的にも、コミュニケーション的にもきわめて面白いし、とくに「いろはかるた」については、鶴...
お正月のあそびといえば、かるたに双六、羽根つきにタコあげ──と、相場がきまっている。そのそれぞれのゲームは、民俗学的にも、コミュニケーション的にもきわめて面白いし、とくに「いろはかるた」については、鶴... -
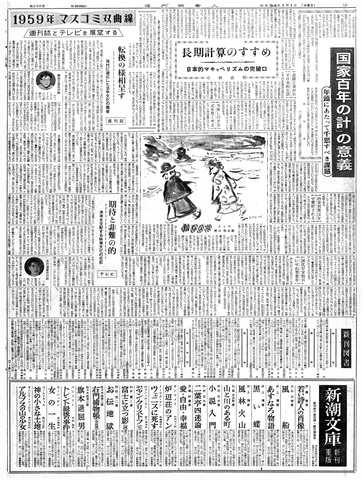 大衆社会といわれる現代に生きるわれわれの特徴は何か。それは心の中にレーダーを備えて常に他人の行動に向調子ることだ、という『孤独な群衆』の著者によれば、人類のコミュニケーション史は、口頭コミュニケーショ...
大衆社会といわれる現代に生きるわれわれの特徴は何か。それは心の中にレーダーを備えて常に他人の行動に向調子ることだ、という『孤独な群衆』の著者によれば、人類のコミュニケーション史は、口頭コミュニケーショ... -
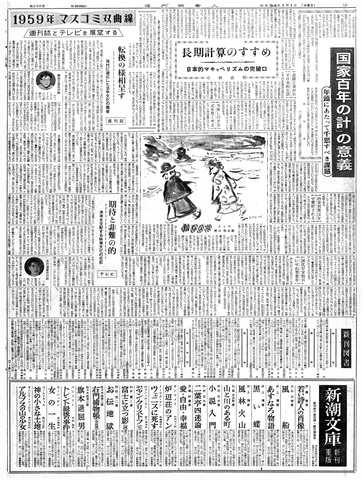
- [週刊読書人]1959/01/01号
- ジャンル:
- 評者: 野口弥太郎
〇⋯伊勢神宮の初もうで、五十鈴川の清流のほとり、エメラルド色の水面を見ていると、青や赤の魚が流れをさかのぼっているのが見える。水に洗われた紺色にかがやいた敷石と玉砂利のほとりに、いつ現われたのか二重マ... -
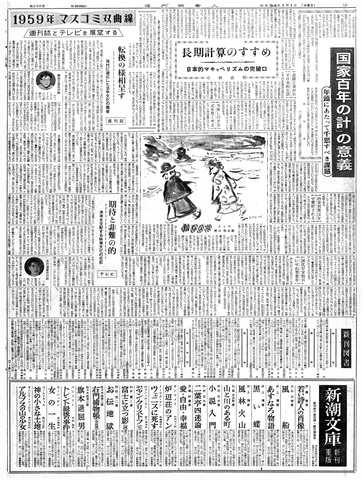 「一年の計は元旦にあり」といわれる。正月元旦を起点とする一年の期間は、封建時代の昔から近頃まで、実用に即した生活のサイクルにおける最長の計算単位であったのだろう。裏から言えば、過去のふつうの日本人の生...
「一年の計は元旦にあり」といわれる。正月元旦を起点とする一年の期間は、封建時代の昔から近頃まで、実用に即した生活のサイクルにおける最長の計算単位であったのだろう。裏から言えば、過去のふつうの日本人の生... -
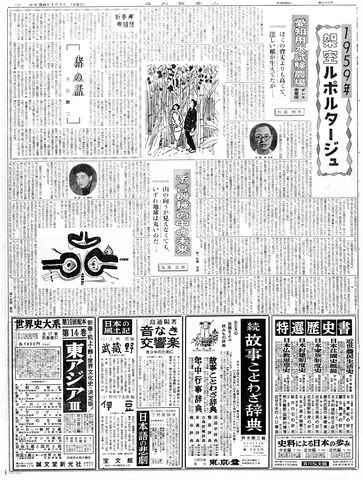
-
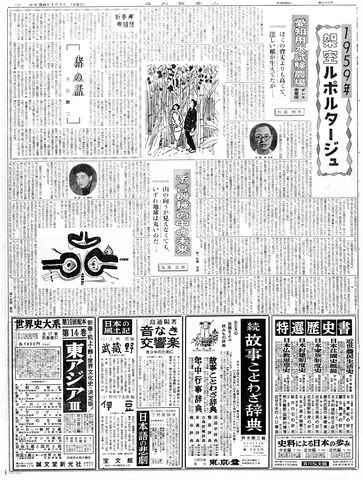 誰かが言った。「百年後のことは疲れないでもないが、数年後を語るのはむつかしい時代だ」と。 なるほど、そのとおりだと私も思った。自然のリズムで時をはかっていた時代なら、近い将来の予言は、そう困難で...
誰かが言った。「百年後のことは疲れないでもないが、数年後を語るのはむつかしい時代だ」と。 なるほど、そのとおりだと私も思った。自然のリズムで時をはかっていた時代なら、近い将来の予言は、そう困難で... -
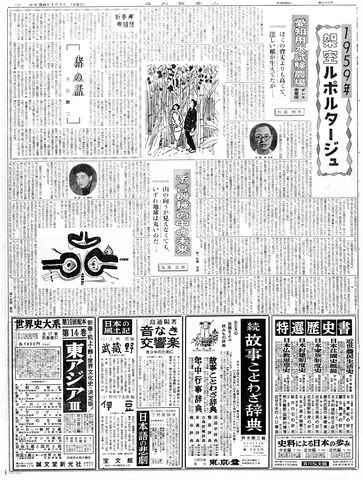 ほととぎす大竹藪を洩る月夜 こいつは色蕉の旬だったかな。わたしは、両側から竹かすすきのような葉が頭の上におおいかぶさって、昼なお暗い小路に立って、ちょっとそんなことを考えた。というのは、絶えず烈しい...
ほととぎす大竹藪を洩る月夜 こいつは色蕉の旬だったかな。わたしは、両側から竹かすすきのような葉が頭の上におおいかぶさって、昼なお暗い小路に立って、ちょっとそんなことを考えた。というのは、絶えず烈しい... -
 最後十四年目を迎えた今年は、一昨年来、論環をにきわしてきた日本文化論があらたな応用を期待されている年でもある。そこで本紙ではかねてからこの問題に深い関心を示している桑原武夫(京大人文科学研究所教授・フ...
最後十四年目を迎えた今年は、一昨年来、論環をにきわしてきた日本文化論があらたな応用を期待されている年でもある。そこで本紙ではかねてからこの問題に深い関心を示している桑原武夫(京大人文科学研究所教授・フ... -
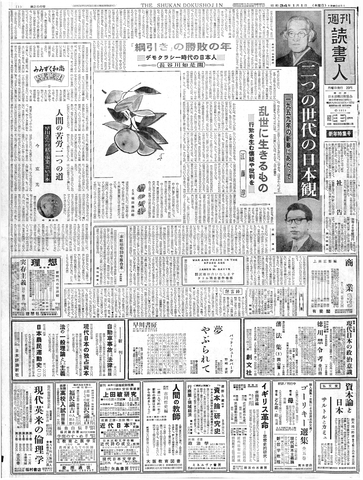 実業家の著述というと大半は専門の著述業者に書かせたものが多く、その著述業者という奴が、老いぼれた文学青年上りときているから、まったく読めたものじゃない。僕はいろいろな実業家から本をもらったが、大抵は閉...
実業家の著述というと大半は専門の著述業者に書かせたものが多く、その著述業者という奴が、老いぼれた文学青年上りときているから、まったく読めたものじゃない。僕はいろいろな実業家から本をもらったが、大抵は閉... -
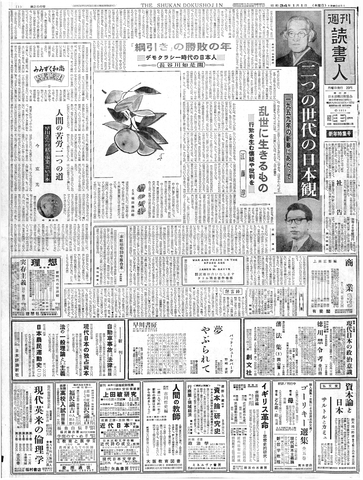 われわれは、現にひとつの乱世に生きている。乱世とはなにか。出来合いの尺度や規範がすべて間尺に合わなくなりだした時代のことである。逆にいえば、出来合いの尺度や規範にすがりついて、間尺にあわない部分を無視...
われわれは、現にひとつの乱世に生きている。乱世とはなにか。出来合いの尺度や規範がすべて間尺に合わなくなりだした時代のことである。逆にいえば、出来合いの尺度や規範にすがりついて、間尺にあわない部分を無視... -
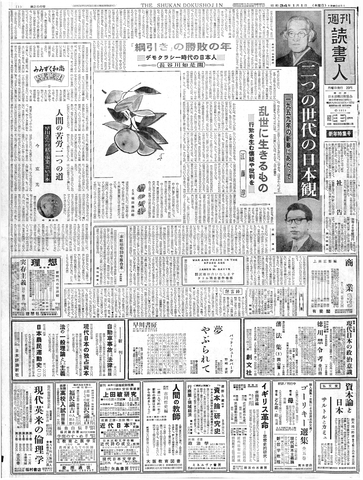 日本人の性格としても、また日本文明の性格としても、多様性という特徴があって、異った時代においてはもちろんのこと、同じ時代や同じ人間にも同方の極端な性格の現われることがあるのを特徴とするが、またある場合...
日本人の性格としても、また日本文明の性格としても、多様性という特徴があって、異った時代においてはもちろんのこと、同じ時代や同じ人間にも同方の極端な性格の現われることがあるのを特徴とするが、またある場合... -

-

-

-

- ←前へ
- 次へ→


